茶道具 短冊 直筆
楽天市場検索
レディースファッション (1) (茶道具 短冊 直筆)
メンズファッション (0)
インナー・下着・ナイトウェア (0)
バッグ・小物・ブランド雑貨 (0)
靴 (0)
腕時計 (0)
ジュエリー・アクセサリー (0)
キッズ・ベビー・マタニティ (0)
おもちゃ (0)
スポーツ・アウトドア (0)
家電 (0)
TV・オーディオ・カメラ (0)
パソコン・周辺機器 (0)
スマートフォン・タブレット (0)
光回線・モバイル通信 (0)
食品 (0)
スイーツ・お菓子 (0)
水・ソフトドリンク (0)
ビール・洋酒 (0)
日本酒・焼酎 (0)
インテリア・寝具・収納 (0)
日用品雑貨・文房具・手芸 (0)
キッチン用品・食器・調理器具 (0)
本・雑誌・コミック (0)
CD・DVD (0)
テレビゲーム (0)
ホビー (457) (茶道具 短冊 直筆)
楽器・音響機器 (0)
車・バイク (0)
車用品・バイク用品 (0)
美容・コスメ・香水 (0)
ダイエット・健康 (0)
医薬品・コンタクト・介護 (0)
ペット・ペットグッズ (0)
花・ガーデン・DIY (0)
サービス・リフォーム (0)
住宅・不動産 (0)
カタログギフト・チケット (0)
百貨店・総合通販・ギフト (0)
レディースファッション (1) (茶道具 短冊 直筆)
メンズファッション (0)
インナー・下着・ナイトウェア (0)
バッグ・小物・ブランド雑貨 (0)
靴 (0)
腕時計 (0)
ジュエリー・アクセサリー (0)
キッズ・ベビー・マタニティ (0)
おもちゃ (0)
スポーツ・アウトドア (0)
家電 (0)
TV・オーディオ・カメラ (0)
パソコン・周辺機器 (0)
スマートフォン・タブレット (0)
光回線・モバイル通信 (0)
食品 (0)
スイーツ・お菓子 (0)
水・ソフトドリンク (0)
ビール・洋酒 (0)
日本酒・焼酎 (0)
インテリア・寝具・収納 (0)
日用品雑貨・文房具・手芸 (0)
キッチン用品・食器・調理器具 (0)
本・雑誌・コミック (0)
CD・DVD (0)
テレビゲーム (0)
ホビー (457) (茶道具 短冊 直筆)
楽器・音響機器 (0)
車・バイク (0)
車用品・バイク用品 (0)
美容・コスメ・香水 (0)
ダイエット・健康 (0)
医薬品・コンタクト・介護 (0)
ペット・ペットグッズ (0)
花・ガーデン・DIY (0)
サービス・リフォーム (0)
住宅・不動産 (0)
カタログギフト・チケット (0)
百貨店・総合通販・ギフト (0)
458件中 61件 - 90件
1 2 3 4 5 6 7 8
| 商品 | 説明 | 価格 |
|---|---|---|
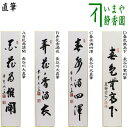 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 百花為誰開 長谷川大真筆又は弄花香満衣 長谷川大真筆又は春水満四澤 長谷川大真筆又は春色無高下 長谷川寛州筆 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者長谷川大真筆 春色無高下のみ:長谷川寛州筆 箱たとう紙 注意メール便不可 (R5/棒丸・岡・15890) 【コンビニ受取対応商品】百花為誰開ひゃくかだがためにひらく 春が来てたくさんの花が開くのはいったい誰に見せるためか。せっかく満地の花をなぜか見て取れないのかという意味が込められている。 弄花香満衣はなをろうすればかおりこももにみつ 花を摘んでいると、自分の衣も香りに包まれ、こころまで花と一体となって、清々しい境涯に至る。 「花の香り」を良い教えと考えますと、徳や良い教えに触れると、気付かぬうちに影響を受けます。そのありのままの姿が自然の真実であるということ。 春水満四澤しゅんすいしたくにまつ 春になり、雪解けの水が何処の沢にも満ち溢れ、万物を潤している、という意味です。 春が来て、春の雪解け水(春水)が四方の沢/あらゆる沢(四沢)満ちあふれ、やがて大河となって滔々と流れて行くように、仏の慈悲があまねく沁み渡り、私どももその恩恵に与っている、とも解釈されます。 中国東晋時代の詩人陶淵明の『四時の詩』(春水満四澤 夏雲多奇峰 秋月揚明輝 冬嶺秀狐松)の初句です。 春色無高下しゅんしょくこうげなし 春の光はわけへだてなくふりそそぎ、何を見ても春の風情に満ちあふれている。 平等と差別の混然とした中に心理のあることを表現した意味。 【長谷川大真】三玄院 臨済宗 大徳寺塔頭 1957年昭和32年2月 出生 1979年昭和54年 駒沢大学卒業 大本山相国寺 (梶谷宗忍管長)僧堂にて修行 1997年平成09年08月 三玄院住職 ------------------------------ 【三玄院】大徳寺 一五七九年に、春屋和尚を開祖に、石田三成・浅野幸長・森忠政の三人が建てた寺で、沢庵和尚・千宗旦の修道場として著名です。 春屋和尚の弟子には、徳川幕府の悪令に対抗して大徳寺の面目を天下に示した玉室・江月宗玩和尚がおられます。近衛信尹・久我敦通・古田織部・藪内剣仲・小堀遠州・黒田長政・桑山重晴・瀬田掃部・山岡宗無等が参禅した事もつとに知られます。また、石田三成・古田織部の墓があり、茶室は古田織部の設計による篁庵があります。 ------------------------------ 【長谷川寛州】 老師 臨済宗 大徳寺 紫野 三玄院 元住職 | 12,705円 |
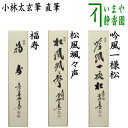 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 福寿又は松風颯々声(松風颯々聲)又は吟風一様松 小林太玄筆 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者小林太玄筆 箱たとう紙 注意メール便不可 (目吉丸大・20800) 【コンビニ受取対応商品】福寿ふくじゅ 幸福で長命であること。 松風颯々声しょうふうさつさつのこえ松風颯颯声・松風颯颯聲・松風颯々聲 謡曲『高砂』の「千秋楽」に「千秋楽は民を撫で、萬歳楽には命をのぶ。相生の 松風、颯々の聲ぞ楽しむ、颯々の聲ぞ楽しむ。」とある 身も心も松風につつまれ穏やかな、無我の境地 吟風一様松ぎんぷういちようのまつ 松はみな同じように風に梢を鳴らしている。寒山の居する深山の様子を語ったもの。 【小林太玄】黄梅院 大徳寺塔頭 1938年昭和13年 奉天生まれ 1961年昭和36年 花園大学卒業 相国僧堂に掛塔 大津暦堂に参禅 1975年昭和50年 大徳寺塔頭 20世 黄梅院に就任 | 16,940円 |
 〇【茶器/茶道具 短冊】 直筆 渓泉清流又は春水満四澤 松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) 箱たとう紙 注意メール便不可 (R5/野山丸岡・4650) 【コンビニ受取対応商品】渓泉清流けいせんせいりゅう 渓泉(けいせん)とは谷間に湧く泉。そこから流れ出した細い清流がかすかな音をたてている。深山の閑(しず)かなたたずまい。 春水満四澤しゅんすい、したくにみつ 春になって雪解け水が何処の沢にも満ち溢れ、萬物を潤している。やがて、大河となり滔々と流れていく。 【松濤泰宏(松涛泰宏)[まつなみたいこう]】 前大徳寺 鷲峰山、寿福寺第50世住職(福岡県) 1960年昭和35年 生まれ 1972年昭和47年 得度 1982年昭和57年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂初掛塔 1984年昭和59年 福岡大学卒業 1987年昭和62年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂再掛塔 1990年平成02年 臨済宗大徳寺派、三等地寿福寺住職 ----------------------------- 【寿福寺】山号 鷲峰山 福岡県福岡市 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 1190年代に臨済宗の開祖 明庵栄西禅師(建仁寺開祖)によって禅宗に改宗され江戸末期から明治の初期に大徳寺派の末寺になる | 3,550円 |
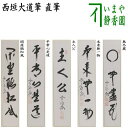 〇【茶器/茶道具 短冊】 直筆 閑座聴松風又は平常心是道又は主人公又は本来無一物又は無尽蔵 西垣大道筆 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 箱たとう紙 作者西垣大道筆 注意メール便不可 (R5/野輪大・2910) 【コンビニ受取対応商品】閑座聴松風かんざしょうふうをきく 一切の雑念を捨て、静かに 座ってただ松風の音を聴く。 心が急いでいれば気付かぬことが多い。 静かに座って耳を 済ませば澄み渡った音が聞こえてくる。 静かに座って、松の間を吹く風の音(釜の湯の沸く音)を聴く 平常心是道びょうじょうしんこれどう 端的に言えば、尽十方界(宇宙・大自然)の絶え間ない活動は常に「平常底」であり真実であるということを表現している。自然界の変化に係わることなく、普通に日々を過ごしている様。 道は知に属せず、不知に属せず。普段の心が悟りである。 主人公しゅじんこう 瑞巌(ずいがん)和尚は 「おーい、主人公(自分)よ。ちゃんと目を覚ましているか?」と、自分で自分に問いかけ、 「大丈夫だ」と、自答する。 「世間に流されるなよ」 「大丈夫だ」 そうやって、自分自身に声をかけては自分で答えていたことから主人公という禅語は生まれた。 本来無一物ほんらいむいちぶつ 本来、執着すべきものは何もなく空であるという意味。 無盡蔵むじんぞう(無尽蔵) この宇宙に生きるにあたって、全てを投げ捨てて無一物に徹すれば、逆に全てが無尽蔵に湧き出てくるとの意味です。 【西垣大道】極楽寺 兵庫県城崎 1942年昭和17年 庫県に生まれる。 1949年昭和24年 分山宗興について得度。日本社会福祉大学卒業後、大徳僧堂、のち相国僧堂に掛塔。 1976年昭和51年 仏教大学大学院修士課程修了。 1978年昭和53年 兵庫県城崎郡の大徳寺派極楽禅寺住職に就任し、現在に至る。 | 2,909円 |
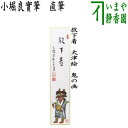 〇【茶器/茶道具 短冊画賛】 直筆 放下着 小堀良實筆 大津絵 鬼の画 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 箱たとう紙 作者小堀良實筆 注意メール便不可 (R5/輪野中・4400)〇5325 【コンビニ受取対応商品】放下着ほうげじゃく 「放下ほうげ」とは、投げ捨てる、放り出す、捨て切るの意です。「著じゃく」は命令の助辞じょじで、放下の意を強めるために用います。「放下著」、すなわち煩悩妄想はいうに及ばず、仏や悟りまでも捨て去る、すべての執着を捨て去れ、すべてを放下せよという事。 【小堀良實(りょうじつ)】寶林寺 山号を曹渓山 大徳寺派 (臨済宗) 1972年昭和47年 京都市:大徳寺:弧蓬庵の次男に生 1996年平成08年 花園大学卒業 博多 崇福寺専門道場にて修行 2004年平成16年 寶林寺住職 ------------------------------ 【寶林寺】 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 寶林寺 山号を曹渓山は 禅宗の祖と言われる達磨大師より、6代目慧能禅師が、この地に来りて、仏法を解きて以来、禅の宗風喩々隆盛となる。開山、春嶺紹温禅師(大灯国師より204世)は寛文年間亀岡の地に来りて創建し、曹渓山寶林寺と名付けられた。 山内には、重要文化財(旧国宝)の薬師・阿弥陀・釈迦の三如来の仏像と九重石塔婆等があります。 | 4,259円 |
 〇【茶器/茶道具 短冊】 直筆 薫風自南来 松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) 箱たとう紙 注意メール便不可 (野礼岡/R5/野目り・4650)4440 【コンビニ受取対応商品】薫風自南来くんぷうじなんらいくんぷうみなみよりきたる 初夏の爽やかな風が南より吹いてくる 。 風香る五月。 新緑の香りをのせた南風は、執着やわだかまりのない心爽やかな悟りの心境にたとえられる。 南から薫風が吹き殿閣を涼しい心地良い空間にすると。続けて、蘇東坡が、天下万民が住みよい世にしてこそ、天子たる処なり、と付け足した。 【松濤泰宏(松涛泰宏)[まつなみたいこう]】 前大徳寺 鷲峰山、寿福寺第50世住職(福岡県) 1960年昭和35年 生まれ 1972年昭和47年 得度 1982年昭和57年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂初掛塔 1984年昭和59年 福岡大学卒業 1987年昭和62年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂再掛塔 1990年平成02年 臨済宗大徳寺派、三等地寿福寺住職 ----------------------------- 【寿福寺】山号 鷲峰山 福岡県福岡市 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 1190年代に臨済宗の開祖 明庵栄西禅師(建仁寺開祖)によって禅宗に改宗され江戸末期から明治の初期に大徳寺派の末寺になる | 3,718円 |
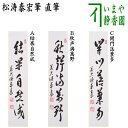 〇【茶器/茶道具 短冊】 直筆 結果自然成又は秋声満萬野又は開門落葉多(落葉多開門) 松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) 箱たとう紙 注意メール便不可 (野山丸岡の礼り・4650)4440 【コンビニ受取対応商品】結果自然成けっかじねんになる 禅宗の初祖菩提達磨大師が慧可に伝えた伝法偈の中の一句と伝えられており「一華開五葉」と対句を成している。 「吾れ本と茲の土に来たり、法を伝えて迷情を救う。一華五葉を開き、結果自然に成る」 深遠な佛法の真髄が込められた妙句であるが、一般には「開く」「成る」という言葉の連想から開運吉祥の語として古来愛唱されてきた。 やれるだけのことを精一杯やったら、あとは自然に果実が実るのを待てばいい 秋声満萬野しゅうせいばんやにみつ 秋の気配を知らせる「声」です。これが萬野、つまり至る所に満ち満ちているというのですから、もうすっかり秋で素晴らしい景です。 開門多落葉もんをひらけばらくようおおし(開門落葉多) 『禅林句集』五言対句に「聽雨寒更盡、開門落葉多」(雨を聴いて寒更尽き、門を開けば落葉多し) 雨音を聴いているうちに寒い夜更けが過ぎ、夜が明けたので門を開けてみると、あたり一面に葉が落ちていた。 一晩中聴いていた雨音は、朝になってみれば、実は軒端をたたく落ち葉の音だったという幽寂な閑居の風情、つまり、雨音とばかり思っていた音が、実は落葉の音と知った瞬間、悟りを開いた瞬間を表しています。【禅語大辞典より】 【松濤泰宏(松涛泰宏)[まつなみたいこう]】 前大徳寺 鷲峰山、寿福寺第50世住職(福岡県) 1960年昭和35年 生まれ 1972年昭和47年 得度 1982年昭和57年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂初掛塔 1984年昭和59年 福岡大学卒業 1987年昭和62年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂再掛塔 1990年平成02年 臨済宗大徳寺派、三等地寿福寺住職 ----------------------------- 【寿福寺】山号 鷲峰山 福岡県福岡市 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 1190年代に臨済宗の開祖 明庵栄西禅師(建仁寺開祖)によって禅宗に改宗され江戸末期から明治の初期に大徳寺派の末寺になる | 3,550円 |
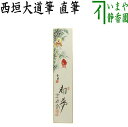 〇【茶器/茶道具 短冊画賛 御題「夢」】 直筆 初夢 西垣大道筆 十日えびすの福笹の画 曽根幸風画(肉筆画) (干支巳 御題夢) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者字:西垣大道筆 画:曽根幸風画 箱たとう紙 注意メール便不可 (野申丸R6/N・/1-・・大・4356)〇5025 【コンビニ受取対応商品】初夢 新しい年を迎え、最初に寝た日の夜に見る夢のこと。 大晦日の夜から元日にかけて見る夢を指すと考える人も多いでしょうが、元日から2日にかけて見た夢とする説が一般的といわれています。 十日えびす(十日戎) 関西を中心に毎年1月10日に行われる。 七福神の一人、えびす様に商売繁盛や豊漁などを祈願するお祭りのことです。 縁起物の熊手や福笹という笹の葉に縁起物を結んだ物を買い求めます。 福笹は諸説ありますが、 ・えびす様の釣り竿が竹でできていて、その竿にあやかってできた ・笹は氾濫の多い水辺でも生命力が非常に高く育ち、また食品の殺菌効果があるため神社のお清めなどに使われていたから などが主な理由と考えられています。 【西垣大道】極楽寺 兵庫県城崎 1942年昭和17年 庫県に生まれる。 1949年昭和24年 分山宗興について得度。日本社会福祉大学卒業後、大徳僧堂、のち相国僧堂に掛塔。 1976年昭和51年 仏教大学大学院修士課程修了。 1978年昭和53年 兵庫県城崎郡の大徳寺派極楽禅寺住職に就任し、現在に至る。 ------------------------------ 【曽根幸風】 1936年昭和11年 京都粟田口生れ 1956年昭和31年 京都府立陶工専修校(陶画科)終了 (故陶師高嶋光楽のもとで作陶師事) 1957年昭和32年 故陶師人間国宝富本憲吉先生に陶画師事 1973年昭和48年 京都洛東 東山に開窯(幸風窯) 1978年昭和53年まで京都東山の窯元で作陶に修行 1989年平成01年 京都 伏見に移窯 (茶道の陶画を通じ絵画に励む) | 4,312円 |
 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 紅炉一点雪 有馬頼底筆 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ並巾:約縦36.3×横6cm 箱たとう紙 作者有馬頼底筆 注意送料無料 (R5/ス吉り・19120) 【コンビニ受取対応商品】紅露一点雪こうろいってんのゆき 煩悩妄念を断滅した坐禅三昧の正念のある処、ここにはどんな邪念も寄せつけない。迷妄、邪悪は、恰も紅蓮の炎をあげて赤々と燃え盛る炉の上に、一片の雪花が舞い落ち、一瞬のうちに溶けて跡形もなく消えてしまうかのようだ。 【有馬頼底(号 大龍窟)】萬年山相国承天禅寺 相國寺派 臨済宗 7代管長 京都仏教会 理事長、日本文化芸術財団 理事 久留米藩主 有馬家(赤松氏流)の子孫 (東京にて華族の家系に生まれ、天皇陛下のご学友となる) 1933年昭和08年 有馬本家当主有馬頼寧の従兄弟にあたる分家有馬正頼男爵の次男として東京で生を受ける 1941年昭和16年 8歳の時、大分県日田市の岳林寺で得度 1955年昭和30年 22歳 京都臨済宗相国寺僧堂に入門。大津櫪堂老師に師事 1968年昭和43年 相国寺塔頭大光明寺住職 1971年昭和46年 相国寺派教学部長 1984年昭和59年 相国寺承天閣美術館設立により事務局長 1988年昭和63年 京都仏教会理事長に就任 1995年平成07年 臨済宗相国寺派七代管長(相国寺132世)に就任・・・・・・・・ | 17,325円 |
 〇【茶器/茶道具 短冊】 直筆 一期一会又は和敬清寂又は松無古今色又は本来無一物 松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) 箱たとう紙 注意メール便不可 (野山丸岡り野山リ井・4650) 【コンビニ受取対応商品】一期一会いちごいちえ 茶の湯、茶会では毎回一生に一度という思いをこめて真剣に行うことをといた語 一生に一度しかない出会い。一生に一度かぎり。 和敬清寂わけいせいじゃく 茶道の心得を示す言葉 意味は、主人と賓客がお互いの心を和らげて謹み敬い、茶室の備品や茶会の雰囲気を清浄にすることという意である。 茶道における「利休の四規七則」と言われ、 一、茶は服のよきように点て 二、炭は湯の沸くように置き 三、花は野にあるように 四、夏は涼しく冬は暖かに 五、刻限は早めに 六、降らずとも傘の用意 七、相客に心せよ というものです。 弟子が「茶の湯の極意を教えて欲しい」と願ったのに対し、千利休はこの四規七則を答えたとされています。 松無古今色まつにここんのいろなし 松の翠は四季を通じ、今昔なくいつもみずみずしく茂っている意味。 本来無一物ほんらいむいちぶつ 本来、執すべきものは何もなく空であるという意味。 【松濤泰宏(松涛泰宏)[まつなみたいこう]】 前大徳寺 鷲峰山、寿福寺第50世住職(福岡県) 1960年昭和35年 生まれ 1972年昭和47年 得度 1982年昭和57年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂初掛塔 1984年昭和59年 福岡大学卒業 1987年昭和62年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂再掛塔 1990年平成02年 臨済宗大徳寺派、三等地寿福寺住職 ----------------------------- 【寿福寺】山号 鷲峰山 福岡県福岡市 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 1190年代に臨済宗の開祖 明庵栄西禅師(建仁寺開祖)によって禅宗に改宗され江戸末期から明治の初期に大徳寺派の末寺になる | 3,905円 |
 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 阿吽又は汲尽西江水又は山花開似錦又は潤水湛如藍 松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 箱たとう紙 作者松濤泰宏筆 注意メール便不可 (R5/野山丸岡・4440) 【コンビニ受取対応商品】阿吽あうん 初めにある阿と終わりにある吽。密教では、この2字を万物の初めと終わりを象徴するものとし、菩提心と涅槃(ねはん)などに当てる。 仁王(におう)や狛犬(こまいぬ)などにみられる、口を開いた阿形(あぎょう)と、口を閉じた吽形(うんぎょう)の一対の姿 吐く息と吸う息。呼吸。 相対・対比など相対する二つのものにいう語。 一口汲尽西江水いっくにきゅうじんすせいこうのみずいっくにきゅうじんすさいこうのみず[一口吸盡西江水](くみつくすせいごうのみず) 一滴の水が大海の水にあたると、どちらが上とも下ともない。 『馬祖語録』、『龐居士語録』他. 大河の水を一口で飲み尽くす。 生半可な状態に停まらず、余すところなく一切を吸収し、 天地万物と一体となり無になれ。 仏法の自我、平常の意 山花開似錦さんかひらいてにしきににたり 真理の法身と、肉身とは決して別物でない。 瞬時に散ってしまう花がそのまま堅固な法身なのだ。 潤水湛如藍かんすいたたえてあいのごとし 水は無色だが満々と湛えた淵では深い藍 のような色になる。変化の中に不変の真理が宿っていること 【松濤泰宏(松涛泰宏)[まつなみたいこう]】 前大徳寺 鷲峰山、寿福寺第50世住職(福岡県) 1960年昭和35年 生まれ 1972年昭和47年 得度 1982年昭和57年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂初掛塔 1984年昭和59年 福岡大学卒業 1987年昭和62年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂再掛塔 1990年平成02年 臨済宗大徳寺派、三等地寿福寺住職 ----------------------------- 【寿福寺】山号 鷲峰山 福岡県福岡市 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 1190年代に臨済宗の開祖 明庵栄西禅師(建仁寺開祖)によって禅宗に改宗され江戸末期から明治の初期に大徳寺派の末寺になる | 3,550円 |
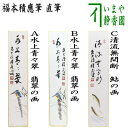 ◎【茶器/茶道具 短冊画賛】 直筆 水上青々翠 翡翠の画(川蝉の画)又は清流無間断 鮎の画 福本積應筆 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 箱たとう紙 作者福本積應筆 注意メール便不可 (R3/1-1り・5500) 【コンビニ受取対応商品】水上青々翠すいじょうせいせいたるみどり 水上には青々とした美しい水草. はかない世にあっても 、初夏の息吹が輝いて、その美しさを変わらず呈している。 清流無間断せいりゅうかんだんなし 清らかな流れが、絶え間なく続く様。 常に活動する ものは、尊い清流のように、新鮮さを持ち続ける。 不断の努力修行が大切であるの意 【福本積應】 1930年昭和05年 京都に生まれる 1959年昭和34年 大徳寺派招春寺(京都府船井郡)住職を拝命 1983年昭和58年 大徳寺派宝林寺(亀岡市)兼務住職を拝命 1989年平成01年 宝林寺本堂・庫裏・山門を建立 2002年平成14年 招春寺本堂・山門を建立 2004年平成16年 宝林寺を後任住職に譲 再度招春寺住職を拝命 | 4,950円 |
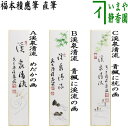 【茶器/茶道具 短冊画賛】 直筆 渓泉清流 福本積應筆 めだかの画又は青楓に渓流の画又は青楓に杭の画 濱田松陽画 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者字:福本積應筆 画:濱田松陽画 箱たとう紙 注意メール便不可 渓泉変る(輪輪り・5500)〇5940 【コンビニ受取対応商品】渓泉清流けいせんせいりゅう 渓泉(けいせん)とは谷間に湧く泉。そこから流れ出した細い清流がかすかな音をたてている。深山の閑(しず)かなたたずまい。 【福本積應】 1930年昭和05年 京都に生まれる 1959年昭和34年 大徳寺派招春寺(京都府船井郡)住職を拝命 1983年昭和58年 大徳寺派宝林寺(亀岡市)兼務住職を拝命 1989年平成01年 宝林寺本堂・庫裏・山門を建立 2002年平成14年 招春寺本堂・山門を建立 2004年平成16年 宝林寺を後任住職に譲 再度招春寺住職を拝命 ------------------------------ 【濱田松陽】 1928年昭和03年 兵庫県に生まれる。 サロンドパリ委員 明石美協理事 個展15回受賞数回 | 4,400円 |
 〇【茶器/茶道具 短冊】 直筆 昨夜一聲雁(昨夜一声雁)又は秋空一聲雁(秋空一声雁) 松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) 箱たとう紙 注意メール便不可 (R5/野山丸岡・4650)4440 【コンビニ受取対応商品】昨夜一聲雁さくやいっせいのかり(昨夜一声雁) 昨夜雁が一声鳴いて空を渡っていった。 雁の一声がまるで秋を呼び起こしたようにすっかり秋色が深まっている様子。 秋空一声雁しゅうくういっせいのかり[秋空一聲雁] 雁の声が一声秋空に響いた。 天下のもと、どこも秋の気配に満ちている。 【松濤泰宏(松涛泰宏)[まつなみたいこう]】 前大徳寺 鷲峰山、寿福寺第50世住職(福岡県) 1960年昭和35年 生まれ 1972年昭和47年 得度 1982年昭和57年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂初掛塔 1984年昭和59年 福岡大学卒業 1987年昭和62年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂再掛塔 1990年平成02年 臨済宗大徳寺派、三等地寿福寺住職 ----------------------------- 【寿福寺】山号 鷲峰山 福岡県福岡市 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 1190年代に臨済宗の開祖 明庵栄西禅師(建仁寺開祖)によって禅宗に改宗され江戸末期から明治の初期に大徳寺派の末寺になる | 3,550円 |
 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 無事是貴人又は白珪尚可磨又は主人公 松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) 箱たとう紙 注意メール便不可 (野山丸岡の礼り・4650) 【コンビニ受取対応商品】無事是貴人ぶじこれきにん 禅でも茶道でも、何の計らいもなく自然法爾に徹する人を最高の人とするという意味。 白珪尚可磨はっけいなおみがくべし(白圭尚可磨) 完全無欠の貴重な玉でも、さらに磨き続けるべきであるという意味。 主人公しゅじんこう 瑞巌(ずいがん)和尚は 「おーい、主人公(自分)よ。ちゃんと目を覚ましているか」と、自分自身に声をかけては自分で答えていたことから主人公という禅語は生まれた。 【松濤泰宏(松涛泰宏)[まつなみたいこう]】 前大徳寺 鷲峰山、寿福寺第50世住職(福岡県) 1960年昭和35年 生まれ 1972年昭和47年 得度 1982年昭和57年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂初掛塔 1984年昭和59年 福岡大学卒業 1987年昭和62年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂再掛塔 1990年平成02年 臨済宗大徳寺派、三等地寿福寺住職 ----------------------------- 【寿福寺】山号 鷲峰山 福岡県福岡市 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 1190年代に臨済宗の開祖 明庵栄西禅師(建仁寺開祖)によって禅宗に改宗され江戸末期から明治の初期に大徳寺派の末寺になる | 3,905円 |
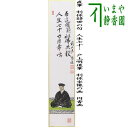 〇【茶器/茶道具 短冊画賛 利休忌】 直筆 利休辞世の句 人生七十… 戸上明道筆 利休坐像の画 円香画 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者戸上明道筆円香画 箱たとう紙 注意メール便不可 (輪棒中)(・6360) 【コンビニ受取対応商品】利休辞世の句 人生七十力圍希咄(りきいきとつ)吾這(わがこの)宝剣祖仏共殺(そぶつぐせつ)堤ル我得具足(ひっさぐるわがえぐそく)の太刀今此時ぞ天に抛(なげうつ) 利休忌は現在、3月27日および3月28日に大徳寺で行われている。 表千家家元では、ひと月送りにして、新暦3月27日に利休忌の行事が催されています。 裏千家家元では毎年3月28日、全国の社中参列のもと、茶室「咄々斎」で、茶家 最大の行事・利休忌が開催されます。 【戸上明道】玉瀧寺 1935年昭和10年03月 三重県玉瀧(伊賀市)に生る 1958年昭和33年03月 龍谷大学卒業 1960年昭和35年04月 大徳寺専門道場掛塔 (小田雪窓老師に師事) 1964年昭和39年07月 立命館大学院修了 1977年昭和52年03月 玉瀧寺住職 1990年平成02年02月 前住位稟承 2006年平成18年06月 閑栖 ------------------------------ 【玉瀧寺】 玉瀧寺 吉祥山 三重県北伊賀(現伊賀市) | 5,692円 |
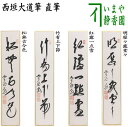 〇【茶器/茶道具 短冊】 直筆 松無古今色又は竹有上下節又は紅露一点雪又は明歴々露堂々 西垣大道筆 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 箱たとう紙 作者西垣大道筆 注意メール便不可 (R5/野輪大・2910) 【コンビニ受取対応商品】松無古今色まつにここんのいろなし 松の翠は四季を通じ、今昔なくいつもみずみずしく茂っている意味。 竹有上下節たけにじょうげのふしあり 竹には上から下まではっきりと節がついていて、差別具体の世界を対比させた言葉。 紅露一点雪こうろいってんのゆき(紅炉一点雪・紅爐一点雪) 煩悩妄念を断滅した坐禅三昧の正念のある処、ここにはどんな邪念も寄せつけない。迷妄、邪悪は、恰も紅蓮の炎をあげて赤々と燃え盛る炉の上に、一片の雪花が舞い落ち、一瞬のうちに溶けて跡形もなく消えてしまうかのようだ。 明歴々露堂々めいれきれきつゆどうどう 明らかにはっきりと顕われていて、隠すところなどすこしもない、という意味。英語では【clearly apparent and openly exposed】などと表現できます。 【西垣大道】極楽寺 兵庫県城崎 1942年昭和17年 庫県に生まれる。 1949年昭和24年 分山宗興について得度。日本社会福祉大学卒業後、大徳僧堂、のち相国僧堂に掛塔。 1976年昭和51年 仏教大学大学院修士課程修了。 1978年昭和53年 兵庫県城崎郡の大徳寺派極楽禅寺住職に就任し、現在に至る。 | 2,909円 |
 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 松風又は閑座聴松風又は松風塵外心又は松風颯々聲(松風颯々声) 松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) 箱たとう紙 注意メール便不可 (R6/野山丸~R7野吉丸岡・4650) 【コンビニ受取対応商品】松風しょうふう・まつかぜ 松に吹く風。松籟(しょうらい)。 茶の湯で、釜の湯の煮え立つ音。 閑座聴松風かんざしょうふうをきく(閑坐聴松風) 一切の雑念を捨て、静かに 座ってただ松風の音を聴く。 心が急いでいれば気付かぬことが多い。 静かに座って耳を 済ませば澄み渡った音が聞こえてくる。 静かに座って、松の間を吹く風の音(釜の湯の沸く音)を聴く 松風塵外心しょうふうじんがいのこころ 松風の音(湯が沸き、茶釜が鳴る音)に心が洗われ、世俗の塵から解放される心境をいい、茶室では俗事を忘れ、釜の湯の煮える音に耳を傾けなさいという意味。 松風颯々声しょうふうさつさつのこえ(松風颯颯声・松風颯颯聲・松風颯々聲) 謡曲『高砂』の「千秋楽」に「千秋楽は民を撫で、萬歳楽には命をのぶ。相生の 松風、颯々の聲ぞ楽しむ、颯々の聲ぞ楽しむ。」とある 身も心も松風につつまれ穏やかな、無我の境地 【松濤泰宏(松涛泰宏)[まつなみたいこう]】 前大徳寺 鷲峰山、寿福寺第50世住職(福岡県) 1960年昭和35年 生まれ 1972年昭和47年 得度 1982年昭和57年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂初掛塔 1984年昭和59年 福岡大学卒業 1987年昭和62年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂再掛塔 1990年平成02年 臨済宗大徳寺派、三等地寿福寺住職 ----------------------------- 【寿福寺】山号 鷲峰山 福岡県福岡市 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 1190年代に臨済宗の開祖 明庵栄西禅師(建仁寺開祖)によって禅宗に改宗され江戸末期から明治の初期に大徳寺派の末寺になる | 3,718円 |
 〇【茶器/茶道具 短冊】 直筆 一雨潤千山又は千山添翠色 松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) 箱たとう紙 注意メール便不可 (野山丸岡の目り・4650) 【コンビニ受取対応商品】一雨潤千山いちうせんざんをうるおす ひとしきりの雨があらゆる山を潤す。炎早(えんかん)の地に恵みの雨が降りそそぎ、潤いを取り戻して植物が生き生きと蘇る爽やかな夏の情景。一雨は、みなに平等に行き渡る。一雨は、一粒の信念であり、一粒の愛である。わずかに身を濡らすだけの雨も見渡せばあらゆるものをゆったりと潤している様子。 千山添翠色せんざんすいしょくにそう 見渡す限りの山々に鮮やかな翠が見える若葉が萌えいずる初夏の風景。 中国唐時代の詩人李賀の「暁は涼しく、暮れは涼しく、 樹は蓋の如し、千山の濃緑雲外に生ず。」による。 【松濤泰宏(松涛泰宏)[まつなみたいこう]】 前大徳寺 鷲峰山、寿福寺第50世住職(福岡県) 1960年昭和35年 生まれ 1972年昭和47年 得度 1982年昭和57年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂初掛塔 1984年昭和59年 福岡大学卒業 1987年昭和62年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂再掛塔 1990年平成02年 臨済宗大徳寺派、三等地寿福寺住職 ----------------------------- 【寿福寺】山号 鷲峰山 福岡県福岡市 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 1190年代に臨済宗の開祖 明庵栄西禅師(建仁寺開祖)によって禅宗に改宗され江戸末期から明治の初期に大徳寺派の末寺になる | 3,550円 |
 〇【茶器/茶道具 短冊 秋】 直筆 萬里無片雲又は紅葉舞秋風又は採菊東籬下又は悠然見南山 西垣大道筆 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 箱たとう紙 作者西垣大道筆 注意メール便不可 (R5/野の大・2910) 【コンビニ受取対応商品】 No24万里・No45紅葉・No採菊・No40悠然萬里無片雲ばんりへんうんなし(万里無片雲) 萬里は、万里の天。片雲は、一片の浮き雲。雲は妄想や煩悩などの例えで、心の隅々まで妄想や煩悩がない状態をいう。 紅葉舞秋風こうようしゅうふうにまう 散りそめた紅葉が秋風に舞っている様子で、晩秋の寒々とした光景のかぎり。まさに、裏をみせ表を見せて散りゆく様子を表す 人はすべて の汚れ、邪念を捨て世に身を任せ「無心」になることから大切です。 採菊東籬下きくをとるとうりのもと 東の垣根のところで菊を取ったり、街中にいたとしても、気持ちはゆったりとしている様。 悠然見南山ゆうぜんとなんざんをみる ゆったりとした気分で南山を見上げる。煩悩妄想の跡形もない、悠悠自適な様子。 【西垣大道】極楽寺 兵庫県城崎 1942年昭和17年 庫県に生まれる。 1949年昭和24年 分山宗興について得度。日本社会福祉大学卒業後、大徳僧堂、のち相国僧堂に掛塔。 1976年昭和51年 仏教大学大学院修士課程修了。 1978年昭和53年 兵庫県城崎郡の大徳寺派極楽禅寺住職に就任し、現在に至る。 | 2,909円 |
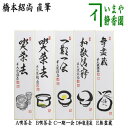 〇【茶器/茶道具 短冊画賛】 直筆 喫茶去 抹茶碗と茶筅の画又は抹茶碗の画又は一期一会 抹茶碗の画又は和敬清寂 抹茶碗の画又は無盡蔵(無尽蔵)砂金袋の画 橋本紹尚筆(柳生紹尚筆) 5種類より選択 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 箱たとう紙 作者橋本紹尚筆(柳生紹尚筆) 注意メール便不可 (R5/ス輪中・4900)〇5445 【コンビニ受取対応商品】喫茶去きっさこ お茶でもおあがりなさいという意味。 お茶と向き合い、茶を飲む、その一事に専念すること。 和敬清寂わけいせいじゃく 茶道の心得を示す言葉 意味は、主人と賓客がお互いの心を和らげて謹み敬い、茶室の備品や茶会の雰囲気を清浄にすることという意である。 茶道における「利休の四規七則」と言われ、 一、茶は服のよきように点て 二、炭は湯の沸くように置き 三、花は野にあるように 四、夏は涼しく冬は暖かに 五、刻限は早めに 六、降らずとも傘の用意 七、相客に心せよ というものです。 弟子が「茶の湯の極意を教えて欲しい」と願ったのに対し、千利休はこの四規七則を答えたとされています。 一期一会いちごいちえ 茶の湯、茶会では毎回一生に一度という思いをこめて真剣に行うことをといた語 一生に一度しかない出会い。一生に一度かぎり。 無盡蔵むじんぞう(無尽蔵) この宇宙に生きるにあたって、全てを投げ捨てて無一物に徹すれば、逆に全てが無尽蔵に湧き出てくるとの意味です。 | 4,900円 |
 〇【茶器/茶道具 短冊】 直筆 青山元不動又は清流無間断 松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) 箱たとう紙 注意メール便不可 (有/野山丸岡、清流・4650) 【コンビニ受取対応商品】青山元不動 白雲自去来せいざんもとふどう はくうんおのずからきょらい 梅雨があけると遠く青山(雄大な山)がくっきりと現れ、いよいよ本格的夏がくる。 泰然として動かざる山と、動いてやまない雲の対比された自然の妙景。 山は堂々と立っていて何事にも動じない、白い雲は自由に行き来する つまり、自在な白い雲が山の周りを行き来しようが、山は動じずに堂々としてる。 周囲がどのように移ろい変わろうとも、山のように動ずることなく自分の進むべき道を進めば良いのです。 清流無間断せいりゅうかんだんなし 清らかな流れが、絶え間なく続く様。 常に活動する ものは、尊い清流のように、新鮮さを持ち続ける。 不断の努力修行が大切であるの意 【松濤泰宏(松涛泰宏)[まつなみたいこう]】 前大徳寺 鷲峰山、寿福寺第50世住職(福岡県) 1960年昭和35年 生まれ 1972年昭和47年 得度 1982年昭和57年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂初掛塔 1984年昭和59年 福岡大学卒業 1987年昭和62年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂再掛塔 1990年平成02年 臨済宗大徳寺派、三等地寿福寺住職 ----------------------------- 【寿福寺】山号 鷲峰山 福岡県福岡市 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 1190年代に臨済宗の開祖 明庵栄西禅師(建仁寺開祖)によって禅宗に改宗され江戸末期から明治の初期に大徳寺派の末寺になる | 3,550円 |
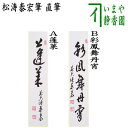 〇【茶器/茶道具 短冊】 直筆 蓬莱又は彩鳳舞丹宵 松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) 箱たとう紙 注意メール便不可 (R3/野山丸岡・4650) 【コンビニ受取対応商品】蓬莱五彩雲ほうらいごさいのくも 不老長寿の仙人が住むという伝説の蓬莱山には美しい5色(青・黄・赤・白・黒)の雲がたなびいている、という意味になります。 たいへんおめでたく、縁起のよい言葉です。 彩鳳舞丹宵さいほうたんしょうにまう 丹宵とは朝焼けや夕焼けのなどの澄み切った赤い空の事で、めでたい風光を言う。 【松濤泰宏(松涛泰宏)[まつなみたいこう]】 前大徳寺 鷲峰山、寿福寺第50世住職(福岡県) 1960年昭和35年 生まれ 1972年昭和47年 得度 1982年昭和57年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂初掛塔 1984年昭和59年 福岡大学卒業 1987年昭和62年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂再掛塔 1990年平成02年 臨済宗大徳寺派、三等地寿福寺住職 ----------------------------- 【寿福寺】山号 鷲峰山 福岡県福岡市 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 1190年代に臨済宗の開祖 明庵栄西禅師(建仁寺開祖)によって禅宗に改宗され江戸末期から明治の初期に大徳寺派の末寺になる | 3,905円 |
 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 好日又は日々是好日又は千年翠又は松樹千年翠 松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) 箱たとう紙 注意メール便不可 (R6/野山丸岡・4650) 【コンビニ受取対応商品】好日こうじつ よい日。好ましい日。晴れて気持ちのよい日や平穏な日。 日々是好日にちにちこれこうじつ(日日是好日) 毎日毎日が素晴らしい」という意味である そこから、毎日が良い日となるよう努めるべきだと述べているとする解釈や、さらに進んで、そもそも日々について良し悪しを考え一喜一憂することが誤りであり常に今この時が大切なのだ、あるいは、あるがままを良しとして受け入れるのだ、と述べているなどとする解釈がなされている 松樹千年翠しょうじゅせんねんのみどり(松樹(寿)千年翠(緑)) 変化の激しい世の中で年月や季節に左右されずに常に変わらず美しい緑を保ち続ける松こそ万古不易の真実の象徴である 【松濤泰宏(松涛泰宏)[まつなみたいこう]】 前大徳寺 鷲峰山、寿福寺第50世住職(福岡県) 1960年昭和35年 生まれ 1972年昭和47年 得度 1982年昭和57年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂初掛塔 1984年昭和59年 福岡大学卒業 1987年昭和62年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂再掛塔 1990年平成02年 臨済宗大徳寺派、三等地寿福寺住職 ----------------------------- 【寿福寺】山号 鷲峰山 福岡県福岡市 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 1190年代に臨済宗の開祖 明庵栄西禅師(建仁寺開祖)によって禅宗に改宗され江戸末期から明治の初期に大徳寺派の末寺になる | 3,905円 |
 【茶器/茶道具 短冊画賛 端午の節句】 直筆 洗心 鯉のぼりの画(鯉幟の画) 曽根幸風画 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 箱たとう紙 作者画:曽根幸風画 注意メール便不可 (野申丸R6/N・/1-・・大・4565)〇5025 【コンビニ受取対応商品】洗心せんしん 心の塵を洗いおとすこと。心の煩累を洗い去り浄めること。また、改心すること。 作者:字(西垣大道筆) 画(曽根幸風画) ---------- 【西垣大道】極楽寺 兵庫県城崎 昭和17年 庫県に生まれる。 昭和24年 分山宗興について得度。日本社会福祉大学卒業後、大徳僧堂、のち相国僧堂に掛塔。 昭和51年 仏教大学大学院修士課程修了。 昭和53年 兵庫県城崎郡の大徳寺派極楽禅寺住職に就任し、現在に至る。 ---------- 【曽根幸風画伯】 昭和11年 京都粟田口生れ 昭和31年 京都府立陶工専修校(陶画科)終了 (故陶師高嶋光楽のもとで作陶師事) 昭和32年 故陶師人間国宝富本憲吉先生に陶画師事 昭和48年 京都洛東 東山に開窯(幸風窯) 昭和53年まで京都東山の窯元で作陶に修行 平成01年 京都 伏見に移窯 (茶道の陶画を通じ絵画に励む) ---------- | 3,652円 |
 色紙 利休座像「和敬清寂」西垣大道師(タトウ紙)※絵:印刷 賛:直筆 茶道具商 左座園 | 2,420円 | |
 【茶道具・色紙・短冊 】書・色紙 「弄花香満衣」、大徳寺 三玄院 長谷川寛州 直筆 佐藤大観堂 | ■要予約■在庫のない場合、お申し込後、納品迄、 1〜2週間程度ご猶予をお願いする場合がございます。■作品は、それぞれ逸品物のため、 仕上がりが多少異なる場合があります、予めご了承下さい。 ■色紙 「弄花香満衣」 長谷川寛州 直筆 分類 茶道具 R-O1-SH-HK-----------------------------------【 弄花香満衣 】(花を弄すれば香衣に満つ)「はなをろうずれば かおりころもにみつ」[解説]花を摘んでいると、自分の衣もその香りに包まれこころまで花と一体となって、清々しい境涯に至る。-----------------------------------------------【 参考 】掬水月在手(水を掬すれば 月 手に在り) 弄花香満衣(花を弄すれば 香 衣に満つ) 水を両手ですくうと手の中の水に月が宿り、花を手折れば香りが衣に移る。 [解説]月と自分、花と自分は、それぞれ別々のものでありながら、一体となる無我の境地。中唐の詩人、干良史(うりょうし)の「春山夜月」という詩の中の二句、後に、虚堂智愚禅師(きどうちぐぜんじ)らが禅的な解釈をする。 筆者 長谷川寛州 老師。 筆者略歴 臨済宗 大徳寺 紫野 三玄院 元住職。 寸法 縦 27.2cm、 横 24.2cm。 備考 畳紙(たとうし)付。新品。 茶道具 美術工芸品 陶磁器 漆器 和の器 茶会用品 抹茶--大観堂 ■トップページに戻り、他の作品を見る | 16,780円 |
 茶道具・書・短冊 「葉々起清風」大徳寺 三玄院 長谷川寛州 直筆 佐藤大観堂 | ■在庫のない場合、お申し込後、納品迄、 1〜2週間程度ご猶予をお願いする場合がございます。■作品は、それぞれ直筆逸品物のため、 仕上がりが多少異なる場合があります、予めご了承下さい。 ■短冊 「葉々起清風」 長谷川寛州 直筆 分類 茶道具 R-W9-T-YYS-HK----------------------------------------【 葉々起清風 (ようよう せいふうを おこす)】「相い送って門に当たれば脩竹あり君が為に葉々清風を起こす」別れ難く門のところまで見送りに出てきたら、脩竹の一葉一葉までもがさらさらと音をなして、別れを惜しむかのようにさわめき、清風を送ってくれている。 見送るもの、見送られる者の別離を惜しむ心情がひしひしと感じ取れる。それと同時に、お互いの清らかな 心の交流は脩竹の起こす清風にも感じる。 筆者 長谷川寛州 老師。 筆者略歴 臨済宗 大徳寺 紫野 三玄院 元住職。 寸法 縦 36.2cm、 横 7.7cm。 備考 畳紙(たとうし)付。新品。 取扱品: 茶道具 茶碗 棗 美術工芸品 陶磁器 和の器 酒盃 抹茶 他創業1946年 茶道具販売の老舗 卸売・小売部門 知事賞 受賞:佐藤大観堂 ■トップページに戻り、他の作品を見る | 13,260円 |
 茶道具 書 短冊 画賛「東籬佳秋色」 菊の絵有馬頼底 賛 直筆 佐藤大観堂 | ■在庫のない場合、新作仕入れの為、お申し込後、納品迄、 2〜3週間程お待ち頂く場合があります。■作品は、それぞれ直筆 逸品物のため、 仕上がりが多少異なる場合があります、予めご了承下さい。 ■短冊 画賛 「東籬佳秋色」 菊の絵 有馬頼底 賛直筆 分類 茶道具 tan-ga-touri-kiku-raitei-r-m8-----------------------------------------------【 東籬佳秋色 】「とうり しゅうしょく かなり」---------------------------------------陶 淵明(とう えんめい)の詩から情景と心境をとらえて五字に圧縮したもの。---------------------------------------採菊東籬下 菊を採る 東籬の下悠然見南山 悠然として南山を見る 山氣日夕佳 山気 日夕に佳し 飛鳥相與還 飛鳥 相ひ与に還る ---------------------------------------【 解釈 】東の垣根の下で菊を摘むと 遠く遥かに廬山が目に入る 山の光景は夕方が特に素晴らしい 鳥たちが連れ立って山の巣に帰っていく 筆者 有馬頼底 老大師 筆者略歴 ■号 大龍窟臨済宗 相國寺派 七代管長、金閣寺(鹿苑寺)住職、銀閣寺(慈照寺)住職、京都仏教会 理事長、日本文化芸術財団 理事。■有馬頼底 老大師久留米藩主 有馬家(赤松氏流)の子孫。東京にて華族の家系に生まれ、天皇陛下のご学友となる。8歳で大分県 日田市の岳林寺にて得度。22歳で京都 相國寺に入門し、相國寺にて禅僧として修行を重ねる。古代から近代に至るまでの墨蹟・茶道具・美術工芸品などに造詣が深く、禅宗歴史美術を通じ、広く一般に布教活動を行っている。 寸法 縦 36.2cm、 横 6.2cm。 備考 畳紙(たとうし)、 略歴付。新品。 取扱品:茶道具 茶碗 美術工芸品 陶磁器 和の器 酒盃 抹茶 他創業1946年 / 茶道具販売 卸売・小売部門 知事賞 受賞:佐藤大観堂 ■トップページに戻り、他の作品を見る | 16,800円 |
 茶道具・書・短冊 「竹有上下節」大徳寺 三玄院 長谷川寛州 直筆 佐藤大観堂 | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■作品は、それぞれ直筆逸品物のため、 写真と多少異なる場合があります。 あらかじめご了承下さいませ。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■短冊 「竹有上下節」 長谷川寛州 直筆 分類 茶道具 R-W9-T-TJF-HK-----------------------------------【 竹有上下節 (たけに じょうげの ふしあり)】『禅林句集』五言対句に「松無古今色、竹有上下節」(松に古今の色なく、竹に上下の節あり)とある。「松無古今色」の対句で、松は季節によって緑の色を変えたりせず、いつも平等である。竹には上下に節が有って区別されているように、人間関係にも平等でありながら、上下の区別はある。ゆえに、本来の姿をそのまま認めてこそ円満だということ。 筆者 長谷川寛州 老師。 筆者略歴 臨済宗 大徳寺 紫野 三玄院 元住職。 寸法 縦 36.2cm、 横 7.7cm。 備考 畳紙(たとうし)付。新品。 取扱品:茶道具 茶碗 美術工芸品 陶磁器 和の器 酒盃 抹茶 他 創業1946年 / 茶道具販売 卸売・小売部門 知事賞 受賞:佐藤大観堂 ■トップページに戻り、他の作品を見る | 13,260円 |