茶道具 短冊 直筆
楽天市場検索
レディースファッション (1) (茶道具 短冊 直筆)
メンズファッション (0)
インナー・下着・ナイトウェア (0)
バッグ・小物・ブランド雑貨 (0)
靴 (0)
腕時計 (0)
ジュエリー・アクセサリー (0)
キッズ・ベビー・マタニティ (0)
おもちゃ (0)
スポーツ・アウトドア (0)
家電 (0)
TV・オーディオ・カメラ (0)
パソコン・周辺機器 (0)
スマートフォン・タブレット (0)
光回線・モバイル通信 (0)
食品 (0)
スイーツ・お菓子 (0)
水・ソフトドリンク (0)
ビール・洋酒 (0)
日本酒・焼酎 (0)
インテリア・寝具・収納 (0)
日用品雑貨・文房具・手芸 (0)
キッチン用品・食器・調理器具 (0)
本・雑誌・コミック (0)
CD・DVD (0)
テレビゲーム (0)
ホビー (457) (茶道具 短冊 直筆)
楽器・音響機器 (0)
車・バイク (0)
車用品・バイク用品 (0)
美容・コスメ・香水 (0)
ダイエット・健康 (0)
医薬品・コンタクト・介護 (0)
ペット・ペットグッズ (0)
花・ガーデン・DIY (0)
サービス・リフォーム (0)
住宅・不動産 (0)
カタログギフト・チケット (0)
百貨店・総合通販・ギフト (0)
レディースファッション (1) (茶道具 短冊 直筆)
メンズファッション (0)
インナー・下着・ナイトウェア (0)
バッグ・小物・ブランド雑貨 (0)
靴 (0)
腕時計 (0)
ジュエリー・アクセサリー (0)
キッズ・ベビー・マタニティ (0)
おもちゃ (0)
スポーツ・アウトドア (0)
家電 (0)
TV・オーディオ・カメラ (0)
パソコン・周辺機器 (0)
スマートフォン・タブレット (0)
光回線・モバイル通信 (0)
食品 (0)
スイーツ・お菓子 (0)
水・ソフトドリンク (0)
ビール・洋酒 (0)
日本酒・焼酎 (0)
インテリア・寝具・収納 (0)
日用品雑貨・文房具・手芸 (0)
キッチン用品・食器・調理器具 (0)
本・雑誌・コミック (0)
CD・DVD (0)
テレビゲーム (0)
ホビー (457) (茶道具 短冊 直筆)
楽器・音響機器 (0)
車・バイク (0)
車用品・バイク用品 (0)
美容・コスメ・香水 (0)
ダイエット・健康 (0)
医薬品・コンタクト・介護 (0)
ペット・ペットグッズ (0)
花・ガーデン・DIY (0)
サービス・リフォーム (0)
住宅・不動産 (0)
カタログギフト・チケット (0)
百貨店・総合通販・ギフト (0)
458件中 121件 - 150件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| 商品 | 説明 | 価格 |
|---|---|---|
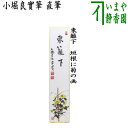 〇【茶器/茶道具 短冊画賛 重陽の節句】 直筆 東籬下 垣根に菊の画 小堀良實筆 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 画賛直筆:短冊 サイズ広巾:約縦36.3×横巾7.5cm 作者小堀良實筆 箱たとう紙 注意メール便不可 (輪野中・5250)〇5250「 【コンビニ受取対応商品】採菊東籬下きくをとるとうりのもと 東の垣根のところで菊を取ったり、街中にいたとしても、気持ちはゆったりとしている様。 【小堀良實(りょうじつ)】寶林寺 山号を曹渓山 大徳寺派 (臨済宗) 1972年昭和47年 京都市:大徳寺:弧蓬庵の次男に生 1996年平成08年 花園大学卒業 博多 崇福寺専門道場にて修行 2004年平成16年 寶林寺住職 ------------------------------ 【寶林寺】 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 寶林寺 山号を曹渓山は 禅宗の祖と言われる達磨大師より、6代目慧能禅師が、この地に来りて、仏法を解きて以来、禅の宗風喩々隆盛となる。開山、春嶺紹温禅師(大灯国師より204世)は寛文年間亀岡の地に来りて創建し、曹渓山寶林寺と名付けられた。 山内には、重要文化財(旧国宝)の薬師・阿弥陀・釈迦の三如来の仏像と九重石塔婆等があります。 | 4,180円 |
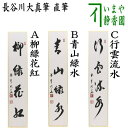 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 柳緑花紅又は青山緑水又は行雲流水 長谷川大真筆 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者長谷川大真筆 箱たとう紙 注意メール便不可 (R4/棒丸岡・15890) 一行軸102000 【コンビニ受取対応商品】柳緑花紅やまぎはみどりはなくれない 柳は緑の枝を垂れ花はあかく咲きほこっている。はじめは諸現象の違いしか見えない。 修行が完成すると後にありのままの姿が見えるが、最初とは違う全く違った世界が見える。 青山緑水せいざんりょくすい 新緑の季節万物の調和のとれた様 山は青く、水はみどりありのまま、「悟て見れば青山緑水で元の儘、明月清風も昔の通りじや」普燈録:一条の緑水青山を巡る、とある。 行雲流水こううんりゅうすい 空行く雲や流れる水のように、深く物事に執着しないで自然の成り行きに任せて行動するたとえ。また、一定の形をもたず、自然に移り変わってよどみがないことのたとえ。 「行雲」は空行く雲。「流水」は流れる水。諸国を修行してまわる禅僧のたとえにも用いられることがある。 【長谷川大真】三玄院 臨済宗 大徳寺塔頭 1957年昭和32年2月 出生 1979年昭和54年 駒沢大学卒業 大本山相国寺 (梶谷宗忍管長)僧堂にて修行 1997年平成09年08月 三玄院住職 ------------------------------ 【三玄院】大徳寺 一五七九年に、春屋和尚を開祖に、石田三成・浅野幸長・森忠政の三人が建てた寺で、沢庵和尚・千宗旦の修道場として著名です。 春屋和尚の弟子には、徳川幕府の悪令に対抗して大徳寺の面目を天下に示した玉室・江月宗玩和尚がおられます。近衛信尹・久我敦通・古田織部・藪内剣仲・小堀遠州・黒田長政・桑山重晴・瀬田掃部・山岡宗無等が参禅した事もつとに知られます。また、石田三成・古田織部の墓があり、茶室は古田織部の設計による篁庵があります。 | 12,705円 |
 【茶器/茶道具 短冊画賛 端午の節句】 直筆 五月晴 鯉のぼりの画又は薫風 菖蒲の画又は菖蒲 鍾馗の画(しょうき) 小堀良實筆 円香画 3種類より選択 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 作者小堀良實筆 画:円香画 箱たとう紙 注意メール便不可 (輪野R7/中・5250) 【コンビニ受取対応商品】五月晴さつきばれ(ごがつばれ) 梅雨の間のさわやかな晴れ間。 陰暦5月の、梅雨の合間の晴天のこと。 薫風くんぷう 初夏、新緑の間を吹いてくる快い風。 【小堀良實(りょうじつ)】寶林寺 山号を曹渓山 大徳寺派 (臨済宗) 1972年昭和47年 京都市:大徳寺:弧蓬庵の次男に生 1996年平成08年 花園大学卒業 博多 崇福寺専門道場にて修行 2004年平成16年 寶林寺住職 ------------------------------ 【寶林寺】 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 寶林寺 山号を曹渓山は 禅宗の祖と言われる達磨大師より、6代目慧能禅師が、この地に来りて、仏法を解きて以来、禅の宗風喩々隆盛となる。開山、春嶺紹温禅師(大灯国師より204世)は寛文年間亀岡の地に来りて創建し、曹渓山寶林寺と名付けられた。 山内には、重要文化財(旧国宝)の薬師・阿弥陀・釈迦の三如来の仏像と九重石塔婆等があります。 | 4,180円 |
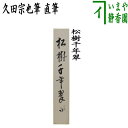 〇【中古】【茶器/茶道具 短冊】 直筆 松樹千年翠 久田宗也筆(尋牛斎) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 箱たとう紙 作者久田宗也筆(尋牛斎) 注意メール便不可 (野吉り・岡・44000)〇39800 【コンビニ受取対応商品】松樹千年翠しょうじゅせんねんのみどり(松樹(寿)千年翠(緑)) 変化の激しい世の中で年月や季節に左右されずに常に変わらず美しい緑を保ち続ける松こそ万古不易の真実の象徴である 【久田家】 久田家は3代宗旦の娘の嫁ぎ先で利休の血筋であり、家元が途絶えそうになった場合、久田家から養子で入っています。 久田家の庵号は半床庵(は んしょうあん)といい、3代宗全による二畳中板の茶室を指す。 【久田家歴代系図】 【初代 宗栄 生々斎】 1559年~1624年3月6日 俗名は久田新八房政 (利休の甥か?) 【2代 宗利 受得斎】 1610年~1685年11月7日 本間利兵衛 (千宗旦の娘クレの夫、藤村庸軒の兄) 【藤村庸軒】(宗旦の四天王の一人) 千家とつながりの深かった久田家初代の久田宗栄の次男で、呉服商十二屋の藤村家に養子に入ったとされる。 薮内紹智に茶の湯を学び、小堀政一(遠州)、金森重近(宗和)からも教えを受ける。のちに千宗旦のもとで台子伝授を許され宗旦四天王の一人に数えられた。 没後、荻野道興の編集により『庸軒詩集』が1803年(享和3年)に刊行された。 【3代 宗全 徳誉斎】 1647年~1707年5月6日 元は本間勘兵衛と称した (宗全は手工に秀で、炭斗の宗全籠等、茶碗・茶杓に優品物が多数あります。) 【4代 宗也 不及斎】 1681年~1744年1月13日 宗全の甥 <4代不及斎には二男あり、理由は不明ながら次男の宗悦が半床庵を継嗣した。> 【高倉久田家歴代】 【5代 宗悦 凉滴斎】 1715年~1768年4月26日 不及斎の次男 【6代 磻翁宗渓 挹泉斎】 1742年~1785年7月24日 【7代 維妙宗也 皓々斎】 1767年~1819年11月29日 【8代 宗利】 不詳-1844年6月30日 養子、元は関宗厳と称した 【9代 一乗宗与】 不詳-1862年8月24日 住山楊甫の孫 『住山家』とは、 住山 楊甫(すみやま ようほ)は、初代(?~?) 表千家6代目宗左の門人。姉は、7代目宗左の妻 2代(1782~1855)天明2年~安政2年 初代楊甫の養嗣子 表千家9代了々斎の死後、幼い吸江斎の後見人になる 一乗宗与(~1862年8月24日)~文久2年 高倉久田家9代目 (住山家八代云々斎楊甫の孫。幼名は岩之介) 【10代 宗悦 玄乗斎】 1856年~1895年4月24日 (表千家10代吸江斎の子で皓々斎の孫) 【11代 守一宗也 無適斎】 1884年~1946年9月13日 【12代 宗也 尋牛斎】 1925年~2010年10月22日 大正14年(1925)京都生。名は和彦、11世無適斎宗也の長男。 京大史学科卒 【13代 宗也 得流斎】 1958年~2011年10月13日 当代 | 14,850円 |
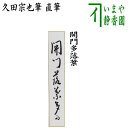 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 開門多落葉 久田宗也筆(尋牛斎宗匠) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ並巾:約縦36.3×横6cm 作者久田宗也筆(尋牛斎) 箱たとう紙 注意メール便不可 (・40150) 【コンビニ受取対応商品】開門多落葉もんをひらけばらくようおおし(開門落葉多) 『禅林句集』五言対句に「聽雨寒更盡、開門落葉多」(雨を聴いて寒更尽き、門を開けば落葉多し) 雨音を聴いているうちに寒い夜更けが過ぎ、夜が明けたので門を開けてみると、あたり一面に葉が落ちていた。 一晩中聴いていた雨音は、朝になってみれば、実は軒端をたたく落ち葉の音だったという幽寂な閑居の風情、つまり、雨音とばかり思っていた音が、実は落葉の音と知った瞬間、悟りを開いた瞬間を表しています。【禅語大辞典より】 【久田家】 久田家は3代宗旦の娘の嫁ぎ先で利休の血筋であり、家元が途絶えそうになった場合、久田家から養子で入っています。 久田家の庵号は半床庵(は んしょうあん)といい、3代宗全による二畳中板の茶室を指す。 【久田家歴代系図】 【初代 宗栄 生々斎】 1559年〜1624年3月6日 俗名は久田新八房政 (利休の甥か?) 【2代 宗利 受得斎】 1610年〜1685年11月7日 本間利兵衛 (千宗旦の娘クレの夫、藤村庸軒の兄) 【藤村庸軒】(宗旦の四天王の一人) 千家とつながりの深かった久田家初代の久田宗栄の次男で、呉服商十二屋の藤村家に養子に入ったとされる。 薮内紹智に茶の湯を学び、小堀政一(遠州)、金森重近(宗和)からも教えを受ける。のちに千宗旦のもとで台子伝授を許され宗旦四天王の一人に数えられた。 没後、荻野道興の編集により『庸軒詩集』が1803年(享和3年)に刊行された。 【3代 宗全 徳誉斎】 1647年〜1707年5月6日 元は本間勘兵衛と称した (宗全は手工に秀で、炭斗の宗全籠等、茶碗・茶杓に優品物が多数あります。) 【4代 宗也 不及斎】 1681年〜1744年1月13日 宗全の甥 <4代不及斎には二男あり、理由は不明ながら次男の宗悦が半床庵を継嗣した。> 【高倉久田家歴代】 【5代 宗悦 凉滴斎】 1715年〜1768年4月26日 不及斎の次男 【6代 磻翁宗渓 挹泉斎】 1742年〜1785年7月24日 【7代 維妙宗也 皓々斎】 1767年〜1819年11月29日 【8代 宗利】 不詳-1844年6月30日 養子、元は関宗厳と称した 【9代 一乗宗与】 不詳-1862年8月24日 住山楊甫の孫 『住山家』とは、 住山 楊甫(すみやま ようほ)は、初代(?〜?) 表千家6代目宗左の門人。姉は、7代目宗左の妻 2代(1782〜1855)天明2年〜安政2年 初代楊甫の養嗣子 表千家9代了々斎の死後、幼い吸江斎の後見人になる 一乗宗与(〜1862年8月24日)〜文久2年 高倉久田家9代目 (住山家八代云々斎楊甫の孫。幼名は岩之介) 【10代 宗悦 玄乗斎】 1856年〜1895年4月24日 (表千家10代吸江斎の子で皓々斎の孫) 【11代 守一宗也 無適斎】 1884年〜1946年9月13日 【12代 宗也 尋牛斎】 1925年〜2010年10月22日 大正14年(1925)京都生。名は和彦、11世無適斎宗也の長男。 京大史学科卒 【13代 宗也 得流斎】 1958年〜2011年10月13日 当代 | 29,700円 |
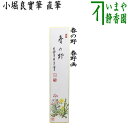 〇【茶器/茶道具 短冊画賛】 直筆 春の野 小堀良實筆 春野画 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横巾7.5cm 作者小堀良實筆 箱たとう紙 注意メール便不可 (輪野中・5250)〇5250「 【コンビニ受取対応商品】春の野はるのの 春、雪が消え、草木が芽吹き、日に日に緑に染まってゆく野をいう。 【小堀良實(りょうじつ)】寶林寺 山号を曹渓山 大徳寺派 (臨済宗) 1972年昭和47年 京都市:大徳寺:弧蓬庵の次男に生 1996年平成08年 花園大学卒業 博多 崇福寺専門道場にて修行 2004年平成16年 寶林寺住職 ------------------------------ 【寶林寺】 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 寶林寺 山号を曹渓山は 禅宗の祖と言われる達磨大師より、6代目慧能禅師が、この地に来りて、仏法を解きて以来、禅の宗風喩々隆盛となる。開山、春嶺紹温禅師(大灯国師より204世)は寛文年間亀岡の地に来りて創建し、曹渓山寶林寺と名付けられた。 山内には、重要文化財(旧国宝)の薬師・阿弥陀・釈迦の三如来の仏像と九重石塔婆等があります。 | 4,180円 |
 〇【茶器/茶道具 短冊画賛 重陽の節句】 直筆 満山川 小堀良實筆 紅葉の画(画は上に、下にお任せ) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 紅葉の画は上の位置、下の位置はお任せ 画賛直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横巾7.5cm 作者小堀良實筆 箱たとう紙 注意メール便不可 (野目中・525)「 【コンビニ受取対応商品】紅葉満山川こうようさんせんにみつ 紅葉の画は上の位置、下の位置はお任せ紅葉が山にも川にも満ち満ちている情景。 目の前の錦秋の風景は、そのままが悟境であり、妙景であり、仏性そのものと言える。 【小堀良實(りょうじつ)】寶林寺 山号を曹渓山 大徳寺派 (臨済宗) 1972年昭和47年 京都市:大徳寺:弧蓬庵の次男に生 1996年平成08年 花園大学卒業 博多 崇福寺専門道場にて修行 2004年平成16年 寶林寺住職 ------------------------------ 【寶林寺】 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 寶林寺 山号を曹渓山は 禅宗の祖と言われる達磨大師より、6代目慧能禅師が、この地に来りて、仏法を解きて以来、禅の宗風喩々隆盛となる。開山、春嶺紹温禅師(大灯国師より204世)は寛文年間亀岡の地に来りて創建し、曹渓山寶林寺と名付けられた。 山内には、重要文化財(旧国宝)の薬師・阿弥陀・釈迦の三如来の仏像と九重石塔婆等があります。 | 4,180円 |
 〇【茶器/茶道具 短冊画賛】 直筆 無事千秋楽 箒の画又は山寒花発遅 寒牡丹の画 福本積應筆 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 箱たとう紙 作者福本積應筆 注意メール便不可 (り・5400) 【コンビニ受取対応商品】無事千秋楽ぶじせんしゅうらく 今年も何事もなく年末を迎えられ、感謝の気持ち 普段と同じ・平常な日々 無事とは、仏や悟り、道の完成を他に求めない心をいいます。悟っているあなたは、何もする事はないですよ。との事。 山寒花発遅やまさむうしてはなのひらくことおそし 山里の冬は長く、春は遅々として訪れない。つまり、花の発くことは、厳しい修行の果てにたどり着く悟りを、意味する。 【福本積應】 1930年昭和05年 京都に生まれる 1959年昭和34年 大徳寺派招春寺(京都府船井郡)住職を拝命 1983年昭和58年 大徳寺派宝林寺(亀岡市)兼務住職を拝命 1989年平成01年 宝林寺本堂・庫裏・山門を建立 2002年平成14年 招春寺本堂・山門を建立 2004年平成16年 宝林寺を後任住職に譲 再度招春寺住職を拝命 | 5,005円 |
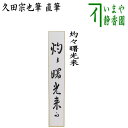 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 灼々曙光来 久田宗也筆(尋牛斎) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ並巾:約縦36.3×横6cm 作者久田宗也筆(尋牛斎) 箱たとう紙 (・40150) 【コンビニ受取対応商品】灼々曙光来しゃくしゃくしょこうきたる 灼々…光り輝くさまのこと。 曙光…夜明けに、東の空にさしてくる太陽の光。 物事の前途に見えはじめた明るいきざし。 【久田家】 久田家は3代宗旦の娘の嫁ぎ先で利休の血筋であり、家元が途絶えそうになった場合、久田家から養子で入っています。 久田家の庵号は半床庵(は んしょうあん)といい、3代宗全による二畳中板の茶室を指す。 【久田家歴代系図】 【初代 宗栄 生々斎】 1559年〜1624年3月6日 俗名は久田新八房政 (利休の甥か?) 【2代 宗利 受得斎】 1610年〜1685年11月7日 本間利兵衛 (千宗旦の娘クレの夫、藤村庸軒の兄) 【藤村庸軒】(宗旦の四天王の一人) 千家とつながりの深かった久田家初代の久田宗栄の次男で、呉服商十二屋の藤村家に養子に入ったとされる。 薮内紹智に茶の湯を学び、小堀政一(遠州)、金森重近(宗和)からも教えを受ける。のちに千宗旦のもとで台子伝授を許され宗旦四天王の一人に数えられた。 没後、荻野道興の編集により『庸軒詩集』が1803年(享和3年)に刊行された。 【3代 宗全 徳誉斎】 1647年〜1707年5月6日 元は本間勘兵衛と称した (宗全は手工に秀で、炭斗の宗全籠等、茶碗・茶杓に優品物が多数あります。) 【4代 宗也 不及斎】 1681年〜1744年1月13日 宗全の甥 <4代不及斎には二男あり、理由は不明ながら次男の宗悦が半床庵を継嗣した。> 【高倉久田家歴代】 【5代 宗悦 凉滴斎】 1715年〜1768年4月26日 不及斎の次男 【6代 磻翁宗渓 挹泉斎】 1742年〜1785年7月24日 【7代 維妙宗也 皓々斎】 1767年〜1819年11月29日 【8代 宗利】 不詳-1844年6月30日 養子、元は関宗厳と称した 【9代 一乗宗与】 不詳-1862年8月24日 住山楊甫の孫 『住山家』とは、 住山 楊甫(すみやま ようほ)は、初代(?〜?) 表千家6代目宗左の門人。姉は、7代目宗左の妻 2代(1782〜1855)天明2年〜安政2年 初代楊甫の養嗣子 表千家9代了々斎の死後、幼い吸江斎の後見人になる 一乗宗与(〜1862年8月24日)〜文久2年 高倉久田家9代目 (住山家八代云々斎楊甫の孫。幼名は岩之介) 【10代 宗悦 玄乗斎】 1856年〜1895年4月24日 (表千家10代吸江斎の子で皓々斎の孫) 【11代 守一宗也 無適斎】 1884年〜1946年9月13日 【12代 宗也 尋牛斎】 1925年〜2010年10月22日 大正14年(1925)京都生。名は和彦、11世無適斎宗也の長男。 京大史学科卒 【13代 宗也 得流斎】 1958年〜2011年10月13日 当代 | 30,800円 |
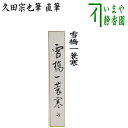 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 雪橋一蓑寒 久田宗也筆(尋牛斎) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ並巾:約縦36.3×横6cm 箱たとう紙 作者久田宗也筆(尋牛斎) 注意メール便不可 (・37880) 【コンビニ受取対応商品】雪橋一蓑寒ゆきはしいちみのさむし 雪降り積もる雪の橋をわたって行く情景を思い浮かべました語句。 冬の寒さが増してくる様子。 【久田家】 久田家は3代宗旦の娘の嫁ぎ先で利休の血筋であり、家元が途絶えそうになった場合、久田家から養子で入っています。 久田家の庵号は半床庵(は んしょうあん)といい、3代宗全による二畳中板の茶室を指す。 【久田家歴代系図】 【初代 宗栄 生々斎】 1559年〜1624年3月6日 俗名は久田新八房政 (利休の甥か?) 【2代 宗利 受得斎】 1610年〜1685年11月7日 本間利兵衛 (千宗旦の娘クレの夫、藤村庸軒の兄) 【藤村庸軒】(宗旦の四天王の一人) 千家とつながりの深かった久田家初代の久田宗栄の次男で、呉服商十二屋の藤村家に養子に入ったとされる。 薮内紹智に茶の湯を学び、小堀政一(遠州)、金森重近(宗和)からも教えを受ける。のちに千宗旦のもとで台子伝授を許され宗旦四天王の一人に数えられた。 没後、荻野道興の編集により『庸軒詩集』が1803年(享和3年)に刊行された。 【3代 宗全 徳誉斎】 1647年〜1707年5月6日 元は本間勘兵衛と称した (宗全は手工に秀で、炭斗の宗全籠等、茶碗・茶杓に優品物が多数あります。) 【4代 宗也 不及斎】 1681年〜1744年1月13日 宗全の甥 <4代不及斎には二男あり、理由は不明ながら次男の宗悦が半床庵を継嗣した。> 【高倉久田家歴代】 【5代 宗悦 凉滴斎】 1715年〜1768年4月26日 不及斎の次男 【6代 磻翁宗渓 挹泉斎】 1742年〜1785年7月24日 【7代 維妙宗也 皓々斎】 1767年〜1819年11月29日 【8代 宗利】 不詳-1844年6月30日 養子、元は関宗厳と称した 【9代 一乗宗与】 不詳-1862年8月24日 住山楊甫の孫 『住山家』とは、 〇住山 楊甫(すみやま ようほ)は、初代(?〜?) 表千家6代目宗左の門人。姉は、7代目宗左の妻 〇二代(1782〜1855)天明2年〜安政2年 初代楊甫の養嗣子 表千家9代了々斎の死後、幼い吸江斎の後見人になる 〇一乗宗与(〜1862年8月24日)〜文久2年 高倉久田家9代目 (住山家八代云々斎楊甫の孫。幼名は岩之介) 【10代 宗悦 玄乗斎】 1856年〜1895年4月24日 (表千家10代吸江斎の子で皓々斎の孫) 【11代 守一宗也 無適斎】 1884年〜1946年9月13日 【12代 宗也 尋牛斎】 1925年〜2010年10月22日 大正14年(1925)京都生。名は和彦、11世無適斎宗也の長男。 京大史学科卒 【13代 宗也 得流斎】 1958年〜2011年10月13日 当代 | 30,800円 |
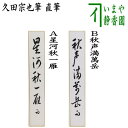 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 星河秋一雁又は秋声満萬岳 久田宗也筆(尋牛斎) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ並巾:約縦36.3×横6cm 作者久田宗也筆(尋牛斎) 箱たとう紙 (・40150) 【コンビニ受取対応商品】星河秋一雁せいがあきいちがんせいがいちがんのあき 天の川が輝く 澄みきった秋の夜空を、一羽の雁が飛んで行く 秋声満萬岳しゅうせいまんがくにみつ もの寂しげな秋の夕暮れの情景。 秋声とは颯々と吹き渡る秋風の音や、木の葉の散る音など秋を感じさせる音、声。 見渡す一面秋の情景が想像できます。 【久田家】 久田家は3代宗旦の娘の嫁ぎ先で利休の血筋であり、家元が途絶えそうになった場合、久田家から養子で入っています。 久田家の庵号は半床庵(は んしょうあん)といい、3代宗全による二畳中板の茶室を指す。 【久田家歴代系図】 【初代 宗栄 生々斎】 1559年〜1624年3月6日 俗名は久田新八房政 (利休の甥か?) 【2代 宗利 受得斎】 1610年〜1685年11月7日 本間利兵衛 (千宗旦の娘クレの夫、藤村庸軒の兄) 【藤村庸軒】(宗旦の四天王の一人) 千家とつながりの深かった久田家初代の久田宗栄の次男で、呉服商十二屋の藤村家に養子に入ったとされる。 薮内紹智に茶の湯を学び、小堀政一(遠州)、金森重近(宗和)からも教えを受ける。のちに千宗旦のもとで台子伝授を許され宗旦四天王の一人に数えられた。 没後、荻野道興の編集により『庸軒詩集』が1803年(享和3年)に刊行された。 【3代 宗全 徳誉斎】 1647年〜1707年5月6日 元は本間勘兵衛と称した (宗全は手工に秀で、炭斗の宗全籠等、茶碗・茶杓に優品物が多数あります。) 【4代 宗也 不及斎】 1681年〜1744年1月13日 宗全の甥 <4代不及斎には二男あり、理由は不明ながら次男の宗悦が半床庵を継嗣した。> 【高倉久田家歴代】 【5代 宗悦 凉滴斎】 1715年〜1768年4月26日 不及斎の次男 【6代 磻翁宗渓 挹泉斎】 1742年〜1785年7月24日 【7代 維妙宗也 皓々斎】 1767年〜1819年11月29日 【8代 宗利】 不詳-1844年6月30日 養子、元は関宗厳と称した 【9代 一乗宗与】 不詳-1862年8月24日 住山楊甫の孫 『住山家』とは、 住山 楊甫(すみやま ようほ)は、初代(?〜?) 表千家6代目宗左の門人。姉は、7代目宗左の妻 2代(1782〜1855)天明2年〜安政2年 初代楊甫の養嗣子 表千家9代了々斎の死後、幼い吸江斎の後見人になる 一乗宗与(〜1862年8月24日)〜文久2年 高倉久田家9代目 (住山家八代云々斎楊甫の孫。幼名は岩之介) 【10代 宗悦 玄乗斎】 1856年〜1895年4月24日 (表千家10代吸江斎の子で皓々斎の孫) 【11代 守一宗也 無適斎】 1884年〜1946年9月13日 【12代 宗也 尋牛斎】 1925年〜2010年10月22日 大正14年(1925)京都生。名は和彦、11世無適斎宗也の長男。 京大史学科卒 【13代 宗也 得流斎】 1958年〜2011年10月13日 当代 | 29,700円 |
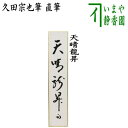 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 天晴龍昇 久田宗也筆(尋牛斎) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ並巾:約縦36.3×横6cm 作者久田宗也筆(尋牛斎) 箱たとう紙 注意メール便不可 (・37880) 【コンビニ受取対応商品】天晴龍昇てんせいりゅうしょう 時に天に上り、雨雲を呼ぶ。 陽のエネルギーを待つ、経済発展の繁栄や幸運を呼ぶ。 天子の権力の象徴 【久田家】 久田家は3代宗旦の娘の嫁ぎ先で利休の血筋であり、家元が途絶えそうになった場合、久田家から養子で入っています。 久田家の庵号は半床庵(は んしょうあん)といい、3代宗全による二畳中板の茶室を指す。 【久田家歴代系図】 【初代 宗栄 生々斎】 1559年〜1624年3月6日 俗名は久田新八房政 (利休の甥か?) 【2代 宗利 受得斎】 1610年〜1685年11月7日 本間利兵衛 (千宗旦の娘クレの夫、藤村庸軒の兄) 【藤村庸軒】(宗旦の四天王の一人) 千家とつながりの深かった久田家初代の久田宗栄の次男で、呉服商十二屋の藤村家に養子に入ったとされる。 薮内紹智に茶の湯を学び、小堀政一(遠州)、金森重近(宗和)からも教えを受ける。のちに千宗旦のもとで台子伝授を許され宗旦四天王の一人に数えられた。 没後、荻野道興の編集により『庸軒詩集』が1803年(享和3年)に刊行された。 【3代 宗全 徳誉斎】 1647年〜1707年5月6日 元は本間勘兵衛と称した (宗全は手工に秀で、炭斗の宗全籠等、茶碗・茶杓に優品物が多数あります。) 【4代 宗也 不及斎】 1681年〜1744年1月13日 宗全の甥 <4代不及斎には二男あり、理由は不明ながら次男の宗悦が半床庵を継嗣した。> 【高倉久田家歴代】 【5代 宗悦 凉滴斎】 1715年〜1768年4月26日 不及斎の次男 【6代 磻翁宗渓 挹泉斎】 1742年〜1785年7月24日 【7代 維妙宗也 皓々斎】 1767年〜1819年11月29日 【8代 宗利】 不詳-1844年6月30日 養子、元は関宗厳と称した 【9代 一乗宗与】 不詳-1862年8月24日 住山楊甫の孫 『住山家』とは、 〇住山 楊甫(すみやま ようほ)は、初代(?〜?) 表千家6代目宗左の門人。姉は、7代目宗左の妻 〇二代(1782〜1855)天明2年〜安政2年 初代楊甫の養嗣子 表千家9代了々斎の死後、幼い吸江斎の後見人になる 〇一乗宗与(〜1862年8月24日)〜文久2年 高倉久田家9代目 (住山家八代云々斎楊甫の孫。幼名は岩之介) 【10代 宗悦 玄乗斎】 1856年〜1895年4月24日 (表千家10代吸江斎の子で皓々斎の孫) 【11代 守一宗也 無適斎】 1884年〜1946年9月13日 【12代 宗也 尋牛斎】 1925年〜2010年10月22日 大正14年(1925)京都生。名は和彦、11世無適斎宗也の長男。 京大史学科卒 【13代 宗也 得流斎】 1958年〜2011年10月13日 当代 | 30,800円 |
 ◎【茶器/茶道具 短冊】 直筆 月白風清又は千里同風又は清風拂明月又は秋山風月清 松涛泰宏筆 4種類より選択 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者松涛泰宏筆 箱たとう紙 注意メール便不可 (野山丸岡・3980) 【コンビニ受取対応商品】月白風清つきしろくかぜきよし 中秋の名月の一句 中国宋代第一の詩人とうたわれた文豪・蘇軾[そしょく](蘇東坡[そとうば])の代表作「後赤壁[ごせきへき]の賦[ふ]」の中の句です。 澄みきった天空に一輪の月がこうこうと輝き、すすきの穂の間から爽やかな風がゆるやかに吹きわたる爽やかな空間 千里同風せんりどうふう 千里の彼方、すなわちはるか遠方まで同じ風が吹いている。 皆同じく平等の風の恩恵に浴し、万民和楽で世界の太平なること。 皆は同様な立つ位地にある。 清風拂明月せいふうめいげつをはらう(清風払明月) 清らかな風が明月を払い清め、清らかな風もまた明月の白き光に払い清められる。 澄みきった秋の夜空に明月が掛かり、清らかな風が颯颯と吹きすぎる情景を詠じた、秋の季節にふさわしい名句。 『禅語字彙』に「本體が作用となり、作用が本體となりて、一方に固定せざるをいふ」とある。 秋山風月清しゅうざんふうげつのきよき 秋の山は風も月も清らかに澄み渡っている。 どこまもでも透明な独脱の世界。 【松濤泰宏(松涛泰宏)[まつなみたいこう]】 前大徳寺 鷲峰山、寿福寺第50世住職(福岡県) 1960年昭和35年 生まれ 1972年昭和47年 得度 1982年昭和57年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂初掛塔 1984年昭和59年 福岡大学卒業 1987年昭和62年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂再掛塔 1990年平成02年 臨済宗大徳寺派、三等地寿福寺住職 ----------------------------- 【寿福寺】山号 鷲峰山 福岡県福岡市 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 1190年代に臨済宗の開祖 明庵栄西禅師(建仁寺開祖)によって禅宗に改宗され江戸末期から明治の初期に大徳寺派の末寺になる | 3,718円 |
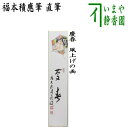 【茶器 茶道具 短冊画賛 新春】 直筆 慶春 福本積應筆 凧上げの画 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 箱たとう紙 作者福本積應筆 注意メール便不可 (H29・9-11り・4400)〇5940 【コンビニ受取対応商品】慶春けいしゅん 新春をよろこぶこと。年賀状などの挨拶にも使われる。 【福本積應】 1930年昭和05年 京都に生まれる 1959年昭和34年 大徳寺派招春寺(京都府船井郡)住職を拝命 1983年昭和58年 大徳寺派宝林寺(亀岡市)兼務住職を拝命 1989年平成01年 宝林寺本堂・庫裏・山門を建立 2002年平成14年 招春寺本堂・山門を建立 2004年平成16年 宝林寺を後任住職に譲 再度招春寺住職を拝命 | 5,005円 |
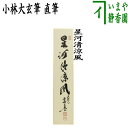 【茶器/茶道具 短冊 七夕】 直筆 星河清涼風 小林大玄筆 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者小林太玄筆(黄梅院:頭塔) 箱たとう紙 (R5/限定目礼大・21185) 【コンビニ受取対応商品】星河清涼風せいがりょうふうきよし/せいかせいりょうのかぜ 「星河」とは、天の川・銀河の意。 星空を眺めていると涼しい風が吹いてきて清々しい気分になった。 【小林太玄】黄梅院 大徳寺塔頭 1938年昭和13年 奉天生まれ 1961年昭和36年 花園大学卒業 相国僧堂に掛塔 大津暦堂に参禅 1975年昭和50年 大徳寺塔頭 20世 黄梅院に就任 昭和50年 大徳寺塔頭 20世 黄梅院に就任 | 16,940円 |
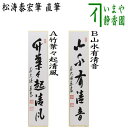 〇【茶器/茶道具 短冊】 直筆 竹葉々起清風又は山水有清音 松濤泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者松濤泰宏(宗潤)筆(まつなみたいこう) 箱たとう紙 注意メール便不可 (野吉丸岡・4650)4440 【コンビニ受取対応商品】竹(為君)葉々起清風たけ(きみがために)、ようようせいふうをおこす(竹葉葉起清風) 竹の葉っぱが重なり合い揺れ、さわやかな風を起こしている 現象としては、風が葉を揺らしているのですが、ここでは、葉が風を起こしている かつての弟子が旅の前に訪ねてきてくれたので門まで見送る。すると(あなたの為に)竹の葉までもが風を起こして新たな旅立ちを送っていた。 山水有清音さんすいにせいおんあり 左思(さし)西晋 の詩人 山や川、自然には、澄んだ清らかな音がある の意。 人為のない、ありのままの世界が奏でる清浄な響き。下手な造作を加えないありのままの世界。 【松濤泰宏(松涛泰宏)(宗潤)[まつなみたいこう]】 前大徳寺 鷲峰山、寿福寺第50世住職(福岡県) 1960年昭和35年 生まれ 1972年昭和47年 得度 1982年昭和57年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂初掛塔 1984年昭和59年 福岡大学卒業 1987年昭和62年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂再掛塔 1990年平成02年 臨済宗大徳寺派、三等地寿福寺住職 ----------------------------- 【寿福寺】山号 鷲峰山 福岡県福岡市 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 1190年代に臨済宗の開祖 明庵栄西禅師(建仁寺開祖)によって禅宗に改宗され江戸末期から明治の初期に大徳寺派の末寺になる | 3,550円 |
 【茶器/茶道具 短冊画賛】 直筆 和敬清寂又は本来無一物 有馬頼底筆 石山懐紙風 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ並巾:約縦36.3×横6cm 箱たとう紙 作者有馬頼底筆 注意メール便不可 (大・21600) 【コンビニ受取対応商品】和敬清寂わけいせいじゃく 茶道の心得を示す言葉 意味は、主人と賓客がお互いの心を和らげて謹み敬い、茶室の備品や茶会の雰囲気を清浄にすることという意である。 茶道における「利休の四規七則」と言われ、 一、茶は服のよきように点て 二、炭は湯の沸くように置き 三、花は野にあるように 四、夏は涼しく冬は暖かに 五、刻限は早めに 六、降らずとも傘の用意 七、相客に心せよ というものです。 弟子が「茶の湯の極意を教えて欲しい」と願ったのに対し、千利休はこの四規七則を答えたとされています。 本来無一物ほんらいむいちぶつ 本来、執すべきものは何もなく空であるという意味。 【有馬頼底(号 大龍窟)】萬年山相国承天禅寺 相國寺派 臨済宗 7代管長 京都仏教会 理事長、日本文化芸術財団 理事 久留米藩主 有馬家(赤松氏流)の子孫 (東京にて華族の家系に生まれ、天皇陛下のご学友となる) 1933年昭和08年 有馬本家当主有馬頼寧の従兄弟にあたる分家有馬正頼男爵の次男として東京で生を受ける 1941年昭和16年 8歳の時、大分県日田市の岳林寺で得度 1955年昭和30年 22歳 京都臨済宗相国寺僧堂に入門。大津櫪堂老師に師事 1968年昭和43年 相国寺塔頭大光明寺住職 1971年昭和46年 相国寺派教学部長 1984年昭和59年 相国寺承天閣美術館設立により事務局長 1988年昭和63年 京都仏教会理事長に就任 1995年平成07年 臨済宗相国寺派七代管長(相国寺132世)に就任 | 17,325円 |
 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 春光生嘉祥又は和気生嘉祥又は和顔生幸慶 久田宗也筆(尋牛斎) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ並巾:約縦36.3×横6cm 作者久田宗也筆(尋牛斎) 箱たとう紙 注意メール便不可 (中・37880) 【コンビニ受取対応商品】春光生嘉祥しゅんこうかしょうをしょうず 冬の眠りに就ついていた万物を覚醒させて生命力を与える、春の陽光のめでたい兆しが生まれる。 和気生嘉祥わきかしょうをしょうず 和(やわ)らいだ気はめでたさを生じる。 和気には大別して天候が順当であることの意と、人の心が和睦であるの意とがある。 天候が和順であることによて、五穀豊穣となり人々の幸福を招くこと。また、人々の心が睦まじく和らいで吉祥を生じるということ。 和顔生幸慶わがんこうけいをしょうず 和やかな顔で接すれば、おのずと祝福する気持ちが生まれる 【久田家】 久田家は3代宗旦の娘の嫁ぎ先で利休の血筋であり、家元が途絶えそうになった場合、久田家から養子で入っています。 久田家の庵号は半床庵(は んしょうあん)といい、3代宗全による二畳中板の茶室を指す。 【久田家歴代系図】 【初代 宗栄 生々斎】 1559年〜1624年3月6日 俗名は久田新八房政 (利休の甥か?) 【2代 宗利 受得斎】 1610年〜1685年11月7日 本間利兵衛 (千宗旦の娘クレの夫、藤村庸軒の兄) 【藤村庸軒】(宗旦の四天王の一人) 千家とつながりの深かった久田家初代の久田宗栄の次男で、呉服商十二屋の藤村家に養子に入ったとされる。 薮内紹智に茶の湯を学び、小堀政一(遠州)、金森重近(宗和)からも教えを受ける。のちに千宗旦のもとで台子伝授を許され宗旦四天王の一人に数えられた。 没後、荻野道興の編集により『庸軒詩集』が1803年(享和3年)に刊行された。 【3代 宗全 徳誉斎】 1647年〜1707年5月6日 元は本間勘兵衛と称した (宗全は手工に秀で、炭斗の宗全籠等、茶碗・茶杓に優品物が多数あります。) 【4代 宗也 不及斎】 1681年〜1744年1月13日 宗全の甥 <4代不及斎には二男あり、理由は不明ながら次男の宗悦が半床庵を継嗣した。> 【高倉久田家歴代】 【5代 宗悦 凉滴斎】 1715年〜1768年4月26日 不及斎の次男 【6代 磻翁宗渓 挹泉斎】 1742年〜1785年7月24日 【7代 維妙宗也 皓々斎】 1767年〜1819年11月29日 【8代 宗利】 不詳-1844年6月30日 養子、元は関宗厳と称した 【9代 一乗宗与】 不詳-1862年8月24日 住山楊甫の孫 『住山家』とは、 〇住山 楊甫(すみやま ようほ)は、初代(?〜?) 表千家6代目宗左の門人。姉は、7代目宗左の妻 〇二代(1782〜1855)天明2年〜安政2年 初代楊甫の養嗣子 表千家9代了々斎の死後、幼い吸江斎の後見人になる 〇一乗宗与(〜1862年8月24日)〜文久2年 高倉久田家9代目 (住山家八代云々斎楊甫の孫。幼名は岩之介) 【10代 宗悦 玄乗斎】 1856年〜1895年4月24日 (表千家10代吸江斎の子で皓々斎の孫) 【11代 守一宗也 無適斎】 1884年〜1946年9月13日 【12代 宗也 尋牛斎】 1925年〜2010年10月22日 大正14年(1925)京都生。名は和彦、11世無適斎宗也の長男。 京大史学科卒 【13代 宗也 得流斎】 1958年〜2011年10月13日 当代 | 29,700円 |
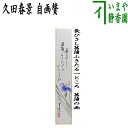 【茶器/茶道具 短冊画賛 端午の節句】 直筆 長ひさし菖蒲ふきたる一ところ 菖蒲の画 久田春景画 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ並幅:約縦36.4×横6.1cm 箱たとう紙 作者画:久田春景画 注意メール便不可 (R5/・・野丸中・4070) 【コンビニ受取対応商品】【久田春景】書道家 1950年昭和25年 兵庫県姫路市生まれ 師 田中玉仙(実姉) 書道師 石山萌斉氏 1995年平成07年 国選特選 瀬戸大橋全国書道展特選2回 | 3,256円 |
 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 紅葉満山川 小堀良實筆 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者小堀良實筆 箱たとう紙 注意メール便不可 (R6/野輪中・3300) 【コンビニ受取対応商品】紅葉満山川こうようさんせんにみつ 紅葉が山にも川にも満ち満ちている情景。 目の前の錦秋の風景は、そのままが悟境であり、妙景であり、仏性そのものと言える。 【小堀良實(りょうじつ)】寶林寺 山号を曹渓山 大徳寺派 (臨済宗) 1972年昭和47年 京都市:大徳寺:弧蓬庵の次男に生 1996年平成08年 花園大学卒業 博多 崇福寺専門道場にて修行 2004年平成16年 寶林寺住職 ------------------------------ 【寶林寺】 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 寶林寺 山号を曹渓山は 禅宗の祖と言われる達磨大師より、6代目慧能禅師が、この地に来りて、仏法を解きて以来、禅の宗風喩々隆盛となる。開山、春嶺紹温禅師(大灯国師より204世)は寛文年間亀岡の地に来りて創建し、曹渓山寶林寺と名付けられた。 山内には、重要文化財(旧国宝)の薬師・阿弥陀・釈迦の三如来の仏像と九重石塔婆等があります。 | 2,618円 |
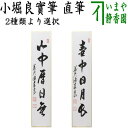 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 山中無暦日又は壺中日月長 松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者松涛泰宏筆(宗潤)(まつなみたいこう) 箱たとう紙 注意メール便不可 (~R7野吉丸・4650) 【コンビニ受取対応商品】山中無暦日さんちゅうれきじつなし 無意味に時を過ごすのでなく、禅では日常無心に生きとしいきるにすぐる。閑人を指すのでなく、時間に謀殺されて、己を見失うことなく、今を自己を見つめるゆとりも必要ですと、説く。(唐詩選) 太上隠者の「人に答うる」と言う題の詩の中の 一節. 偶々 (たまたま) 松樹の下に来たり 枕を高くして石頭に眠る 山中暦日無し 寒尽 くるも年を知らず。 壺中日月長こちゅうにちげつながし壷中日月長 茶道で狭い室内を時空を越えた仙境とし、思う存分異次元を体験する場所に見立てる。 【松濤泰宏(松涛泰宏)[まつなみたいこう]】 前大徳寺 鷲峰山、寿福寺第50世住職(福岡県) 1960年昭和35年 生まれ 1972年昭和47年 得度 1982年昭和57年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂初掛塔 1984年昭和59年 福岡大学卒業 1987年昭和62年 臨済宗大徳寺派、別格地、崇福僧堂再掛塔 1990年平成02年 臨済宗大徳寺派、三等地寿福寺住職 ----------------------------- 【寿福寺】山号 鷲峰山 福岡県福岡市 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 1190年代に臨済宗の開祖 明庵栄西禅師(建仁寺開祖)によって禅宗に改宗され江戸末期から明治の初期に大徳寺派の末寺になる | 3,718円 |
 (五月晴:粽の絵有ります【茶器/茶道具 短冊画賛 端午の節句】 直筆 丈夫意気高(五月天) 兜画(弓矢兜画)又は五月晴 粽の画 小堀良實筆 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ並巾:約縦36.3×横6cm 箱たとう紙 作者前田宗源筆 注意メール便不可 (野吉井・4400) 【コンビニ受取対応商品】丈夫意気高五月天ますらをいきたかしさつきのそら 丈夫、すなわち一人前の人間には元来勢いが誰にでもある。 清々しい五月の空のように人間誰もが本来具有(ぐゆう)している仏性(ぶしょう)は世俗の塵(ちり)の中にあってもけがされることはない。 五月晴さつきばれ・ごがつばれ 梅雨の間のさわやかな晴れ間。 陰暦5月の、梅雨の合間の晴天のこと。 【前田宗源】瑞光院 山号を紫雲山 大徳寺派 赤穂義士遺跡 1932年昭和07年04月10日京都に生 京都府立第三中学校 京都府立朱雀高校 同志社大学経済学部 京都建仁寺僧堂にて修行 ------------------------------ 【瑞光院】 京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する 紫雲山 瑞光院は 慶長18年(1613年)創建。 赤穂 浅野家とは縁があり、46士の遺髪が埋葬されている | 3,520円 |
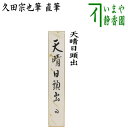 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 天晴日頭出 久田宗也筆(尋牛斎) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ並巾:約縦36.3×横6cm 箱たとう紙 作者久田宗也筆(尋牛斎) 注意メール便不可 (・42880) 【コンビニ受取対応商品】天晴日頭出てんはれてにっとういづる 天晴日頭出 雨下地上湿(てんはれてにっとういづ あめふりてちじょううるおう) 天気が良いと太陽が姿を表し、雨が降れば地上が濡れる。自然現象の何のはからいもない様であり、無用な分別妄想が微塵も無い無執着の有様の例えです。 【久田家】 久田家は3代宗旦の娘の嫁ぎ先で利休の血筋であり、家元が途絶えそうになった場合、久田家から養子で入っています。 久田家の庵号は半床庵(は んしょうあん)といい、3代宗全による二畳中板の茶室を指す。 【久田家歴代系図】 【初代 宗栄 生々斎】 1559年〜1624年3月6日 俗名は久田新八房政 (利休の甥か?) 【2代 宗利 受得斎】 1610年〜1685年11月7日 本間利兵衛 (千宗旦の娘クレの夫、藤村庸軒の兄) 【藤村庸軒】(宗旦の四天王の一人) 千家とつながりの深かった久田家初代の久田宗栄の次男で、呉服商十二屋の藤村家に養子に入ったとされる。 薮内紹智に茶の湯を学び、小堀政一(遠州)、金森重近(宗和)からも教えを受ける。のちに千宗旦のもとで台子伝授を許され宗旦四天王の一人に数えられた。 没後、荻野道興の編集により『庸軒詩集』が1803年(享和3年)に刊行された。 【3代 宗全 徳誉斎】 1647年〜1707年5月6日 元は本間勘兵衛と称した (宗全は手工に秀で、炭斗の宗全籠等、茶碗・茶杓に優品物が多数あります。) 【4代 宗也 不及斎】 1681年〜1744年1月13日 宗全の甥 <4代不及斎には二男あり、理由は不明ながら次男の宗悦が半床庵を継嗣した。> 【高倉久田家歴代】 【5代 宗悦 凉滴斎】 1715年〜1768年4月26日 不及斎の次男 【6代 磻翁宗渓 挹泉斎】 1742年〜1785年7月24日 【7代 維妙宗也 皓々斎】 1767年〜1819年11月29日 【8代 宗利】 不詳-1844年6月30日 養子、元は関宗厳と称した 【9代 一乗宗与】 不詳-1862年8月24日 住山楊甫の孫 『住山家』とは、 〇住山 楊甫(すみやま ようほ)は、初代(?〜?) 表千家6代目宗左の門人。姉は、7代目宗左の妻 〇二代(1782〜1855)天明2年〜安政2年 初代楊甫の養嗣子 表千家9代了々斎の死後、幼い吸江斎の後見人になる 〇一乗宗与(〜1862年8月24日)〜文久2年 高倉久田家9代目 (住山家八代云々斎楊甫の孫。幼名は岩之介) 【10代 宗悦 玄乗斎】 1856年〜1895年4月24日 (表千家10代吸江斎の子で皓々斎の孫) 【11代 守一宗也 無適斎】 1884年〜1946年9月13日 【12代 宗也 尋牛斎】 1925年〜2010年10月22日 大正14年(1925)京都生。名は和彦、11世無適斎宗也の長男。 京大史学科卒 【13代 宗也 得流斎】 1958年〜2011年10月13日 当代 | 34,100円 |
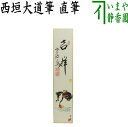 【茶器/茶道具 短冊画賛】 直筆 吉祥 西垣大道筆 猿猴捉月の画 曽根幸風画(肉筆画) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆・肉筆画 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者字:西垣大道筆 曽根幸風画 箱たとう紙 注意メール便不可 (R6/N・/7-・・野輪大・4565)〇5025 【コンビニ受取対応商品】吉祥きっしょう めでたい兆し。吉兆。きっしょう。 猿猴捉月えんこうそくげつ 欲をおこして前後をわきまえず、無謀な行動をとって大失敗すること。 身のほど知らずが、その結果身を滅ぼすことのたとえ。 「猴」は、サル。「捉月」は、月をとらえる。 井戸水に映った月をとろうとしてサルが木の枝にぶらさがって、数珠つなぎになったとたんに枝が折れてしまい、全員井戸の底に落ちて死んだという説話から。 「猿猴(えんこう)月を捉(とら)える」と読み下す。 【西垣大道】極楽寺 兵庫県城崎 1942年昭和17年 庫県に生まれる。 1949年昭和24年 分山宗興について得度。日本社会福祉大学卒業後、大徳僧堂、のち相国僧堂に掛塔。 1976年昭和51年 仏教大学大学院修士課程修了。 1978年昭和53年 兵庫県城崎郡の大徳寺派極楽禅寺住職に就任し、現在に至る。 ------------------------------ 【曽根幸風】 1936年昭和11年 京都粟田口生れ 1956年昭和31年 京都府立陶工専修校(陶画科)終了 (故陶師高嶋光楽のもとで作陶師事) 1957年昭和32年 故陶師人間国宝富本憲吉先生に陶画師事 1973年昭和48年 京都洛東 東山に開窯(幸風窯) 1978年昭和53年まで京都東山の窯元で作陶に修行 1989年平成01年 京都 伏見に移窯 (茶道の陶画を通じ絵画に励む) | 3,652円 |
 △【茶器/茶道具 短冊】 直筆 無事又は看々臘月尽 方谷豊宗筆 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 作者方谷豊宗筆 箱たとう紙 注意メール便不可 (・3405)看々臘月尽・歳月不待人・ 【コンビニ受取対応商品】無事ぶじ 無造作、平常の意味、何も起こらぬことの意味。 看々臘月尽みよみよろうげつ、つく 臘月は12月のこと。 時間はみるみるうちに過ぎ去ってしまい、今年も残りわずかであるという意味。 【方谷豊宗】海蔵寺 開山峯翁祖一(大暁禅師)は、大燈禅師を兄弟子として大応国師に学び、のち、海蔵寺を作る 1937年昭和12年生まれ 師 法谷浩明老師 第12代管長の徒弟となり得度 1959年昭和34 安養寺住職になる・現在、海蔵寺住職 ------------------------------ 【海蔵寺】 海蔵寺 開山は鼎岩法周居士の開創 | 2,772円 |
 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 関南北東西活路通又は歳月不待人又は語尽山雲海月情 有馬頼底筆 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ並巾:約縦36.3×横6cm 箱たとう紙 作者有馬頼底筆 注意メール便不可 (R5/ス吉り・17120) 【コンビニ受取対応商品】関南北東西活路通かんなんぼくとうざいかつろにつうず 年末・年始の時期に相応しい禅語です。 関はぴしゃりと閉めてどこへも通さぬ、東西南北はどこへでも立派な道がつづいているという意味。 歳月不待人さいげつひとをまたず 時間は人の都合とは関係なしに刻々と過ぎていくものであり、人を待ってくれるこFとなどない。 転じて、人はすぐに老いてしまうものだから、二度と戻らない時間をむだにしないで、努力に励めよという戒めを含む。 陶潜の『雑詩』に「盛年重ねて来たらず、一日再びあしたなり難し、時に及んで当に勉励すべし、歳月人を待たず(若い時は二度と来ない、一日に朝は二度とない、時を逃さず一瞬を大切にして勉学に励めよ)」とあるのに基づく。 語尽山雲海月情かたりつくすかいうんかいげつのじょう 山の心情、雲の心情、海の心情、月の情心、即ち一切のこころと言うのが 山雲海月の情で、この場合、親しきもの同士が胸中の心情を語りつくすさまを表す。 【有馬頼底(号 大龍窟)】萬年山相国承天禅寺 相國寺派 臨済宗 7代管長 京都仏教会 理事長、日本文化芸術財団 理事 久留米藩主 有馬家(赤松氏流)の子孫 (東京にて華族の家系に生まれ、天皇陛下のご学友となる) 1933年昭和08年 有馬本家当主有馬頼寧の従兄弟にあたる分家有馬正頼男爵の次男として東京で生を受ける 1941年昭和16年 8歳の時、大分県日田市の岳林寺で得度 1955年昭和30年 22歳 京都臨済宗相国寺僧堂に入門。大津櫪堂老師に師事 1968年昭和43年 相国寺塔頭大光明寺住職 1971年昭和46年 相国寺派教学部長 1984年昭和59年 相国寺承天閣美術館設立により事務局長 1988年昭和63年 京都仏教会理事長に就任 1995年平成07年 臨済宗相国寺派七代管長(相国寺132世)に就任 | 13,689円 |
 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 春草池塘緑又は春山如笑又は処々聴啼鳥 久田宗也筆(尋牛斎) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 箱たとう紙 サイズ並巾:約縦36.3×横6cm 作者久田宗也筆(尋牛斎) 注意メール便不可 (中・37880) 【コンビニ受取対応商品】春草池塘緑しゅんそうちとうのみどり 池の堤(ため池)には、もう春の草や緑の芽が萌えだしてきた(のどかな春の風景) 春山高花如笑しょんざんたかくはなしょうしょう 「笑」、「咲」は、ともに「わらう、さく」の両義をもつ。 「花笑鴬歌詠」では「花さいて鴬歌(おうか)の詠(えい)」と読む。 「花咲笑」は「花咲き笑う」ではなく「花笑笑」であり、春の山に花が咲き誇っている様子を表している。 処々聴啼鳥しゅしょていちょうをきく 孟浩然(もうこうねん)の五言絶句「春眠暁を覚えず、処々啼鳥を聞く、夜来風雨の声、花落つること知るいくばくぞ」前半二句 「春は夜明けがわからないほど眠い、ところどころ鳥が鳴いていたのを聞いた、夜は風雨が聞こえてた、花もいくつか落ちただろう」 穏やかな心境で眺める。長閑(のどか)な春の日の情景が描かれる。 【久田家】 久田家は3代宗旦の娘の嫁ぎ先で利休の血筋であり、家元が途絶えそうになった場合、久田家から養子で入っています。 久田家の庵号は半床庵(は んしょうあん)といい、3代宗全による二畳中板の茶室を指す。 【久田家歴代系図】 【初代 宗栄 生々斎】 1559年~1624年3月6日 俗名は久田新八房政 (利休の甥か?) 【2代 宗利 受得斎】 1610年~1685年11月7日 本間利兵衛 (千宗旦の娘クレの夫、藤村庸軒の兄) 【藤村庸軒】(宗旦の四天王の一人) 千家とつながりの深かった久田家初代の久田宗栄の次男で、呉服商十二屋の藤村家に養子に入ったとされる。 薮内紹智に茶の湯を学び、小堀政一(遠州)、金森重近(宗和)からも教えを受ける。のちに千宗旦のもとで台子伝授を許され宗旦四天王の一人に数えられた。 没後、荻野道興の編集により『庸軒詩集』が1803年(享和3年)に刊行された。 【3代 宗全 徳誉斎】 1647年~1707年5月6日 元は本間勘兵衛と称した (宗全は手工に秀で、炭斗の宗全籠等、茶碗・茶杓に優品物が多数あります。) 【4代 宗也 不及斎】 1681年~1744年1月13日 宗全の甥 <4代不及斎には二男あり、理由は不明ながら次男の宗悦が半床庵を継嗣した。> 【高倉久田家歴代】 【5代 宗悦 凉滴斎】 1715年~1768年4月26日 不及斎の次男 【6代 磻翁宗渓 挹泉斎】 1742年~1785年7月24日 【7代 維妙宗也 皓々斎】 1767年~1819年11月29日 【8代 宗利】 不詳-1844年6月30日 養子、元は関宗厳と称した 【9代 一乗宗与】 不詳-1862年8月24日 住山楊甫の孫 『住山家』とは、 住山 楊甫(すみやま ようほ)は、初代(?~?) 表千家6代目宗左の門人。姉は、7代目宗左の妻 2代(1782~1855)天明2年~安政2年 初代楊甫の養嗣子 表千家9代了々斎の死後、幼い吸江斎の後見人になる 一乗宗与(~1862年8月24日)~文久2年 高倉久田家9代目 (住山家八代云々斎楊甫の孫。幼名は岩之介) 【10代 宗悦 玄乗斎】 1856年~1895年4月24日 (表千家10代吸江斎の子で皓々斎の孫) 【11代 守一宗也 無適斎】 1884年~1946年9月13日 【12代 宗也 尋牛斎】 1925年~2010年10月22日 大正14年(1925)京都生。名は和彦、11世無適斎宗也の長男。 京大史学科卒 【13代 宗也 得流斎】 1958年~2011年10月13日 当代 | 29,700円 |
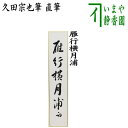 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 雁行横月浦 久田宗也筆(尋牛斎) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ並巾:約縦36.3×横6cm 作者久田宗也筆(尋牛斎) 箱たとう紙 注意メール便不可 (・37880) 【コンビニ受取対応商品】雁行横月浦がんこうげっぽによこたう 雁が月あかりの水辺をの群れをなして飛んで行く。 秋の月明かりの中、湖の上を飛んでいく雁。 【久田家】 久田家は3代宗旦の娘の嫁ぎ先で利休の血筋であり、家元が途絶えそうになった場合、久田家から養子で入っています。 久田家の庵号は半床庵(は んしょうあん)といい、3代宗全による二畳中板の茶室を指す。 【久田家歴代系図】 【初代 宗栄 生々斎】 1559年〜1624年3月6日 俗名は久田新八房政 (利休の甥か?) 【2代 宗利 受得斎】 1610年〜1685年11月7日 本間利兵衛 (千宗旦の娘クレの夫、藤村庸軒の兄) 【藤村庸軒】(宗旦の四天王の一人) 千家とつながりの深かった久田家初代の久田宗栄の次男で、呉服商十二屋の藤村家に養子に入ったとされる。 薮内紹智に茶の湯を学び、小堀政一(遠州)、金森重近(宗和)からも教えを受ける。のちに千宗旦のもとで台子伝授を許され宗旦四天王の一人に数えられた。 没後、荻野道興の編集により『庸軒詩集』が1803年(享和3年)に刊行された。 【3代 宗全 徳誉斎】 1647年〜1707年5月6日 元は本間勘兵衛と称した (宗全は手工に秀で、炭斗の宗全籠等、茶碗・茶杓に優品物が多数あります。) 【4代 宗也 不及斎】 1681年〜1744年1月13日 宗全の甥 <4代不及斎には二男あり、理由は不明ながら次男の宗悦が半床庵を継嗣した。> 【高倉久田家歴代】 【5代 宗悦 凉滴斎】 1715年〜1768年4月26日 不及斎の次男 【6代 磻翁宗渓 挹泉斎】 1742年〜1785年7月24日 【7代 維妙宗也 皓々斎】 1767年〜1819年11月29日 【8代 宗利】 不詳-1844年6月30日 養子、元は関宗厳と称した 【9代 一乗宗与】 不詳-1862年8月24日 住山楊甫の孫 『住山家』とは、 〇住山 楊甫(すみやま ようほ)は、初代(?〜?) 表千家6代目宗左の門人。姉は、7代目宗左の妻 〇二代(1782〜1855)天明2年〜安政2年 初代楊甫の養嗣子 表千家9代了々斎の死後、幼い吸江斎の後見人になる 〇一乗宗与(〜1862年8月24日)〜文久2年 高倉久田家9代目 (住山家八代云々斎楊甫の孫。幼名は岩之介) 【10代 宗悦 玄乗斎】 1856年〜1895年4月24日 (表千家10代吸江斎の子で皓々斎の孫) 【11代 守一宗也 無適斎】 1884年〜1946年9月13日 【12代 宗也 尋牛斎】 1925年〜2010年10月22日 大正14年(1925)京都生。名は和彦、11世無適斎宗也の長男。 京大史学科卒 【13代 宗也 得流斎】 1958年〜2011年10月13日 当代 | 30,800円 |
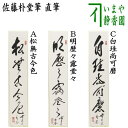 △【茶器/茶道具 短冊】 直筆 松無古今色又は明歴々露堂々又は白珪尚可磨 佐藤朴堂筆 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ広巾:約縦36.3×横7.5cm 箱たとう紙 作者佐藤朴堂筆 注意メール便不可 (ス野中3750)万里無片雲・明歴々露堂々・清風払明月・明月清風共一家 【コンビニ受取対応商品】松無古今色まつにここんのいろなし 松の翠は四季を通じ、今昔なくいつもみずみずしく茂っている意味。 明歴々露堂々めいれきれきつゆどうどう 明らかにはっきりと顕われていて、隠すところなどすこしもない、という意味。 白珪尚可磨はっけいなおみがくべし(白圭尚可磨) 完全無欠の貴重な玉でも、さらに磨き続けるべきであるという意味。 【佐藤朴堂(本名 宗秀)】 1935年昭和10年07月京都市に生 1947年昭和22年09月兵庫県(但馬:大徳寺派蔵雲寺熙道和尚に就て得度 1956年昭和31年 京都花園妙心寺専門道場禅修業に参禅 1956年昭和46年06月大徳寺派福聚院に住職す 1977年昭和52年04月大徳寺前往位に昇進 ------------------------------ 【福聚院】大徳寺派 滋賀県 | 2,992円 |
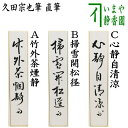 【茶器/茶道具 短冊】 直筆 竹外茶煙静又は掃雪開松径又は心静自清涼 久田宗也筆(尋牛斎) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | 直筆 サイズ並巾:約縦36.3×横6cm 箱たとう紙 作者久田宗也筆(尋牛斎) 注意メール便不可 (中・37880) 【コンビニ受取対応商品】竹外茶烟静ちくがいちゃえんしずかなり 林のむこうに、茶を焙(ほう)ずる煙が静かに立ちのぼっている。 山村の平和な風景。自然の営み。 掃雪開松径ゆきをはいてまつのみちをひらく 降り積もった雪を掃くと、そこには松の小径が開けた。 悩みや迷いが一掃されて、生地の仏性(ぶっしょう)が現前したようす。 門閑心静自清涼ころしずかなればおのれはせいりょう 平穏な世の中で屋外が静寂であれば、涼風と共に精神が落ち着く。 【久田家】 久田家は3代宗旦の娘の嫁ぎ先で利休の血筋であり、家元が途絶えそうになった場合、久田家から養子で入っています。 久田家の庵号は半床庵(は んしょうあん)といい、3代宗全による二畳中板の茶室を指す。 【久田家歴代系図】 【初代 宗栄 生々斎】 1559年〜1624年3月6日 俗名は久田新八房政 (利休の甥か?) 【2代 宗利 受得斎】 1610年〜1685年11月7日 本間利兵衛 (千宗旦の娘クレの夫、藤村庸軒の兄) 【藤村庸軒】(宗旦の四天王の一人) 千家とつながりの深かった久田家初代の久田宗栄の次男で、呉服商十二屋の藤村家に養子に入ったとされる。 薮内紹智に茶の湯を学び、小堀政一(遠州)、金森重近(宗和)からも教えを受ける。のちに千宗旦のもとで台子伝授を許され宗旦四天王の一人に数えられた。 没後、荻野道興の編集により『庸軒詩集』が1803年(享和3年)に刊行された。 【3代 宗全 徳誉斎】 1647年〜1707年5月6日 元は本間勘兵衛と称した (宗全は手工に秀で、炭斗の宗全籠等、茶碗・茶杓に優品物が多数あります。) 【4代 宗也 不及斎】 1681年〜1744年1月13日 宗全の甥 <4代不及斎には二男あり、理由は不明ながら次男の宗悦が半床庵を継嗣した。> 【高倉久田家歴代】 【5代 宗悦 凉滴斎】 1715年〜1768年4月26日 不及斎の次男 【6代 磻翁宗渓 挹泉斎】 1742年〜1785年7月24日 【7代 維妙宗也 皓々斎】 1767年〜1819年11月29日 【8代 宗利】 不詳-1844年6月30日 養子、元は関宗厳と称した 【9代 一乗宗与】 不詳-1862年8月24日 住山楊甫の孫 『住山家』とは、 〇住山 楊甫(すみやま ようほ)は、初代(?〜?) 表千家6代目宗左の門人。姉は、7代目宗左の妻 〇二代(1782〜1855)天明2年〜安政2年 初代楊甫の養嗣子 表千家9代了々斎の死後、幼い吸江斎の後見人になる 〇一乗宗与(〜1862年8月24日)〜文久2年 高倉久田家9代目 (住山家八代云々斎楊甫の孫。幼名は岩之介) 【10代 宗悦 玄乗斎】 1856年〜1895年4月24日 (表千家10代吸江斎の子で皓々斎の孫) 【11代 守一宗也 無適斎】 1884年〜1946年9月13日 【12代 宗也 尋牛斎】 1925年〜2010年10月22日 大正14年(1925)京都生。名は和彦、11世無適斎宗也の長男。 京大史学科卒 【13代 宗也 得流斎】 1958年〜2011年10月13日 当代 | 29,700円 |