#D 図解即戦力 電子書籍 [本・雑誌・コミック]
楽天市場検索
本・雑誌・コミック
小説・エッセイ (0)
資格・検定 (0)
ライフスタイル (0)
ホビー・スポーツ・美術 (0)
絵本・児童書・図鑑 (0)
語学・辞典・年鑑 (0)
学習参考書・問題集 (0)
旅行・留学 (0)
人文・地歴・社会 (3) (#D 図解即戦力 電子書籍)
ビジネス・経済・就職 (54) (#D 図解即戦力 電子書籍)
PC・システム開発 (37) (#D 図解即戦力 電子書籍)
科学・医学・技術 (3) (#D 図解即戦力 電子書籍)
コミック (0)
ライトノベル (0)
ボーイズラブ (0)
ティーンズラブ (0)
エンターテインメント (0)
写真集 (0)
古書・希少本 (0)
楽譜 (0)
雑誌 (0)
新聞 (0)
洋書 (0)
カレンダー (0)
ポスター (0)
パンフレット (0)
その他 (0)
本・雑誌・コミック
小説・エッセイ (0)
資格・検定 (0)
ライフスタイル (0)
ホビー・スポーツ・美術 (0)
絵本・児童書・図鑑 (0)
語学・辞典・年鑑 (0)
学習参考書・問題集 (0)
旅行・留学 (0)
人文・地歴・社会 (3) (#D 図解即戦力 電子書籍)
ビジネス・経済・就職 (54) (#D 図解即戦力 電子書籍)
PC・システム開発 (37) (#D 図解即戦力 電子書籍)
科学・医学・技術 (3) (#D 図解即戦力 電子書籍)
コミック (0)
ライトノベル (0)
ボーイズラブ (0)
ティーンズラブ (0)
エンターテインメント (0)
写真集 (0)
古書・希少本 (0)
楽譜 (0)
雑誌 (0)
新聞 (0)
洋書 (0)
カレンダー (0)
ポスター (0)
パンフレット (0)
その他 (0)
97件中 1件 - 30件
1 2 3 4
| 商品 | 説明 | 価格 |
|---|---|---|
 図解即戦力 Amazon Web Servicesのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 小笠原種高 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p>Amazon Web Services(AWS)のしくみや関連技術についてわかりやすく解説する図解本です。エンジニア1年生、IT業界などへの転職・就職を目指す人が、AWS関連の用語、しくみ、クラウドとネットワークの基礎技術などを一通り学ぶことのできる、1冊目の入門書としてふさわしい内容を目指します。本書では、クラウドやネットワークの基礎から解説し、AWSのサーバーサービス、ストレージサービス、ネットワークサービス、データベースサービスについて具体的なサービス名を挙げながら初心者向けにわかりやすく紹介します。今までのAWS解説書では用語がわからず難しかったという人も本書なら安心して学ぶことができます。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 2,178円 |
 図解即戦力 証券業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 土信田 雅之【監修】 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>(概要)</strong><br /> **※この商品は固定レイアウトで作成されており,タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また,文字列のハイライトや検索,辞書の参照,引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は Gihyo Disital Publishing ( gihyo.jp/mk/dp/ebook/2021/978-4-297-11879-2 )も合わせてご覧ください。****証券業は、株式・投資信託・債券・デリバティブなど扱う商品は幅広く、金融の知識に加え、経済の動きを読む力が求められます。仕事はリテール・ホールセールから投資銀行業務まであり、専門性も異なります。低金利下で資産運用が注目されており、証券業の役割はますます高まっています。本書では、証券ビジネスの基本としくみから始め、業界地図、多様な金融商品、証券会社の仕事といった内側まで理解できます。知っておきたい専門用語もわかりやすく説明しています。</p> <p>(こんな方におすすめ)<br /> ・証券業界に就職・転職を考えている方<br /> ・いまの証券業界の事情を知りたい方<br /> ・今後の証券ビジネスの展開に興味がある方</p> <p>(目次)<br /> Chapter 1 証券業界を取り巻く環境<br /> 01 日本の証券業界をけん引する大手総合證券<br /> 02 総合証券化に活路を見い出す準大手証券<br /> 03 独自色で生き残りを図る地場証券<br /> 04 アベノミクスでセルフ層の需要が回復しつつある?<br /> 05 日本取引所グループの誕生<br /> 06 普及が進む非課税制度のNISAやiDeCo<br /> 07 小売業やカード会社などの異業種からの参入が増加している<br /> 08 老後2,000万円問題が世の中に与えた衝撃<br /> 09 コロナショックで証券会社の口座開設数が増加している?<br /> Chapter 2 証券業界の基礎知識<br /> 01 日本の証券業の始まり〜世界恐慌や終戦までの歴史〜<br /> 02 直接金融の担い手である証券業界<br /> 03 高度経済成長とバブル崩壊〜失われた20 年〜<br /> 04 金融ビッグバンとネット証券の躍進<br /> 05 金融業界から見る証券業界の市場規模<br /> 06 証券業界の金融ビジネスとほかの金融業界との違い<br /> 07 さまざまな証券会社の種類と特徴<br /> 08 国内における証券取引所の役割<br /> 09 証券会社が扱う「証券」ってそもそもどういうもの?<br /> 10 証券の売買のしくみと証券会社の仕事<br /> 11 証券会社が担う4大業務<br /> 12 証券業界における絶対のオキテ! 金融商品取引法とは?<br /> Chapter 3 ?本の証券会社<br /> 01 証券会社の変遷<br /> 02 証券会社の時価総額と預かり資産ランキング<br /> 03 証券業界で金融コングロマリット化が進む<br /> 04 証券業界をけん引する国内5大証券<br /> 05 現在、国内準大手証券は2社のみとなっている<br /> 06 個人投資家相手に営業する中堅・地場証券<br /> 07 シェアを拡大し続けているネット専業証券<br /> 08 プライベートバンキングに力を入れ始めた外資系証券<br /> 09 デリバティブ取引をけん引する先物取引系証券会社<br /> 10 ホールセール専業の証券会社も存在する<br /> Chapter 4 証券会社のビジネスのしくみ<br /> 01 証券会社の収益源<br /> 02 顧客本意の業務運営が促す収益モデルの転換<br /> 03 アンダーライティング業務ってなに?<br /> 04 株式公開(IPO)は証券会社の収入源の1つ<br /> 05 投資銀行業務の代表的な業務であるM&A<br /> 06 マーケット調査の専門である「リサーチ」部門<br /> 07 顧客と証券会社の資産は別々に保管・管理されている<br /> 08 顧客の資産の管理と運用を行うアセットマネジメント<br /> 09 証券会社ではさまざまなリスクを管理する必要がある<br /> 10 証券会社における社会貢献活動<br /> Chapter 5 証券業界が取り扱うさまざまな?融商品<br /> 01 金融商品にはリスクとリターンがある<br /> 02 企業や国が資金調達を目的に発行する「有価証券」<br /> 03 証券取引所で取引する上場株式<br /> 04 手元資金以上の売買が可能となる「信用取引」<br /> 05 商品ラインナップが充実している「投資信託」<br /> 06 投機性の高さが人気の「先物取引」と「オプション取引」<br /> 07 個人投資家からの人気が急上昇中の「FX」<br /> 08 証券会社の収益を支える債券<br /> 09 投資と保険を融合させた「年金保険」<br /> 10 資産運用を行いながら資金調達できる「証券担保ローン」<br /> 11 不動産を証券化した商品「REIT」<br /> 12 投資一任契約で運用から管理まで行う「ラップ口座」<br /> Chapter 6 証券会社の仕事と組織<br /> 01 証券会社の組織の全体像<br /> 02 証券業界の基本データ〜給与から福利厚生まで〜<br /> 03 証券業界のキャリアパス<br /> 04 証券業界が力を入れる人材開発と研修制度<br /> 05 証券会社の花形「リテール営業」部門<br /> 06 大企業や機関投資家が相手の「ホールセール」部門<br /> 07 企業の買収・合併や資金調達に関わる「投資銀行業務」部門<br /> 08 金融商品の開発・組成を行う「ストラクチャリング」部門<br /> 09 資金を投じて自己売買を行う「ディーリング」部門<br /> 10 市場に影響を与える証券会社の「調査部門」<br /> 11 証券会社の数字・統計の専門家「クオンツ」<br /> 12 顧客の信頼を高める「カスタマーサポート」<br /> 13 信用を維持する監視役「法務」「コンプライアンス」部門<br /> 14 証券会社の生命線である「システム」部門<br /> Chapter 7 支店証券マンの仕事<br /> 01 支店全体のスケジュールと動き<br /> 02 若手社員の1日のスケジュール<br /> 03 マネジャーの1日のスケジュール<br /> 04 証券マンに課される目標とは<br /> 05 重要視される新規顧客の開拓営業<br /> 06 証券会社のトレーダーの1日のスケジュール<br /> 07 気になる新人の転勤、異動のタイミング<br /> Chapter 8 グローバルな視野が必要な証券業界<br /> 01 世界に影響を与える3大証券取引所<br /> 02 そのほか知っておきたい世界各地の証券取引所<br /> 03 金融の歴史を揺るがした金融危機ってなに?<br /> 04 世界の金融をけん引する米国の証券市場<br /> 05 老舗の名門企業が多い欧州の証券市場<br /> 06 日本の取引規模を猛追する中国市場<br /> 07 中国の手が伸びる香港市場と停滞が続く韓国市場<br /> 08 注目を集めるASEAN市場<br /> Chapter 9 証券業界の課題と未来<br /> 01 野村證券が進める構造改革<br /> 02 進まない日本の投資教育<br /> 03 ポスト・アベノミクス戦略の模索が続く<br /> 04 金融シームレス化が加速している<br /> 05 証券業界で起きているAI革命とは<br /> 06 東京証券取引所によるフィンテックの取り組み<br /> 07 売買手数料無料化によるフィー型ビジネスへの移行が必須に<br /> 08 期待されるIFAと証券業界の今後の関わりかた<br /> 09 大相続時代に立ち向かう必要がある大手証券会社<br /> 10 日本の総合取引所は誕生したばかり**</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,650円 |
 図解即戦力 食品業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 松岡 康浩 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>(概要)</strong><br /> **※この商品は固定レイアウトで作成されており,タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また,文字列のハイライトや検索,辞書の参照,引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は Gihyo Disital Publishing ( gihyo.jp/mk/dp/ebook/2020/978-4-297-11366-7 )も合わせてご覧ください。****人が生活していく上で必要な衣・食・住の一翼を担う食品業界。本書では食品業界を“生産者から消費者に届くまで”のサプライチェーンとして、素材型・加工型製造業を中心に、食材生産(農畜水産業)、流通・小売(食品産業)、外食産業までのあらましとしくみを俯瞰します。食品消費の変化からフードシステム、最新ロジスティックスや堅調に伸びる食品の電子商取引まで、就活生はもちろん、新たなビジネスチャンスを探している人にも、気になる業界の最新動向がわかります。</p> <p>(こんな方におすすめ)<br /> ・食品製造/加工/流通業界に就職/転職を考えている人(農畜水産および外食産業に就職、従事している人も)<br /> ・食品産業に進出を考えている経営者・起業家、取引・協業関係者</p> <p>(目次)<br /> Chapter1 食品業界の最新動向<br /> 01 少子高齢化がもたらすもの<br /> 02 食品消費の変化<br /> 03 消費者の健康志向と保健機能食品<br /> 04 グローバル化と食料自給率<br /> 05 食の輸出による食産業の活性化<br /> 06 労働力の不足から省力化へ<br /> 07 環境への課題<br /> 08 食料資源への対策<br /> Chapter2 食品業界を構成する各業界のあらまし<br /> 01 私たちの国の食生活の特徴<br /> 02 食品産業の発展と変容<br /> 03 食品が消費者に届くまで<br /> 04 農畜水産業のしくみ<br /> 05 食品製造業のしくみ<br /> 06 食品流通業のしくみ<br /> 07 外食産業のしくみ<br /> Chapter3 農畜水産業のあらましと仕事<br /> 01 食材生産を担う農畜水産業<br /> 02 稲作から果樹までの耕種農業<br /> 03 家畜から乳や卵・肉を採る畜産業<br /> 04 海や川から魚介類を届ける水産業<br /> 05 6次産業とアグリビジネス<br /> 06 地域の農業を活性化させる農業協同組合<br /> 07 1次産業と行政<br /> Chapter4 食品製造業の種類と特徴<br /> 01 食品製造業の構造<br /> 02 製粉<br /> 03 食用油<br /> 04 製糖・でんぷん<br /> 05 製塩<br /> 06 農産加工品<br /> 07 味噌・醤油<br /> 08 食酢、その他の調味料<br /> 09 ソース・マヨネーズ・スパイス類<br /> 10 素材メーカー<br /> 11 食肉加工品<br /> 12 乳製品<br /> 13 水産加工品<br /> 14 製パン<br /> 15 冷凍食品<br /> 16 レトルト食品<br /> 17 インスタント食品<br /> 18 清涼飲料<br /> 19 酒類<br /> 20 菓子<br /> 21 美容・健康食品(機能性食品)<br /> 22 中食<br /> Chapter5 食品製造業の仕事内容<br /> 01 仕事の種類と関係<br /> 02 商品企画(マーケティング)の仕事と人材<br /> 03 研究開発の仕事と人材<br /> 04 生産技術の仕事と人材<br /> 05 購買・調達の仕事と人材<br /> 06 製造の仕事と人材<br /> 07 品質保証の仕事と人材<br /> 08 生産・流通管理の仕事と人材<br /> 09 営業の仕事と人材<br /> 10 経営企画の仕事と人材<br /> Chapter6 食品流通業のあらましと仕事<br /> 01 あらゆる食品を調達する商社・卸売業<br /> 02 総合商社・食品専門商社の業態と仕事<br /> 03 卸売市場の業態と仕事<br /> 04 食品卸の業態と仕事<br /> 05 消費者との接点である小売業<br /> 06 スーパーマーケットの業態と仕事1<br /> 07 スーパーマーケットの業態と仕事2<br /> 08 コンビニエンスストア(CVS)の業態と仕事1<br /> 09 コンビニエンスストア(CVS)の業態と仕事2<br /> 10 専門店の業態と仕事<br /> 11 ドラッグストアの業態と仕事<br /> 12 通信販売(EC)の業態と仕事<br /> Chapter7 外食産業のあらましと仕事<br /> 01 外食産業の企業規模による特徴<br /> 02 外食産業のビジネスモデル<br /> 03 外食産業の代表的な職種<br /> 04 外食産業の市場と競争環境<br /> 05 外食産業の未来<br /> Chapter8 食品業界にかかわる法令<br /> 01 食品業界に関係する主な法律<br /> 02 「食料・農業・農村基本法」と「農地法」<br /> 03 JAS法<br /> 04 食品安全基本法<br /> 05 食品衛生法<br /> 06 「景品表示法」と「健康増進法」<br /> 07 食品表示法<br /> Chapter9 食品業界の課題と将来<br /> 01 食品をめぐる貿易協定<br /> 02 農産物の安全、品質に関する規範<br /> 03 食品安全マネジメントシステムの普及<br /> 04 スマート農業への期待<br /> 05 ICTによるロジスティックスの効率化**</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,650円 |
 図解即戦力 商社のしくみとビジネスがこれ1 冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 治良博史 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>(概要)</strong><br /> **※この商品は固定レイアウトで作成されており,タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また,文字列のハイライトや検索,辞書の参照,引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は Gihyo Disital Publishing ( gihyo.jp/mk/dp/ebook/2021/978-4-297-11749-8 )も合わせてご覧ください。****大学生の就職希望先として今も昔も根強い人気を誇るのが商社です。商社と聞くと、まず商取引を仲介する会社というイメージを持つかもしれません。しかし現在の商社はそれだけに限らず、あらゆる分野においてモノとカネを投入して儲けを生み出す投資会社という側面がより濃くなっています。本書では、商社業界の歴史や取り巻く状況から、商社マンの仕事や待遇、商社が取り組む新ビジネスまで、現在の商社の姿を理解するために必要な知識をわかりやすく解説しています。</p> <p>(こんな方におすすめ)<br /> ・総合商社への就職を目指す学生、商社と取引がある社会人など</p> <p>(目次)<br /> 第1章 商社業界の最新動向<br /> 01 今の商社は何を行っているのか?<br /> 02 投資会社としての側面が強まる総合商社<br /> 03 全業界とのつながりが強みの商社<br /> 04 役割分担が進む総合商社と専門商社<br /> 05 新興国経済との密接な関係<br /> 06 資源ビジネスと非資源ビジネス<br /> 07 国策に絡む商社の役割<br /> 08 有事における商社の活躍<br /> 第2章 商社の変遷<br /> 01 日本の経済発展に大きく寄与した商社<br /> 02 総合商社は日本独自の企業形態<br /> 03 商取引こそが商社という稼業の原点<br /> 04 商社の姿は日々変わりゆく<br /> 05 高度経済成長下で伸びた商社の商取引<br /> 06 銀行の強大な存在感とメーカーの物流機能強化<br /> 07 メーカーが力をつけたことでささやかれた「商社不要論」<br /> 08 商取引における「中抜き」からの脱却<br /> 09 海外シフトを通じメーカーと新たな関係を築く<br /> 第3章 日本の7大総合商社<br /> 01 伊藤忠商事の最新動向と特徴<br /> 02 三菱商事の最新動向と特徴<br /> 03 住友商事の最新動向と特徴<br /> 04 三井物産の最新動向と特徴<br /> 05 丸紅の最新動向と特徴<br /> 06 豊田通商の最新動向と特徴<br /> 07 双日の最新動向と特徴<br /> 08 資産・従業員数で見る7 大総合商社の比較<br /> 09 ROAとROEで見る5 大総合商社の比較<br /> 10 売上総利益・自己資本比率で見る7大総合商社の比較<br /> 第4章 分野に特化した専門商社<br /> 01 商社系・メーカー系・独立系の主な専門商社<br /> 02 一点特化型の専門商社 扱う商材の特徴は?<br /> 03 専門商社の仕事はトレードビジネスが中心<br /> 04 総合商社にはない専門商社の独自性<br /> 05 総合商社系専門商社の特徴<br /> 06 メーカー系専門商社の特徴<br /> 07 独立系専門商社の特徴<br /> 第5章 商社の組織構造<br /> 01 総合商社における組織図と事業部門<br /> 02 タテ型組織からヨコ型組織への変革<br /> 03 多岐にわたる事業部門の業務内容<br /> 04 世界を舞台に活躍する商社の間接部門<br /> 05 世界に広がる商社のネットワーク<br /> 06 商社が持つ海外拠点 現地法人・支店・駐在員事務所<br /> 07 複合的な知識のため各部門の連携が進む<br /> 08 子会社と連携を強めて事業を展開していく<br /> 09 資本業務提携を結び会社の業績を上げる<br /> 第6章 商社マンの採用・待遇・キャリアパス<br /> 01 海外で戦える人材を作る商社の研修体制<br /> 02 世界各地で働く商社マンに求められる能力<br /> 03 気になる給与や福利厚生 平均給与水準はいくら?<br /> 04 海外で働く商社マンの現地での主な業務内容<br /> 05 国内の本社や支社に勤務した場合の仕事内容<br /> 06 本社からこつこつと経験を積む商社マンのキャリアパス<br /> 07 新人商社マンの1日のスケジュールモデル<br /> 08 中堅商社マンの1日のスケジュールモデル<br /> 09 商社の新卒採用事情<br /> 10 商社の転職事情<br /> 第7章 商社の利益を生み出す8つの機能<br /> 01 総合商社の主な利益のしくみ<br /> 02 商社が持つ8つの機能<br /> 03 商取引1 事業内容<br /> 04 商取引2 商取引からビジネスが広がる<br /> 05 情報調査1 事業内容<br /> 06 情報調査2 IT技術の進化に伴う質の変化<br /> 07 市場開拓1 事業内容<br /> 08 市場開拓2 海外駐在の意味<br /> 09 事業経営1 事業内容<br /> 10 事業経営2 投資した事業との関わり方<br /> 11 リスクマネジメント1 事業内容<br /> 12 リスクマネジメント2 リスク判断の仕方<br /> 13 物流事業1 事業内容<br /> 14 物流事業2 商社が変える物流の在り方<br /> 15 金融事業1 事業内容<br /> 16 金融事業2 商社金融と一般金融の違い<br /> 17 オーガナイザー機能1 事業内容<br /> 18 オーガナイザー機能2 商取引におけるオーガナイザー<br /> 第8章 商社が展開するビジネスモデル事業例<br /> 01 投資会社としての商社<br /> 02 先遣隊に欠かせぬパートナーの選定<br /> 03 メーカーと連携して海外市場を切り開く<br /> 04 商社による事業マネジメント<br /> 05 経営者を育成して投資先会社を運営する<br /> 06 バリューチェーンを構築する<br /> 07 新しいビジネスモデルへの取り組み<br /> 08 新しい産業分野における商社の活躍<br /> 09 発展途上国への経済援助案件<br /> 10 商社のオーガナイザー機能の真骨頂<br /> 11 組織としてのリスクマネジメント<br /> 12 トレード契約ではない契約増加への対応<br /> 第9章 商社が手掛ける新ビジネス<br /> 01 社外の人も使える三井物産新オフィス<br /> 02 NTTと組みDXを進める三菱商事<br /> 03 スタンプ式めっき処理装置の販売事業を展開する兼松<br /> 04 地域商社ふじのくに物産の地域プラットフォーム事業<br /> 05 伊藤忠商事のファミリーマート改革<br /> 06 次世代通信5Gに対応する商社<br /> 第10章 商社業界の行方<br /> 01 今後商社に求められる機能<br /> 02 商社を取り巻く業界のM&A動向<br /> 03 サステナビリティの実現<br /> 04 丸紅のビジネスプランコンテスト<br /> 05 デジタル技術と新たな付加価値の提供<br /> 06 商社のリスクマネジメントの行方<br /> 07 総合商社は生き残れるのか?<br /> 08 2030年商社は何をしている?**</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,650円 |
 図解即戦力 債券のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 土屋剛俊【監修】 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>(概要)</strong><br /> **※この商品は固定レイアウトで作成されており,タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また,文字列のハイライトや検索,辞書の参照,引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は Gihyo Disital Publishing ( gihyo.jp/mk/dp/ebook/2021/978-4-297-12244-7 )も合わせてご覧ください。****債券という言葉を聞いたことがあっても、あなたはちゃんと説明できますか? この本では債券とは何かからはじめて、種類、市場、参加者、売買のしくみ、得失とリスクをやさしく基礎から説明します。発行から売買・償還までの流れ、証券会社の役割、誰が買っているのか、価格はどう決まるのか、デフォルトしたらどうなるのかなど、しくみ全体が理解できます。個人で買える債券もあり、金利・景気・物価・株価と債券価格の関係を知っておけば資産運用にも役立ちます。</p> <p>(こんな方におすすめ)<br /> ・債券についての基本的な知識を整理してしっかり理解したい人<br /> ・学生、新社会人、個人投資家など、債券のことを勉強したい初心者</p> <p>(目次)<br /> 第1章債券ってなんですか?<br /> 01債券と株式は何が違うの?<br /> 02債券を買うとどういう得がある?<br /> 03債券は誰が発行しているの?<br /> 04債券は株式より確実に儲かるの?<br /> 05どんな債券なら安心して投資できる?<br /> 06債券にはどんなリスクがあるの?<br /> 07債券にもインサイダー取引などの罰則がある?<br /> 08マイナス金利は債券にどんな影響を与えているの?<br /> 09世界で最初の債券は何?<br /> 第2章債券にはどんなものがあるの?<br /> 10国債のほかにどんな債券があるの?<br /> 11個人が買える債券の種類を教えて?<br /> 12企業に投資するために債券を買いたい!<br /> 13海外の債券を買うこともできるの?<br /> 14割引債ってなんですか?<br /> 15株式に転換できる社債があるの?<br /> 16デリバティブってなんですか?<br /> 17仕組債の利回りが高いと聞いたけど?<br /> 18サブプライムローンも債券の一種?<br /> 第3章債券の買い方・売り方と満期まで<br /> 19債券はどこで買えるの?<br /> 20社債を買うときに注目することは?<br /> 21債券はいつ募集しているの?<br /> 22国債の金利はどう決まるの?<br /> 23個人で買えない債券はどこにいくの?<br /> 24社債の金利はどう決まるの?<br /> 25利子の支払いと償還の手続きは?<br /> 26債券を途中で売りたいときは?<br /> 27どうやって売買相場がわかるの?<br /> 28企業が破綻したら社債は紙切れになる?<br /> 29利子や売却益・償還差益にかかる税金は?<br /> 第4章債券価格が変わる理由には何がある?<br /> 30金利が上がると債券価格が下がるのはなぜ?<br /> 31金利に影響を与える要因は?<br /> 32株式相場と債券相場は逆の動きをする?<br /> 33日本の債券はすべて単利で計算していいの?<br /> 34イールドカーブってなんですか?<br /> 35デュレーションってなんですか?<br /> 36信用不安で暴落したら売り?買い?<br /> 第5章知っておきたい債券市場のしくみ<br /> 37債券市場に個人投資家はどれくらいいるの?<br /> 38機関投資家っていったい誰のこと?<br /> 39ヘッジファンドって何をしているの?<br /> 40日本銀行は国債とどう関わっているの?<br /> 41日本の国債は絶対に大丈夫なの?<br /> 42ユーロ円債は欧州でしか買えないの?**</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,760円 |
 図解即戦力 ホテル業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 吉田雅也 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は<a href="gihyo.jp/mk/dp/ebook/2023/978-4-297-14483-8">Gihyo Digital Publishing</a>も併せてご覧ください。</strong></p> <h2><strong>◆ホテル業界の「今」がこの1冊でよくわかる!◆</strong></h2> <p>2023年にインバウンド旅行者の消費額は過去最高を記録しました。コロナ禍前(2019年)と比較すると、訪日外国人の宿泊費単価は4.4万円から7.0万円に増加、平均泊数も長期化しています。そのなかで、ホテル各社は最上級ホテル「ラグジュアリーホテル」を新設・提供しています。ほかにも、長期滞在ホテル、サブスク型ホテル、分散型ホテルなど……。さまざまなホテルが登場し多様化しました。<br /> そこで、本書は「今」のホテル業界の全体像を俯瞰できるように、ホテル経営の基礎から最新動向まで丁寧に解説。マーケティング戦略やITの活用、新サービスなども扱っているので、就活生はもちろん、新たなビジネスチャンスを探している人も、気になる業界の最新動向がわかります。外資系ホテル・国内ホテルの要職を歴任し、ホテル経営学を教える大学教授が初学者にもわかりやすくお教えします!</p> <h2><strong>■こんな方におすすめ</strong></h2> <p>・ホテル業界志望者や業界関係者<br /> ・ホテル業界への投資に興味がある人</p> <h2><strong>■目次</strong></h2> <p><strong>Chapter1 ホテル業界の最新動向</strong><br /> 01 アフターコロナの観光と宿泊産業の現状<br /> 02 国策としての「観光立国」とホテルの役割<br /> 03 インバウンド旅行者の消費額は過去最高を記録<br /> 04 国内旅行の消費額はコロナ前水準まで回復<br /> 05 インバウンドにおける地域格差の拡大<br /> 06 人手不足の深刻化 宿泊業従事者の待遇改善が急務<br /> 07 国際旅行者と訪日旅行者のニーズ<br /> 08 高まるサステナビリティへの関心 環境配慮と地域貢献<br /> 09 ユニバーサルツーリズムの推進 「施設」と「心」のバリアフリー<br /> 10 カスタマーハラスメントを繰り返す客の宿泊拒否が可能に<br /> COLUMN1 IRの動向とカジノホテル<br /> <strong>Chapter2 ホテル業界の基礎知識</strong><br /> 01 高級ホテルと低価格ホテルの誕生<br /> 02 日本におけるホテルの誕生と発展<br /> 03 宿泊施設の分類と軒数の推移<br /> 04 ホテルと旅館の違い ホテルは洋室、旅館は和室が基本<br /> 05 ホテルの分類方法と日本におけるホテルの分類<br /> 06 宿泊、食堂、宴会機能をフル装備したシティホテル<br /> 07 リゾートホテル レジャーのための多様なホテル<br /> 08 ビジネスホテルの展開と宿泊特化型ホテル<br /> 09 ブティックホテルとライフスタイルホテル<br /> 10 民泊の台頭と課題<br /> COLUMN2 Airbnbはなぜ成功したのか?<br /> <strong>Chapter3 ホテルビジネスのしくみ</strong><br /> 01 装置産業・労働集約産業としてのホテルビジネスの特性<br /> 02 ホテルビジネスの3つの機能 所有、経営、運営<br /> 03 オーナーが自ら経営・運営を行う所有直営方式<br /> 04 物件を賃借して運営するリース方式<br /> 05 本部のブランド力を活用するフランチャイズ契約方式<br /> 06 オペレーターが経営陣を派遣するマネジメント・コントラクト方式<br /> 07 「持たざる経営」へのシフト 所有・リースからMC・FCへ<br /> 08 アフェリエイト、リファーラル さまざまな業務提携のタイプ<br /> 09 本業のノウハウや施設を活用したホテル施設外のビジネス<br /> 10 ホテル・旅館の再生ビジネスとREITのしくみ<br /> COLUMN3 ホテルオーナーとオペレーターの役割と緊張関係<br /> <strong>Chapter4 ホテルの収益構造</strong><br /> 01 客室ビジネスの特性と顧客セグメント<br /> 02 客室ビジネスの業績を評価するOCC・ADR・RevPAR<br /> 03 需要に応じて価格を変動させるレベニューマネジメント<br /> 04 レストランビジネスの特性と販売戦略<br /> 05 レストランビジネスの3つの指標 客席回転数、平均客単価、RevPASH<br /> 06 さまざまな用途に対応する一般宴会ビジネス<br /> 07 総合力やオリジナリティが求められるホテルウエディング<br /> 08 宴会ビジネスの2つの指標 宴会件数、平均客単価<br /> 09 その他の収入 Other Income<br /> COLUMN4 予算管理とフォーキャスト<br /> <strong>Chapter5 ホテル業界の業界地図(国内ホテル)</strong><br /> 01 帝国ホテル 日本を代表するシティホテル<br /> 02 ホテルオークラ 海外にも積極展開する御三家<br /> 03 ニュー・オータニ 創業者の「NEW」へのこだわり<br /> 04 西武ホールディングス 持たざる経営へのシフトを目指す<br /> 05 東急ホテルズ&リゾーツ マルチ・ブランド戦略による展開<br /> 06 藤田観光 ラグジュアリーからビジネスまで<br /> 07 パレスホテル 国内発のラグジュアリーホテル<br /> 08 ロイヤルホテル ホテルオペレーターへの転換<br /> 09 森トラスト 会員制リゾートとホテル開発<br /> 10 三井不動産グループ 宿泊主体型からラグジュアリーまで<br /> 11 ミリアルリゾートホテルズ 東京ディズニーリゾートのホテル<br /> 12 星野リゾート 軽井沢から日本全国、世界へ<br /> 13 アパホテル 逆張りの経営とキャッシュバック<br /> 14 ルートインジャパン ロードサイドの宿泊特化型ホテル<br /> 15 東横イン コストの削減による低価格の実現<br /> 16 共立メンテナンス ドーミーインとリゾートを運営<br /> COLUMN5 サービス・プロフィット・チェーンとワーク・エンゲージメント<br /> <strong>Chapter6 ホテル業界の業界地図(インターナショナル)</strong><br /> 01 世界最大のホテルチェーン マリオット・インターナショナル<br /> 02 ホテル王が創った100年企業 ヒルトン<br /> 03 デザインにこだわるホテルチェーン ハイアットホテルズ&リゾーツ<br /> 04 英国拠点のホテルチェーン IHGホテルズ&リゾーツ<br /> 05 フランス発の巨大ホテルチェーン アコーグループ<br /> 06 アジア発の最高級ホテルチェーン マンダリン・オリエンタルホテル<br /> 07 カナダ発のラグジュアリーホテル フォーシーズンズ・ホテルズ<br /> 08 アジア発のラグジュアリーブランド ペニンシュラとシャングリ・ラ<br /> 09 タイ発祥のホテルチェーン センタラとデュシット<br /> COLUMN6 外資系ラグジュアリーホテルが注目するRyokanスタイル<br /> <strong>Chapter7 ホテルの職種と求められるスキル</strong><br /> 01 待遇改善が進むホテル業界 ホテル業界で働く魅力<br /> 02 ホテルの組織と職種<br /> 03 宿泊するゲストにサービスを提供する 宿泊部門<br /> 04 食を提供するスペシャリスト 食堂部門<br /> 05 プランニングから運営まで行う 宴会部門<br /> 06 ホテルの魅力を伝えて売上につなげる セールス&マーケティング部門<br /> 07 ホテルの「縁の下の力持ち」 管理部門<br /> 08 ホテルにおけるマネジメント 現場の最高責任者・総支配人<br /> 09 ホテリエのキャリアパス サービス現場からマネジメントへ<br /> 10 人材育成とトレーニング制度 「人財」を育てるための投資<br /> COLUMN7 ホテル業界での多様な働き方<br /> <strong>Chapter8 ホテルのマーケティング戦略</strong><br /> 01 プッシュ戦略とプル戦略<br /> 02 メディアの広告枠を購入する 広告宣伝<br /> 03 広告費をかけない広報活動 パブリック・リレーションズ<br /> 04 デジタル・マーケティング SOEPにおける販売促進活動<br /> 05 レピュテーションマネジメントとSNS<br /> 06 OTA、メタサーチとの共存関係 圧倒的な知名度と集客力<br /> 07 顧客のリピートを促す仕掛け ホテルイベント企画<br /> 08 ブランドマネジメント ブランドスタンダードの遵守<br /> 09 会員特典画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,980円 |
 図解即戦力 SNS担当者の実務と知識がこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 野村総合研究所データサイエンスラボ 広瀬安彦 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>(概要)</strong><br /> <strong>※この商品は固定レイアウトで作成されており,タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また,文字列のハイライトや検索,辞書の参照,引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing ( gihyo.jp/mk/dp/ebook/2022/978-4-297-13057-2 )も合わせてご覧ください。</strong><br /> 本書は、企業や団体の公式SNSアカウント運?を任された方に向けた、基本の??書です。なぜ企業がSNSを活?するのかといった基本の知識をきちんと押さえた上で、アカウント開設前・企画段階での事前準備、運?、効果分析、炎上対策などを体系的に整理し、「企業SNSアカウントの企画・運?などの実務をどのように?い、何に注意すべきか」について解説します。各SNSにおけるアカウント作成や個別の運?ポイントなどについては、書籍の後半でSNSごとに章を分けて解説しています。</p> <p><strong>(こんな方におすすめ)</strong><br /> ・企業・団体のSNS運営を任された?、広報担当者、マーケティング担当者</p> <p><strong>(目次)</strong><br /> <strong>第1章 SNS担当者のための基礎知識</strong><br /> なぜ企業がSNSを活用するのか<br /> SNS運用のメリット1自社の認知度拡大とファン層の囲い込み<br /> SNS運用のメリット2優良顧客の育成<br /> SNS運用のメリット3ユーザーから「生の意見」を吸い上げる<br /> SNS運用のメリット4無料で広報・広告ができる<br /> SNS広告の特徴<br /> ホームページとSNSの役割の違い<br /> コンテンツマーケティングという考え方<br /> ブランドとレピュテーション<br /> レピュテーションを向上させる取り組み<br /> Facebookの特徴<br /> Twitterの特徴<br /> LINEの特徴<br /> YouTubeの特徴<br /> 覚えておきたいSNSのデメリットとリスク<br /> <strong>第2章 SNSアカウントの企画から開設まで</strong><br /> SNSアカウント開設までに決定すべき事柄とは<br /> SNS選択の基準と留意すべきポイント<br /> ビジネスアカウントと個人アカウント<br /> ターゲットの絞り込み<br /> コミュニケーション目標・コンセプトの設定<br /> KGI・KPIの設定<br /> 運用体制の構築<br /> チェック体制の構築<br /> ソーシャルメディアポリシー・ガイドラインの作成<br /> コンティンジェンシープランの準備<br /> SNSから得られる情報の取り扱い<br /> 集客方法の検討<br /> 広告の種類<br /> <strong>第3章 コンテンツ作りとアカウント運用</strong><br /> フォロワーの評価に繋がるコンテンツとは<br /> Googleの3H戦略という考え方<br /> エンゲージメント(絆)作りの重要性<br /> コンテンツ投稿の継続と効率化<br /> コンテンツのシェア<br /> KPI・KGIに基づく取り組みと投稿内容の見直し<br /> SNSごとに違う運用のポイントと注意点<br /> <strong>第4章 SNSにおける炎上の防止/対応</strong><br /> 炎上しないためのポイント<br /> 延焼させないための体制構築<br /> 観測とエスカレーション<br /> 炎上時の基本動作と現場マネジメント<br /> 炎上時のメディア対応と社内アナウンス<br /> 法的措置の検討<br /> 炎上の原因分析と改善<br /> 炎上防止のための社員教育<br /> <strong>第5章 Facebookページの運用</strong><br /> Facebookページの作成と注意点<br /> 投稿・返信の基本方針<br /> Facebookページの目的・KGI/KPI設定のポイント<br /> インサイトによる分析<br /> Instagramとのコンテンツ共有<br /> Facebook広告の作成方法<br /> <strong>第6章 Twitterアカウントの運用</strong><br /> Twitterアカウントの作成と注意点<br /> アクション(フォロー・リツイートなど)の基本方針<br /> アカウント運用の目的・KGI/KPI設定のポイント<br /> Twitterアナリティクスによる分析<br /> Twitterにおける広告とプロモーション<br /> <strong>第7章 LINE公式アカウントの運用</strong><br /> LINE公式アカウントの作成と注意点<br /> 認証済アカウントと未認証アカウント<br /> 利用する機能と方針の決定<br /> LINE公式アカウント運用の目的とポイント<br /> LINE Official Account Managerの活用<br /> LINEにおける広告とプロモーション<br /> <strong>第8章 YouTubeチャンネルの運用</strong><br /> YouTubeチャンネルの作成と注意点<br /> 好まれる動画のポイント<br /> 動画制作・アカウント運用方針の決定<br /> お手軽な動画編集ツールの紹介<br /> YouTubeアナリティクスによる分析<br /> YouTubeにおける広告</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,980円 |
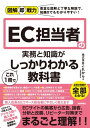 図解即戦力 EC担当者の実務と知識がこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 株式会社これから ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>(概要)</strong><br /> 集客、接客、広告出稿、サイト分析、リピーター対策…ネットショップの担当者になったら、知っておかなければ&やらなければならないことは多岐にわたります。本書は自社ECの売上アップに特化し、制作から集客支援、広告運用、CRM施策、コンサルティングまでを行う専門家集団が、未経験のひとにもわかる文章と図解でやさしく解説する「ECサイト開業・運営の入門書」です。配置転換で突然ネットショップの店長になった人、別業界からEC業界をめざしている人を対象に、サイト制作からwebマーケティングまでEC業務に必須の知識を1冊にまとめました。</p> <p><strong>(こんな方におすすめ)</strong><br /> ・事業会社でEC部門に配属された新人さん →実務未経験者にもやさしく解説しています!<br /> ・EC事業者をクライアントとする コンサル会社や広告会社に就職した新人さん →業界の専門用語もさくっと理解できます!</p> <p><strong>(目次)</strong><br /> <strong>CHAPTER 1 ECの基礎知識とEC担当者のお仕事</strong><br /> 01 そもそもECサイトとは?<br /> 02 まだまだ成長する! EC市場の動向<br /> 03 2020年代 ECはさらに進化する<br /> 04 EC担当者の基本的な販売業務<br /> 05 EC担当者が行うべき販促業務<br /> 06 サイト運営で必須のお客様対応<br /> 07 自社ECサイトとモール型ECサイトの違い<br /> 08 自社ECサイトのカートシステムは大きく3種類<br /> 09 ASP型カートシステムの選び方<br /> 10 自社ECとモール型ECの両方を運営するメリット<br /> 11 EC担当者が知っておきたいCtoCサービス<br /> 12 越境ECを行う理由と注意点<br /> <strong>CHAPTER 2 ECビジネスで知っておきたいこと</strong><br /> 01 売上を決めるのはアクセス数×購入率×平均客単価<br /> 02 サイトの強みと弱みを明らかにするSWOT分析<br /> 03 ペルソナー自社の顧客像の描き方と活用法<br /> 04 ECサイトの目標設定や評価のための指標「KPI」<br /> 05 KPI設定で発見・解決するECサイトの課題<br /> 06 販売機会を逃さない販促イベント計画の立て方<br /> 07 特定商取引法とサイトに必ず掲載すべきこと<br /> 08 ウソや誇大表現はNG! 景品表示法と薬機法<br /> 09 ECサイトで利用される決済方法<br /> 10 ECサイトの売上を伸ばすID決済<br /> 11 商品写真の撮影前に伝えたいことを考え抜くのが大切<br /> 12 商品写真で知っておきたい撮影の知識<br /> 13 自社で撮影するのに必要な機材<br /> 14 価格の決め方と平均客単価を伸ばす方法<br /> 15 在庫管理から発送までのフルフィルメント業務とは<br /> 16 販売戦略につながる配送料金の設定<br /> 17 梱包と封入物でお客様とコミュニケーション<br /> 18 EC担当者なら知っておきたい情報サイト4選<br /> <strong>CHAPTER 3 企画から開店準備までで学ぶECサイト制作の知識</strong><br /> 01 コンセプト決定からオープンまでサイト制作の流れ<br /> 02 サイト制作の精度が上がるコンセプトシートの作成<br /> 03 必要なページと階層を設計するサイトマップ<br /> 04 購入率が2倍に上がるトップページ必須の要素<br /> 05 商材や業態で異なるトップページ構成のセオリー<br /> 06 画面サイズを意識したスマホ専用サイトの構成<br /> 07 工夫するほど売上が伸びる! 商品カテゴリーページ<br /> 08 購入へ最後のひと押しをする商品詳細ページ<br /> 09 最後のダメ押しで売上を伸ばすカートページ<br /> 10 見落としがちな商品ページのつくり込み<br /> 11 ブランディングや定期購入に効くランディングページ<br /> 12 知っておきたいコーディングの知識<br /> 13 サイトの不備から配送トラブルまでテスト注文で検証<br /> 14 オープン前に行うべき運営者側のチェック項目<br /> <strong>CHAPTER 4 ECサイトの集客方法<SEO&SNS編></strong><br /> 01 ECサイトの集客方法と集客チャネル<br /> 02 検索エンジンのしくみとSEO対策<br /> 03 EC担当者が行うSEOの内部対策<タグ設定編><br /> 04 EC担当者が行うSEOの内部対策<キーワード設定編><br /> 05 SEO効果の高いコンテンツのつくり方<br /> 06 やってはいけないSEO対策<br /> 07 SNSの特徴を活かしたECサイト集客術<br /> 08 シームレスなInstagramマーケティング<br /> 09 実店舗と連動したアプリ集客<br /> <strong>CHAPTER 5 ECサイトの集客方法<ウェブ広告編></strong><br /> 01 ウェブ広告の利点と広告費の種類<br /> 02 配信ターゲットの設定と媒体・メニュー選び<br /> 03 ウェブ広告で大切なKPIの考え方<br /> 04 検索ページに表示される「リスティング広告」<br /> 05 リマーケティングが重要「ディスプレイ広告」<br /> 06 商品写真付きで表示「Googleショッピング広告」<br /> 07 商品への興味関心が高いユーザーにリーチできる「SNS広告」<br /> 08 見込み客に毎日商品を宣伝できる「インフィード広告」<br /> 09 静止画広告よりも購買率が高い「動画広告」<br /> 10 定番の集客法「アフィリエイト広告」<br /> 11 アンバサダーマーケティングとインフルエンサーマーケティングの違い<br /> 12 訴求と表現が大切! バナー広告のデザイン<br /> 13 文字の力で訴える! 広告の見出しと説明文<br /> 14 失敗しないウェブ広告の配信と運用<br /> 15 勝ちパターンを見つけるA/Bテストの実施<br /> <strong>CHAPTER 6 購入率を上げるECサイトの接客術</strong><br /> 01 価格よりも大事? ウェブ接客力の重要性<br /> 02 売上アップに効果的なカゴ落ち対策<br /> 03 レコメンドツールは購入率・客単価・リピート率を改善する優秀なスタッフ<br /> 04 訪問者を離脱させない商品検索サジェスト<br /> 05 ECサイトの利便性を高めるチャットボット<br /> 06 「お客様の声」商品レビューはサイトの強い味方<br /> 07 ショップのファンを育成するメディアEC<br /> 08 管理しやすいコンテンツ配信サイトのつくり方<br /> 09 サイトを訪れる理由になるコンテンツのつくり方<br /> <strong>CHAPTER 7 もっと売上を伸ばすためのECサイト分析と改善</strong><br /> 01 売上をゴールにおいて解析するECサイト分析<br /> 02 ECサイトの分析時に押さえておきたい指標<br /> 03 Googleアナリティクスの役割と重要性<br /> 04 GoogleアナリティクスでECサイト専用分析<br /> 05 EC分析のポイントは流入元のメディアとデバイス<br /> 06 売上改善につなげるコンバージョン率の分析<br /> 07 SEO対策の分析ツール! Google Search Console<br /> 08 客観的データで改善を提案「AI解析ツール」の活用<br /> 09 デザインの分析も! ウェブ解析に利用できるツール<br /> <strong>CHAPTER 8 ECサイト運用の王道!リピーター対策</strong><br /> 01 売上を安定的に伸ばしていくにはリピーター対策が必須<br /> 02 顧客を知ることから始まるリピート対策<br /> 03 顧客分析の王道 会員ランク分析とRFM分析<br /> 04 F2転換はスピードが命! 鉄は熱いうちに打つもの<br /> 05 メルマガ配信はタイミングが大事<br /> 06 セグメントメール配信とステップメール配信<br /> 07 圧倒的な誘導率でお客様とつながるLINE公式アカウント活用法<br /> 08 友だち獲得のコツと即ブロック防止術<br /> 09 顧客のハートを掴むには開梱時がチャンス<br /> 10 アナログ対策も忘れずに! 30代以上にはDMとカタログを<br /> 11 1年目で年商1億円も夢ではない! 単品リピート通販の世界<br /> 12 サブスクリプションモデルはリピート通販の新潮流<br /> <strong>CHAPTER 9 多店舗展開で売上アップ!ECモールへの出店</strong><br /> 01 ECモール出店のメリットと注意点<br /> 02 3大ECモールの特徴と売上アップのサイクル<br /> 03 ECモール型サイトでの販促ポイントは「目玉商品」<br /> 04 広告出稿とECモール主催のセールイベント<br />画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 2,178円 |
 図解即戦力 金融のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 伊藤亮太 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>(概要)</strong><br /> **※この商品は固定レイアウトで作成されており,タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また,文字列のハイライトや検索,辞書の参照,引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は Gihyo Disital Publishing ( gihyo.jp/mk/dp/ebook/2021/978-4-297-11741-2 )も合わせてご覧ください。****私たちの生活とは切り離せない金融。金融とは何かといった基礎からはじめ、経済・景気・金利・政策といった日々接している話題との関連性もわかりやすく解説します。銀行・証券といった代表的な金融機関の役割は何か、市場とは、株式・為替のしくみ、債券とは何かなど、知っているようで知らない疑問もやさしく理解することができます。フィンテック、仮想通貨、キャッシュレス化など、新しい金融の動きもわかります。</p> <p>(こんな方におすすめ)<br /> ・金融のしくみを基礎からやさしく理解したい方<br /> ・これから資産運用や投資のための知識を身につけたい方<br /> ・銀行や証券会社などの役割について知りたい方</p> <p>(目次)<br /> 第1章 金融の基本<br /> 01金融とはお金を融通するしくみ<br /> 02お金の定義と3つの機能<br /> 03お?の価値とは信用のこと<br /> 04経済を動かすのは「家計」「企業」「政府」の3つ<br /> 05間接金融と直接金融で経済は活性化されている<br /> 06金融市場ではさまざまな金融商品の取引が行われる<br /> 07インフレとデフレって何?<br /> 08経済を安定させているのは中央銀行<br /> 09金融商品取引法を知ろう<br /> 第2章 「市場」と「?利」<br /> 01金利とはお金の融通で発生する手数料のこと<br /> 02金利はどのようにして決められる?<br /> 03金利が変動する要因<br /> 04金融政策と金利の関係<br /> 05金融市場は長期金融市場と短期金融市場に分けられる<br /> 06株式市場とは<br /> 07債券市場とは<br /> 08外国為替市場とは<br /> 09インターバンク市場とオープン市場とは<br /> 10デリバティブ市場とは<br /> 11国債と金利は相反する値動きをする<br /> 12海外と国内の金利差は為替や債券価格を動かす<br /> 13米国中心に動く金融市場<br /> 第3章 ?融と経済<br /> 01好景気・不景気と景気循環<br /> 02マクロ経済学<br /> 03ミクロ経済学<br /> 04実物経済と金融経済<br /> 05GDPと経済の関係<br /> 06経済指標とはなにか<br /> 07景気と株価<br /> 08景気と金利<br /> 09景気と為替<br /> 10景気と物価<br /> 第4章 金融政策と規制<br /> 01中央銀行が担う3つの役割<br /> 02日本銀行のしくみ<br /> 03「公開市場操作」を中心に行われるさまざまな金融政策<br /> 04金融規制と金融規制緩和<br /> 05預金者や投資家は金融庁によって守られている<br /> 06日本の金庫番と経理を担う財務省<br /> 07金融システムを守る国際ルール「国際金融規制」<br /> 08世界の金融規制が日本の経済に与える影響<br /> 第5章 ?融機関の種類と役割<br /> 01さまざまな種類がある金融機関<br /> 02銀行の役割は信用創造<br /> 03銀行の3大業務とは<br /> 04銀行本部と支店、それぞれの役割と業務<br /> 05信託銀行の役割と業務<br /> 06信用金庫・信用組合・労働金庫・JAの役割と業務<br /> 07証券会社の役割と業務<br /> 08投資銀行の役割と業務<br /> 09保険会社の役割と業務<br /> 10ノンバンクの役割と業務<br /> 11ゆうちょ銀行の役割と業務<br /> 12異業種から参入してきた新銀行<br /> 13地方銀行の再編が進む理由<br /> 第6章 株・投資信託のしくみ<br /> 01株式とは何か<br /> 02誰でも売買できる株、できない株がある<br /> 03株式投資のしくみ<br /> 04信用取引とは<br /> 05株価の指標と企業価値<br /> 06投資信託とは何か<br /> 07投資信託のしくみ<br /> 08投資信託の種類<br /> 09不動産投資信託(REIT)と不動産投資<br /> 10信託銀行が取り扱う信託商品<br /> 11課税が優遇されるNISA<br /> 12個?型確定拠出年?(iDeCo)と企業型確定拠出年金<br /> 第7章 為替のしくみ<br /> 01基軸通貨と通貨の価値<br /> 02外国為替とは異なる通貨の交換を行うこと<br /> 03円高・円安と為替<br /> 04日銀・FRB・ECBの為替介入<br /> 05為替相場制度の種類<br /> 06外貨預?のしくみ<br /> 07FX(外国為替証拠?取引)とは<br /> 08キャリートレードとは<br /> 第8章 債券のしくみ<br /> 01債券とは何か<br /> 02債券発行の流れ<br /> 03債券の形態 利付債・割引債・仕組債<br /> 04債券の種類 ?公共債<br /> 05債券の種類 ?民間債<br /> 06債券の種類 ?外国債<br /> 07債券価格の変動要因とは<br /> 08債券の格付けは誰が決めているのか<br /> 09債券ってどこで買えるの?<br /> 第9章 高度化する金融<br /> 01株や債券から派生した商品「デリバティブ」<br /> 02将来の売買の約束を取引する「先物取引」<br /> 03買う権利と売る権利を売買する「オプション取引」<br /> 04キャッシュフローを交換する「スワップ取引」<br /> 05信用リスクを取引する「クレジット・デリバティブ」<br /> 06複数の投資信託を組み合わせて運用する「ファンドラップ」<br /> 07金融商品ではない?「仮想通貨」<br /> 08証券会社などが行う金融仲介業務「シャドーバンキング」<br /> 09クオンツ運用手法を利用した「クオンツファンド」<br /> 第10章 変わる?融の近未来<br /> 01構造不況といわれ続ける?融業界、今後どうなる?<br /> 02再編と統合で変わる?融業界の勢?地図<br /> 03金融機関の対面サービスがなくなる日も近い?<br /> 04フィンテック(FinTech)はどこまで来たか<br /> 05電子マネーとキャッシュレス決済は普及するのか<br /> 06仮想通貨は国境をなくすのか<br /> 07仮想通貨を支えるブロックチェーン技術<br /> 08クラウドファンでイングは金融構造を変えられるか**</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,650円 |
 図解即戦力 電子コミックビジネスのしくみと戦略がこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 電子コミックビジネス研究会 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は<a href="gihyo.jp/mk/dp/ebook/2023/978-4-297-15069-3">Gihyo Digital Publishing</a>も併せてご覧ください。</strong></p> <h2><strong>◆マンガを売りたい・描きたい・編集したい人必読!◆</strong></h2> <p>Amazonがサービスを開始した2012年当初、出版市場の1割にも満たなかった電子書籍市場は、今や4割を占めるまでに成長しました。電子コミック市場だけでも、2027年には現在の紙版書籍の市場を上回るようになるともいわれています。本書は、成長著しい電子コミックビジネスの現状と将来性について解説したものです。旧来の出版事業と異なり、電子コミックは再販制度に囚われることなく価格設定ができます。また、流通にコストもかからず在庫を持つこともなく、シームレスかつグローバルに展開することも可能なビジネスです。この10年で出版社発のポータルサイトだけではなく、SNSアプリ、投稿サイト、プラットフォームなど、オンラインでボーンデジタルのコミックが生まれヒットしています。スマートフォンでの読書に対応して大量に電子化された既存のコミックも、読み放題などのサブスクのサービスに拍車をかけています。韓国発の縦スクロールカラーコミックなどビジュアル表現の方法も多様になり、今後はAIによる多言語翻訳など、技術革新が期待されています。本書は電子コミックビジネスの現状が俯瞰できる1冊です。</p> <h2><strong>■こんな方におすすめ</strong></h2> <p>1電子コミックストアや出版社で働きたい人<br /> 2コミック編集者になりたい・なりたての人<br /> 3商業デビューしたい・自らマネタイズしたい漫画家<br /> 4コンテンツビジネス、IPビジネスへ進出を目論むスタートアップ企業の新規事業担当者<br /> 5市場が拡大している電子コミックについて知りたい投資家<br /> 6アプリ開発、プラットフォームを所有するIT関連会社とサプライヤー</p> <h2><strong>■目次</strong></h2> <p>CHAPTER1 電子コミックが担う出版ビジネスの夜明け<br /> CHAPTER2 どんな電子コミックサービスがあるか?<br /> CHAPTER3 電子コミックビジネスの多様な販売戦略<br /> CHAPTER4 電子コミックの制作・流通・収益のしくみ<br /> CHAPTER5 編集の現場が変わる 電子コミックの作り方<br /> CHAPTER6 縦スクロール漫画が広げたマーケット<br /> CHAPTER7 デジタル&多言語翻訳で加速するグローバル市場<br /> CHAPTER8 電子だからできる 自らビジネスするマンガ家<br /> CHAPTER9 知っておきたい電子コミックビジネスと法律</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,980円 |
 図解即戦力 介護ビジネス業界のしくみと仕事がこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 高山 善文 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>(概要)</strong><br /> <strong>※この商品は固定レイアウトで作成されており,タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また,文字列のハイライトや検索,辞書の参照,引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は Gihyo Disital Publishing ( gihyo.jp/mk/dp/ebook/2021/978-4-297-12499-1 )も合わせてご覧ください。</strong><br /> 「2025年問題」が間近に迫る介護業界。2014年度の介護サービス市場は8.6兆円の規模でしたが、2025年には18.7兆円と予測されています。介護や支援を必要とする人も17年時点で633万人と、介護保険制度が施行された2000年からの17年間で約3倍に増え、今後さらに認定者数が増加することは間違いありません。国の社会保障の方針や介護保険に対する考え方が大きな影響を受ける介護ビジネス事業者は、2〜3年に1度のペースで改正される介護保険制度について都度、対応を迫られます。この特殊な産業のビジネスモデルを理解するには、介護保険料や介護保険制度に基づく報酬のしくみを知らなければなりません。人手不足への対応策から、他業界の参入が著しい関連ビジネスまで、就活生はもちろん、新たなビジネスチャンスを探している人にも、気になる業界の最新動向がわかります。</p> <p><strong>(こんな方におすすめ)</strong><br /> ・介護スタッフや施設職員などのサービス従事者、周辺業界への参入者。</p> <p><strong>(目次)</strong><br /> <strong>Chapter1 介護業界を取り巻く現状と介護保険制度</strong><br /> 01 少子高齢化の現状と課題<br /> 02 介護保険制度の改正と地域共生社会<br /> 03 感染症や災害への対応力強化<br /> 04 地域包括ケアシステムの推進<br /> 05 自立支援・重度化防止の取組の推進<br /> 06 介護人材の確保・介護現場の革新<br /> 07 制度の安定性・持続可能性の確保<br /> 08 介護保険ビジネスは制度ビジネス<br /> 09 介護保険ビジネスの収入と将来性<br /> <strong>Chapter 2 介護ビジネスの基礎となる介護保険制度</strong><br /> 01 社会保険のひとつである「介護保険」<br /> 02 介護保険制度のしくみ<br /> 03 介護保険は保険料と税金で賄われる<br /> 04 要介護認定の流れ<br /> 05 多岐にわたる介護保険のサービス<br /> 06 ケアプランとケアマネジャー<br /> 07 サービスを利用できる限度<br /> 08 介護サービスとお金<br /> 09 国が3年ごとに決めているサービスの値段<br /> 10 介護保険制度における介護サービス事業者とは<br /> 11 地域包括支援センターとは?<br /> 12 介護現場で働くための資格と職種<br /> <strong>Chapter 3 介護保険の「居宅サービス」の基礎知識</strong><br /> 01 自立するための計画を利用者とつくる「居宅介護支援(ケアマネジメント)」<br /> 02 訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問する「訪問介護」<br /> 03 移動入浴車で訪問して入浴介助をする「訪問入浴介護」<br /> 04 在宅で医療処置が必要なときの「訪問看護」<br /> 05 リハビリ専門職が自宅で訓練する「訪問リハビリテーション」<br /> 06 医療専門職が自宅で指導する「居宅療養管理指導」<br /> 07 日帰りで日中を過ごす「通所介護」<br /> 08 日帰りでリハビリを行う「通所リハビリテーション」<br /> 09 短期間、福祉施設に宿泊する「短期入所生活介護」<br /> 10 短期間、医療系施設に宿泊する「短期入所療養介護」<br /> 11 「福祉用具貸与(レンタル)」と「特定福祉用具販売」<br /> 12 住み慣れた自宅で暮らし続けるために「住宅改修」<br /> <strong>Chapter 4 「介護保険施設」と「高齢者向け住まい」の基礎知識</strong><br /> 01 介護保険施設と運営法人<br /> 02 施設で介護サービスを受ける「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」<br /> 03 在宅復帰を目指してリハビリを行う「介護老人保健施設」<br /> 04 医療と介護が必要な高齢者のための「介護医療院」<br /> 05 養護老人ホームと軽費老人ホーム<br /> 06 種類もいろいろ「有料老人ホーム」<br /> 07 高齢者向け賃貸住宅「サービス付き高齢者向け住宅」<br /> 08 高齢者や障がい者が入りやすい「セーフティネット住宅」<br /> <strong>Chapter 5 介護保険における「地域密着型サービス」</strong><br /> 01 24時間、365日対応「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」<br /> 02 夜間の介護をサポート「夜間対応型訪問介護」<br /> 03 少人数で行うデイサービス「地域密着型通所介護」<br /> 04 認知症専門のデイサービス「認知症対応型通所介護」<br /> 05 通い、訪問、宿泊を一か所で「小規模多機能型居宅介護」<br /> 06 家庭的な雰囲気のなかで「認知症対応型共同生活介護」<br /> 07 小規模多機能プラス訪問看護「看護小規模多機能型居宅介護」<br /> 08 地域密着型の「介護老人福祉施設」と「特定施設入居者生活介護」<br /> <strong>Chapter 6 高齢者を対象としたビジネス</strong><br /> 01 高齢者がいつまでも元気に暮らすために<br /> 02 認知症でも自立して暮らすためのサービス<br /> 03 介護保険制度以外で日常を支える<br /> 04 制度の隙間を埋めるコミュニティビジネス<br /> 05 趣味や特技からビジネスへ<br /> 06 健康と食べる楽しさを提供する<br /> 07 高齢者の外出を促す整容ビジネス<br /> 08 適切な住まいを選ぶために<br /> 09 ひとり暮らしの高齢者の保証人に<br /> <strong>Chapter 7 「介護人材」に関わるビジネス</strong><br /> 01 介護職員の人材派遣・紹介ビジネス<br /> 02 外国人が介護職員として働く<br /> 03 国際協力としての外国人技能実習制度<br /> 04 介護技能を有している外国人が就労可能となった「特定技能」<br /> 05 国家資格「介護福祉士」を養成<br /> 06 スキルアップをするための教育研修<br /> 07 外国人介護職員向けビジネス<br /> <strong>Chapter 8 高齢者のための「モノ」のビジネス</strong><br /> 01 高齢者が暮らしやすい「住まい」をつくる<br /> 02 住み慣れた家で暮らし続けるために<br /> 03 自立した生活を助ける福祉用具<br /> 04 離れていても高齢者の安全を守る<br /> 05 負担の大きい排泄ケアを支援する<br /> 06 「聞こえ」の支援は認知症を防ぐ<br /> 07 「家具」が高齢者の安全を支える<br /> 08 誰もが使いやすいモノを<br /> 09 多くの人に「使いやすいモノ」を安全に安く使ってもらうために<br /> <strong>Chapter 9 介護サービス事業者を対象としたビジネス</strong><br /> 01 介護サービス事業者も経営の安定は重要課題<br /> 02 「弁護士」などの士業への相談が増加<br /> 03 ファクタリングサービスで資金繰りを支える<br /> 04 今後の介護業界再編を目指して<br /> 05 介護業界に「生産性向上」の視点を<br /> 06 「サービス」の質を第三者が評価する<br /> 07 フランチャイズで介護事業を起業する<br /> 08 介護サービス事業の理念や内容を伝える<br /> <strong>Chapter 10 介護ビジネスのリスクマネジメント</strong><br /> 01 介護事業におけるリスク<br /> 02 介護サービスにおける感染症対策<br /> 03 自然災害とBCP(事業継続計画)<br /> 04 介護職員の多くが抱える腰痛のリスク<br /> 05 利用者やその家族からのハラスメント<br /> 06 個人情報漏えいのリスク<br /> 07 利用者や家族からの苦情リスク<br /> <strong>Chapter 11 介護業界・介護ビジネスの未来</strong><br /> 01 近未来の介護サービス事業<br /> 02 全国の自治体に広がる認知症条例<br /> 03 民間介護保険と認知症保険<br /> 04 企業の介護離職を防ぐ支援ビジネスも<br /> 05 介護が必要な高齢者は約2割<br /> 06 働きたい高齢者のためのビジネス<br /> 07 注目される「リバースモーゲージ」<br /> 08 どうする? 高齢者の移動手段<br /> 09 歩いて暮らせるコンパクトシティ<br /> 10 介護現場に広がるDX<br /> 11 介護用ロボット開発の未来<br /> 12 アジア諸国に対する介護サービスの輸出</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,760円 |
 図解即戦力 金融のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書[改訂2版]【電子書籍】[ 伊藤 亮太 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は<a href="gihyo.jp/mk/dp/ebook/2023/978-4-297-13924-7">Gihyo Digital Publishing</a>も併せてご覧ください。</strong></p> <h2><strong>【金融のしくみを基礎からやさしく説いた入門書の定番!】</strong></h2> <p>新NISA制度を活用した投資、暗号資産、キャッシュレス化やCBCDなど、金融の変化の波に立ち向かうにも知識が必要です。金融とは何かといった基礎からはじめ、金融と経済、金融と政策といった日々接している話題との関連性もわかりやすく解説します。銀行・証券といった代表的な金融機関の役割は何か、さらに、市場と金利、株・為替・信託のしくみ、債券とは何かなど、知っているようで知らない疑問も明確に理解することができます。専門用語の多い世界ですので、側注で重要語をその都度解説し、知っていてあたりまえのキーワードもしっかり理解できるようになります。読み終えたときには、金融の世界が身近なものに感じられます!</p> <h2><strong>■こんな方におすすめ</strong></h2> <p>・金融のしくみを基礎からやさしく理解したい社会人、学生<br /> ・経済ニュースを読めるようになりたい方<br /> ・投資を始めたい/始めたばかりの</p> <h2><strong>■目次</strong></h2> <p><strong>第1章 金融の基本</strong><br /> 01 金融とはお金を融通するしくみ<br /> 02 お金の定義と3つの機能<br /> 03 お金の価値とは信用のこと<br /> 04 経済を動かすのは「家計」「企業」「政府」の3つ<br /> 05 間接金融と直接金融で経済は活性化されている<br /> 06 金融市場ではさまざまな金融商品の取引が行われる<br /> 07 インフレとデフレってなに?<br /> 08 経済を安定させているのは中央銀行<br /> 09 金融商品取引法を知ろう<br /> <strong>第2章 「市場」と「金利」</strong><br /> 01 金利とはお金の融通で発生する手数料のこと<br /> 02 金利はどのようにして決められる?<br /> 03 金利が変動する要因<br /> 04 金融政策と金利の関係<br /> 05 金融市場は長期金融市場と短期金融市場に分けられる<br /> 06 株式市場とは<br /> 07 債券市場とは<br /> 08 外国為替市場とは<br /> 09 インターバンク市場とオープン市場とは<br /> 10 デリバティブ市場とは<br /> 11 国債と金利は相反する値動きをする<br /> 12 海外と国内の金利差は為替や債券価格を動かす<br /> 13 米国中心に動く金融市場<br /> <strong>第3章 金融と経済</strong><br /> 01 好景気・不景気と景気循環<br /> 02 マクロ経済学<br /> 03 ミクロ経済学<br /> 04 実物経済と金融経済<br /> 05 GDPと経済の関係<br /> 06 経済指標とはなにか<br /> 07 景気と株価<br /> 08 景気と金利<br /> 09 景気と為替<br /> 10 景気と物価<br /> <strong>第4章 金融政策と規制</strong><br /> 01 中央銀行が担う3つの役割<br /> 02 日本銀行のしくみ<br /> 03 「公開市場操作」を中心に行われるさまざまな金融政策<br /> 04 金融規制と金融規制緩和<br /> 05 預金者や投資家は金融庁によって守られている<br /> 06 日本の金庫番と経理を担う財務省<br /> 07 金融システムを守る国際ルール「国際金融規制」<br /> 08 世界の金融規制が日本の経済に与える影響<br /> <strong>第5章 金融機関の種類と役割</strong><br /> 01 さまざまな種類がある金融機関<br /> 02 銀行の役割は信用創造<br /> 03 銀行の3大業務とは<br /> 04 銀行本部と支店、それぞれの役割と業務<br /> 05 信託銀行の役割と業務<br /> 06 信用金庫・信用組合・労働金庫・JAの役割と業務<br /> 07 証券会社の役割と業務<br /> 08 投資銀行の役割と業務<br /> 09 保険会社の役割と業務<br /> 10 ノンバンクの役割と業務<br /> 11 ゆうちょ銀行の役割と業務<br /> 12 異業種から参入してきた新銀行<br /> 13 地方銀行の再編が進む理由<br /> <strong>第6章 株・投資信託のしくみ</strong><br /> 01 株式とはなにか<br /> 02 誰でも売買できる株、できない株がある<br /> 03 株式投資のしくみ<br /> 04 信用取引とは<br /> 05 株価の指標と企業価値<br /> 06 投資信託とはなにか<br /> 07 投資信託のしくみ<br /> 08 投資信託の種類<br /> 09 不動産投資信託(REIT)と不動産投資<br /> 10 課税が優遇されるNISA1<br /> 11 課税が優遇されるNISA2<br /> <strong>第7章 為替のしくみ</strong><br /> 01 基軸通貨と通貨の価値<br /> 02 外国為替とは異なる通貨の交換を行うこと<br /> 03 円高・円安と為替<br /> 04 日銀・FRB・ECBの為替介入<br /> 05 為替相場制度の種類<br /> 06 外貨預?のしくみ<br /> 07 FX(外国為替証拠?取引)とは<br /> 08 キャリートレードとは<br /> <strong>第8章 債券のしくみ</strong><br /> 01 債券とはなにか<br /> 02 債券発行の流れ<br /> 03 債券の形態 利付債・割引債・仕組債<br /> 04 債券の種類1 公共債<br /> 05 債券の種類2 民間債<br /> 06 債券の種類3 外国債<br /> 07 債券価格の変動要因とは<br /> 08 債券の格付けは誰が決めているのか<br /> 09 債券ってどこで買えるの?<br /> <strong>第9章 高度化する金融</strong><br /> 01 株や債券から派生した商品「デリバティブ」<br /> 02 将来の売買の約束を取引する「先物取引」<br /> 03 買う権利と売る権利を売買する「オプション取引」<br /> 04 キャッシュフローを交換する「スワップ取引」<br /> 05 信用リスクを取引する「クレジット・デリバティブ」<br /> 06 複数の投資信託を組み合わせて運用する「ファンドラップ」<br /> 07 金融商品ではない?「暗号資産(仮想通貨)」<br /> 08 証券会社などが行う金融仲介業務「シャドーバンキング」<br /> 09 クオンツ運用手法を利用した「クオンツファンド」<br /> <strong>第10章 変わる金融の近未来</strong><br /> 01 構造不況といわれ続ける?融業界、今後どうなる?<br /> 02 再編と統合で変わる金融業界の勢力地図<br /> 03 金融機関の対面サービスがなくなる日も近い?<br /> 04 新しい個人送金のしくみ、「ことら」とは?<br /> 05 フィンテック(FinTech)はどこまで来たか<br /> 06 電子マネーとキャッシュレス決済は普及するのか<br /> 07 暗号資産は国境をなくすのか<br /> 08 暗号資産を支えるブロックチェーン技術<br /> 09 クラウドファンディングは金融構造を変えられるか</p> <h2><strong>■著者プロフィール</strong></h2> <p><strong>伊藤 亮太</strong>(いとう りょうた):1982年生まれ。岐阜県大垣市出身。2006年に慶應義塾大学大学院商学研究科経営学・会計学専攻を修了。在学中にCFPを取得する。その後、証券会社にて営業、経営企画、社長秘書、投資銀行業務に携わる。2007年11月に「スキラージャパン株式会社」を設立。2019年には金や株式などさまざまな資産運用を普及させる一般社団法人資産運用総合研究所を設立。現在、個人の資産設計を中心としたマネー・ライフプランの提案・策定・サポート等を行う傍ら、資産運用に関連するセミナー講師や講演を多数行う。著書に『図解 金融入門 基本と常識』(西東社)、『図解即戦力金融業界のしくみとビジネスがこれ一冊でしっかりわかる教科書[改訂2版]』(技術評論社)、監修に『ゼロからはじめる! お金のしくみ見るだけノート』(宝島社)など。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,760円 |
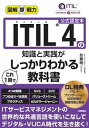 図解即戦力 ITIL? 4の知識と実践がこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ アビームコンサルティング株式会社 加藤明 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は<a href="gihyo.jp/mk/dp/ebook/2023/978-4-297-13802-8">Gihyo Digital Publishing</a>も併せてご覧ください。</strong></p> <h2><strong>【ITサービスマネジメントの世界的な共通言語を使いこなす!】</strong></h2> <p>公式認定を受けたITIL 4の入門書です。<br /> 今や世界的な「ITサービスマネジメントの共通言語」とも言えるITILは、ITIL 4にバージョンアップされたことで大きく進化を遂げています。そこで本書では、第一線で活躍するITサービスマネジメントのプロが、新しくなったITIL 4の基本と実践法を紹介。豊富な図解と具体例を交えたわかりやすい解説で、現場で生きる基礎が身につきます。<br /> さらに読者限定の特典として、ITIL 4ファンデーション認定試験の模擬問題と解説をダウンロード提供。</p> <h2><strong>■こんな方におすすめ</strong></h2> <p>ITサービスマネジメントを体系的に学びたい方はもちろんのこと、人気資格の対策をしたい方にもおすすめできる一冊です。</p> <h2><strong>■目次</strong></h2> <p> <strong>■1章 デジタル時代のITサービスマネジメント</strong><br /> 01 デジタル時代とは<br /> 02 ITサービスマネジメントとは<br /> 03 ITILとは<br /> 04 ITIL 4の書籍体系と概要<br /> 05 ITIL 4の主要コンセプト<br /> コラム 目指すはコール数ゼロのサービスデスク<br /> <strong>■2章 サービスマネジメントの主要概念</strong><br /> 06 登場人物の定義<br /> 07 価値とは<br /> 08 サービスとは<br /> 09 サービス関係とは<br /> コラム ITIL 4はITサービスだけに関係するのか?<br /> <strong>■3章 ITIL 4の主要概念1 4つの側面</strong><br /> 10 4つの側面とは<br /> 11 組織と人材<br /> 12 情報と技術<br /> 13 パートナとサプライヤ<br /> 14 バリューストリームとプロセス<br /> 15 外部要因(PESTLE)とは<br /> コラム パートナとサプライヤの契約を見直そう<br /> <strong>■4章 ITIL 4の主要概念2 SVS</strong><br /> 16 サービスバリュー・システム(SVS)とは<br /> 17 従うべき原則とは<br /> 18 価値に着目する(7つの従うべき原則1)<br /> 19 現状からはじめる(7つの従うべき原則2)<br /> 20 フィードバックをもとに反復して進化する(7つの従うべき原則3)<br /> 21 協働し、可視性を高める(7つの従うべき原則4)<br /> 22 包括的に考え、取り組む(7つの従うべき原則5)<br /> 23 シンプルにし、実践的にする(7つの従うべき原則6)<br /> 24 最適化し、自動化する(7つの従うべき原則7)<br /> 25 ガバナンスとは<br /> 26 サービスバリュー・チェーン(SVC)とは<br /> 27 プラクティスとは<br /> 28 継続的改善とは<br /> コラム 役割分担を整理するITサービス・オペレーティングモデル<br /> <strong>■5章 バリューストリーム ユーザサポート業務</strong><br /> 29 バリューストリームの活用(VSM)<br /> 30 ユーザサポート業務とは<br /> 31 サービスデスク<br /> 32 サービスカタログ管理<br /> 33 インシデント管理<br /> 34 問題管理<br /> 35 ナレッジ管理<br /> 36 サービスレベル管理<br /> 37 モニタリングおよびイベント管理<br /> 38 継続的改善<br /> コラム ナレッジを可視化し、業務継続性を保証する<br /> <strong>■6章 バリューストリーム 新サービス導入</strong><br /> 39 新サービス導入とは<br /> 40 事業分析<br /> 41 サービスデザイン<br /> 42 ソフトウェア開発および管理<br /> 43 インフラストラクチャおよびプラットフォーム管理<br /> 44 変更実現<br /> 45 サービスの妥当性確認およびテスト<br /> 46 リリース管理<br /> 47 展開管理<br /> 48 サービス構成管理<br /> コラム CI間の関係性を「見える化」 サービス構成モデルとは<br /> <strong>■7章 カスタマー・ジャーニー</strong><br /> 49 カスタマー・ジャーニーとは<br /> 50 探求<br /> 51 エンゲージ<br /> 52 提案<br /> 53 合意<br /> 54 オンボーディング<br /> 55 共創<br /> 56 実現<br /> コラム 利害関係者の価値についても考える<br /> <strong>■8章 ITILに関連するフレームワーク</strong><br /> 57 アジャイル<br /> 58 DevOps<br /> 59 SIAM</p> <h2><strong>■著者プロフィール</strong></h2> <p><strong>加藤明</strong>:アビームコンサルティング株式会社 オペレーショナルエクセレンスビジネスユニット シニアマネジャー。組織変革を実現するためのソーシング戦略立案、ITサービスマネジメントを軸としたマルチベンダー管理、IT運用保守の継続的改善、組織のチェンジマネジメント等、幅広いコンサルティング業務に従事。主な保有資格はITILマスター、ITILマネージングプロフェッショナル、ITILストラテジックリーダー、ITILプラクティスマネージャー、VeriSMプロフェッショナル、EXIN SIAMプロフェッショナルなど。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 2,530円 |
 図解即戦力 医薬品業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書[改訂2版]【電子書籍】[ 松宮 和成 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は<a href="gihyo.jp/mk/dp/ebook/2023/978-4-297-14078-6">Gihyo Digital Publishing</a>も併せてご覧ください。</strong></p> <h2><strong>【新たな創薬手法や医薬品不足の背景が手に取るようにわかる!】</strong></h2> <p>1剤で5兆円超…ファイザー社が創薬した新型コロナワクチン「コミナティ」の2022年の売上です。当たれば兆を超える巨大な利益を生み出す一方で、新薬の創出は1剤1千億円の費用と10年以上の研究開発期間がかかる、ハイリスク・ハイリターン事業です。本書では資本力のある世界のメガファーマとしのぎを削る日本の製薬会社やジェネリック医薬品メーカーの動静を、最新の情報を交えて解説します。また、患者に身近な存在である調剤薬局やドラッグストアなどの医薬品販売業も、国の制度や報酬が経営に大きな影響を与えることもあり、複雑で理解しにくいビジネスですが、本書を読めばしくみと最新動向がわかります。MSLやMR、PM、MSなど専門職の業務内容や薬剤師の仕事など、業界で働く人のキャリアについても学べます。</p> <h2><strong>■こんな方におすすめ</strong></h2> <p>・MRやMSなど製薬メーカーや薬品卸業に転職を検討している人<br /> ・薬剤師などの調剤薬局やドラッグストアに勤めている方<br /> ・新薬開発などに興味のある投資家<br /> ・製剤薬局に進出を考えている周辺事業の経営者、取引・協業関係者</p> <h2><strong>■目次</strong></h2> <p><strong>Chapter 1 医薬品業界の現状</strong><br /> 01 拡大し続ける200兆円市場<br /> 02 世界3位も国内市場は伸び止まり<br /> 03 研究開発型のハイリスク・ハイリターン事業<br /> 04 ワクチン1剤で5兆円の売上急拡大とその後のマネジメントの難しさ<br /> 05 空前の医薬品不足は何故起きた<br /> 06 求められる新たな成長戦略<br /> 07 医薬品市場を席捲するバイオ医薬品<br /> 08 世界規模で進む業界再編<br /> 09 後発医薬品への対応が急務の先発医薬品メーカー<br /> 10 異例となる早期のワクチン開発 医薬品業界へのインパクト<br /> 11 ワクチン・治療薬の開発 日本の製薬会社の出遅れの背景<br /> 12 国内医薬品メーカーへの医療費抑制政策の影響<br /> 13 生き残りをかけて海外市場へ進出<br /> <strong>Chapter 2 国内外の大手製薬会社の歴史と動向</strong><br /> 01 製薬会社として初の1,000億ドル超え ファイザーの強さと製薬事業の難しさ<br /> 02 治療薬と診断薬で個別化医療を開拓 ロシュの躍進<br /> 03 新型コロナワクチンで存在感 創薬ベンチャーの実力<br /> 04 医療用医薬品と一般用医薬品を扱う国内メーカー<br /> 05 欧州大手製薬会社を買収 武田薬品工業の戦略<br /> 06 多彩なモダリティ技術による研究開発力で日本発の創薬に注力する第一三共<br /> 07 1剤で市場を変える新薬の開発力 大塚ホールディングスと小野薬品工業<br /> 08 外資傘下でも独自経営を維持 中外製薬の戦略<br /> 09 海外企業に対抗する営業網を強化するアステラス製薬の戦略<br /> 10 認知症の治療から生活まで支えるプラットフォーム エーザイの戦略<br /> 11 漢方薬メーカーと眼科薬メーカー<br /> 12 後発医薬品(ジェネリック)メーカー<br /> <strong>Chapter 3 医薬品業界の組織と仕事</strong><br /> 01 医薬品にかかわるさまざまなプレイヤー<br /> 02 製薬会社の基本的な組織体制<br /> 03 研究開発部門の仕事と創薬ベンチャーの活用<br /> 04 医薬品の適正使用の情報を伝えるスペシャリストのMR<br /> 05 製薬会社での最初の仕事はMRからが原則<br /> 06 MRに求められる専門性と地域医療への貢献<br /> 07 プロダクトマネージャー(PM)の仕事<br /> 08 メディカル・サイエンス・リエゾン(MSL)の仕事<br /> 09 学術情報部門の仕事<br /> 10 業界ルールから国のガイドラインへ<br /> 11 医薬品の流通を支える医薬品卸業<br /> 12 医薬品卸業の販売担当者(MS)の仕事<br /> <strong>Chapter 4 医薬品業界の法律と規制</strong><br /> 01 開発、製造、流通、使用のすべてのプロセスに規制あり<br /> 02 薬事行政の中核省庁である厚生労働省<br /> 03 医薬品ビジネスの根拠法である薬機法<br /> 04 厳しい基準をクリアして医薬品の有効性と安全性を確保<br /> 05 医薬品発売後の情報収集と報告の義務<br /> 06 グローバル化の進展に応じた国際標準化の推進<br /> 07 薬害を防ぐための安全性情報の収集・提供システム<br /> 08 薬害の被害者を救済する医薬品副作用被害救済制度<br /> 09 厚生労働省が原案を作成して検討が進められる薬価<br /> 10 優先審査・優先相談により新薬を迅速に市場投入<br /> 11 国際競争力向上へ 医薬品産業の支援策<br /> <strong>Chapter 5 新薬開発の流れ</strong><br /> 01 医薬品承認・販売に至る長く険しい道<br /> 02 発見、生成、スクリーニングにより薬剤としての可能性を探求<br /> 03 臨床試験の前に安全性を確認する 細胞や動物に対する検査<br /> 04 新薬開発の最終段階であるヒトを対象とした試験<br /> 05 有効性や安全性の審査と薬価決定を経て販売開始へ<br /> 06 大規模治験の大きな壁があるワクチン開発<br /> 07 治験業務をサポートする専門事業者も活躍<br /> 08 開発費や開発期間を抑えられるジェネリック医薬品(後発医薬品)<br /> 09 医薬品にかかわる4つの特許<br /> 10 医療用アプリの承認のガイドラインを新設<br /> 11 医療用アプリによる治療法の変革<br /> <strong>Chapter 6 医薬品の処方と適正使用</strong><br /> 01 治療薬選択の基本概念である科学的根拠に基づく医療(EBM)<br /> 02 効果に影響する医薬品のさまざまな剤形<br /> 03 効果と副作用のバランスによる医薬品の選択<br /> 04 医師が処方する“薬”と“市販薬”の違い<br /> 05 薬剤師の専門性と調剤業務の流れ<br /> 06 医薬品の相互作用の確認と対応<br /> 07 医薬品を適切に飲んでもらうための薬剤師による服薬指導<br /> 08 薬剤師による在宅患者への訪問支援<br /> 09 オンライン診療・服薬指導で市場拡大を目指す<br /> 10 健康を広くサポートする「かかりつけ」の機能<br /> <strong>Chapter 7 調剤薬局とドラッグストアの行く末</strong><br /> 01 保険薬局、調剤薬局、ドラッグストアの違い<br /> 02 医薬分業の推進で6万か所にのぼる薬局数<br /> 03 調剤報酬の薬剤料と技術料<br /> 04 セルフメディケーションを支援<br /> 05 病院前に立ち並ぶ薬局の損益率の低下<br /> 06 対物業務から対人業務へ 調剤薬局が果たす役割<br /> 07 薬局を巡る不正事件の背景<br /> 08 ドラッグストアチェーンと中小事業者の事業環境<br /> 09 受診控えも単価増により収益減をカバー 調剤頼みの経営には限界も<br /> 10 医薬品を軸とした地域の健康ステーションに<br /> <strong>Chapter 8 ビジネスの前提となる社会保障システム</strong><br /> 01 社会保障制度で賄われる医療費<br /> 02 医療費全体の1割にとどまる自己負担分の割合<br /> 03 給付と負担のバランスをとる医療費抑制政策<br /> 04 マイナス改定が続くなかでも薬剤費は約1.5倍の伸び率<br /> 05 市場実勢価格に合わせて毎年引き下げられる薬価制度<br /> 06 薬価設定の背景と適切な薬価の追求<br /> 07 飲み残しや多剤併用をなくし患者の服用を適正化<br /> 08 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の利用の推進<br /> <strong>Chapter 9 革新的新薬開発に向けてのトレンド</strong><br /> 01 ゲノム創薬や個別化医療へ向かう医薬品開発の潮流<br /> 02 アンメット・メディカル・ニーズ<br /> 03 分子標的薬と正確に患部に届ける手法「DDS」<br /> 04 免疫チェックポイント阻害剤<br /> 05 認知症治療薬開発の難しさ<br /> 06 ドラッグ・リポジショニン画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,760円 |
 図解即戦力 アジャイル開発の基礎知識と導入方法がこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 増田智明 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は<a href="gihyo.jp/mk/dp/ebook/2023/978-4-297-13900-1">Gihyo Digital Publishing</a>も併せてご覧ください。</strong></p> <h2><strong>【アジャイル開発手法の基礎と導入のポイントを解説!】</strong></h2> <p>DXが推し進められ、ビジネスやサービスを取り巻く環境やニーズの変化に機敏に対応することが求められる中、アジャイル開発の手法をプロジェクトに取り込むことのメリットがあらためて注目されるようになりました。これまで長い期間をかけて、スクラム開発、XP、チケット駆動といった手法の実践的なノウハウが培われてきましたが、新たに取り組み始めた開発プロジェクトの中には、その場しのぎの導入となってしまっているケースも多いように見受けられます。そこで本書では、「現在のプロジェクトに対して、いかに上手くアジャイル開発の要素を取り込むか」に焦点を当て、実際の開発プロジェクトで実践するための手順や効果的な活用法など、アジャイル開発の基礎と導入時のポイントを図解でわかりやすく解説します。</p> <h2><strong>■目次</strong></h2> <p><strong>■Chapter 1 アジャイルソフトウェア開発宣言</strong><br /> Section 01 アジャイルの定義<br /> Section 02 カウボーイプログラミングとの違い<br /> Section 03 ウォーターフォールとの違い<br /> <strong>■Chapter 2 スクラムとXP</strong><br /> Section 04 スクラムのチーム・価値観<br /> Section 05 期限の決定<br /> Section 06 バックログの作成・顧客との調節<br /> Section 07 単体テストの自動化<br /> Section 08 ペアプログラミング<br /> Section 09 継続的なコードの改善<br /> Section 10 コードの共有化<br /> <strong>■Chapter 3 チケット駆動の基礎</strong><br /> Section 11 チケットの抽出<br /> Section 12 作業するチケットの決定<br /> Section 13 終わったタスクと終わらないタスク<br /> Section 14 追加されるタスクの調節<br /> <strong>■Chapter 4 バックログとチケットの導入</strong><br /> Section 15 バックログと優先度<br /> Section 16 WBS分割の応用<br /> Section 17 PERT図・ガントチャートの応用<br /> Section 18 増えるタスクとスケジューリング<br /> Section 19 EVMを使ったプロジェクト完了時期の予測<br /> <strong>■Chapter 5 自動テストの導入</strong><br /> Section 20 回帰テストが可能な環境<br /> Section 21 モックアップ(モック)の作成<br /> Section 22 再現テストの環境構築<br /> Section 23 コード改修とテストコード<br /> Section 24 テストコードの保守性<br /> <strong>■Chapter 6 コミュニケーションと振り返り</strong><br /> Section 25 スタンドアップミーティング<br /> Section 26 同じ時間に集まることができない場合<br /> Section 27 リモート作業への応用<br /> Section 28 ホワイトボードの活用<br /> Section 29 やらないことリストと振り返り<br /> <strong>■Chapter 7 期日とスケジューリング</strong><br /> Section 30 時間の有効活用<br /> Section 31 タイムボックスの活用<br /> Section 32 マイルストーンの設定<br /> Section 33 マイルストーンの移動・削除<br /> Section 34 学生症候群の活用<br /> <strong>■Chapter 8 ボトルネック</strong><br /> Section 35 ボトルネックの解消<br /> Section 36 リソースを追加する場所<br /> Section 37 いつまでリソースを使うか<br /> Section 38 省力化より無人化へ<br /> Section 39 PDCAによるプロセス改善<br /> <strong>■Chapter 9 ナレッジマネジメント</strong><br /> Section 40 ナレッジマネジメントとは<br /> Section 41 刺身システムによる知識の共有<br /> Section 42 SECIモデルによる知識の循環<br /> Section 43 守破離による基本から応用そして脱却へ<br /> Section 44 知識を貯めるシステム<br /> <strong>■Chapter 10 継続的な開発・学習・成長</strong><br /> Section 45 保守・運用まで考える<br /> Section 46 継続可能なソフトウェア開発<br /> Section 47 高品質がもたらす「ゆとり」<br /> Section 48 プロジェクトの目標・個人の目標<br /> Section 49 エンジニアは週末をどう過ごすべきか</p> <h2><strong>■著者プロフィール</strong></h2> <p><strong>増田智明</strong>:Moonmile Solutions代表。株式会社セックを退職ののち現在はフリーランスに至る。主な活動はプログラマーと執筆業。他にも、保守、新人教育、技術顧問などなど。アジャイル開発、計画駆動、TOC/CCPM、建築、料理をふまえて、開発プロセスを俯瞰しつつ、ソフトウェア開発に適したスタイルを模索中。著書に『図解入門 よくわかる最新システム開発者のための仕様書の基本と仕組み』『成功するチームの作り方 オーケストラに学ぶプロジェクトマネジメント』(ともに秀和システム)。他にもプログラミング言語の入門書を多数。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 2,200円 |
 図解即戦力 SAP S/4HANAの導入と運用がこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 山之内謙太郎 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は<a href="gihyo.jp/mk/dp/ebook/2023/978-4-297-14507-1">Gihyo Digital Publishing</a>も併せてご覧ください。</strong></p> <h2><strong>◆SAP S/4HANAの概要がよくわかる◆</strong></h2> <p>企業における「会計」「人事」「生産」「物流」「販売」などこれまで個別に行われていた管理処理を統合し、それぞれのデータを効率よく運用していくためにERPを導入している企業が多くなっています。そんなERP市場の中で圧倒的なシェアを獲得しているのがSAP社の「R/3」になります。しかし長年使われてきた「R/3」ですが2027年にサポート終了を迎え,今後は「S/4HANA」という別のアーキテクチャになります。本書は最新のSAPのERPパッケージの全体像を図を使ってわかりやすく解説します。</p> <h2><strong>■目次</strong></h2> <p><strong>●第1章 SAPの基礎知識</strong><br /> 01 SAPとは<br /> 02 ERPとは<br /> 03 ERP製品の市場動向(グローバル・国内)<br /> 04 SAPユーザーを悩ます2027年問題<br /> 05 SAPが推進するDX戦略<br /> <strong>●第2章 「S/4HANA」を理解する</strong><br /> 06 「S/4HANA」とは<br /> 07 「S/4HANA」の特徴<br /> 08 「S/4HANA」のアーキテクチャ<br /> 09 圧倒的な高速性を持つHANAデータベース<br /> 10 新しい直感的なユーザーインターフェース「SAP Fiori」<br /> 11 SAP Business Technology Platform<br /> 12 会社間ビジネスプロセスをデジタル化する 「SAP Business Network」<br /> 13 SAPシステムの全体像<br /> 14 SAPで利用される主要マスタ<br /> <strong>●第3章 「モノ」を管理するロジスティクス(全体像)</strong><br /> 15 ロジスティクスとは<br /> 16 ロジスティクス領域の全体構成<br /> <strong>●第4章 調達ロジスティクス</strong><br /> 17 在庫/購買管理モジュール(MMモジュール)<br /> 18 購買管理機能<br /> 19 在庫管理機能<br /> <strong>●第5章 生産ロジスティクス</strong><br /> 20 生産計画/管理モジュール(PPモジュール)<br /> 21 品質管理(QMモジュール)<br /> <strong>●第6章 販売ロジスティクス</strong><br /> 22 販売管理(SDモジュール)<br /> 23 物流管理(LEモジュール)<br /> <strong>●第7章 「カネ」を管理する会計管理</strong><br /> 24 会計領域の全体構成<br /> 25 財務会計(FIモジュール)<br /> 26 管理会計(COモジュール)<br /> 27 統合明細テーブル「ユニバーサルジャーナル」<br /> <strong>●第8章 「ヒト」を管理する人事管理</strong><br /> 28 人事管理(HCMモジュール)<br /> 29 組織管理(OMモジュール)<br /> 30 人材管理(PAモジュール)<br /> 31 勤怠管理(PTモジュール)<br /> 32 給与管理(PYモジュール)<br /> <strong>●第9章 SAP導入ステップ</strong><br /> 33 SAP導入フロー<br /> 34 要件定義フェーズ<br /> 35 設計フェーズ<br /> 36 実装フェーズ<br /> 37 テストフェーズ<br /> 38 移行フェーズ<br /> 39 運用保守フェーズ<br /> 40 アジャイル思考の「SAP Activate方法論」<br /> <strong>●第10章 その他のソリューション 「SAP S/4HANA LoB Solutions」</strong><br /> 41 業種別ソリューションIndustry Cloud<br /> 42 顧客管理の「SAP Customer Experience」<br /> 43 分析ソリューションのSAP Analytics Cloud<br /> 44 人材管理の「SAP SuccessFactors」<br /> 45 出張経費管理の「SAP CONCUR」<br /> 46 間接材購買管理の「SAP Ariba」<br /> 47 外部人材管理のSAP Fieldglass<br /> 48 中堅企業向けの「SAP Business ByDesign」<br /> 49 中小企業向けの「SAP Business One」</p> <h2><strong>■著者プロフィール</strong></h2> <p><strong>山之内謙太郎</strong>:ITコンサルタント(中小企業診断士・ITコーディネータ)。1973年神奈川県生まれ。日本大学商学部卒業。会計コンサルティング会社や株式会社ベンチャー・リンク、アビームコンサルティング株式会社での勤務を経て、フリーランスとして独立。その後、ロジスト株式会社を設立。SAPコンサルタントとして15年以上のキャリアを持ち、エネルギー業界、広告業界、製造業界など、さまざまな大手企業でSAP導入プロジェクトに携わり、その経験を活かし、プロジェクトマネジメントやビジネスプロセスの最適化、業務改革の分野でコンサルタント業務を行う。現在はロジスト株式会社の代表として、企業の規模を問わず、ITを活用した仕組みづくりを支援することをミッションとし、DX(デジタルトランスフォーメーション)を通じて、日本企業の競争力向上に取り組んでいる。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 2,640円 |
 図解即戦力 住宅メーカーのしくみとビジネスがこれ1 冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ あずた ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>(概要)</strong><br /> **※この商品は固定レイアウトで作成されており,タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また,文字列のハイライトや検索,辞書の参照,引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は Gihyo Disital Publishing ( gihyo.jp/mk/dp/ebook/2021/978-4-297-12075-7 )も合わせてご覧ください。****住宅建築・販売は、購入後の設備の購入などの金額も大きく、波及効果が高い業界です。そのため、政府は住宅ローン減税などで住宅着工を促進しています。本書は、住宅を建設する、住宅メーカーの会社組織からそのビジネスモデル、将来性まで、隅々まで解説した書籍です。また、住宅がどうやって作られていくかもわかり、注文住宅を購入しようと思っている方にも最適な内容になっています。</p> <p>(こんな方におすすめ)<br /> ・住宅メーカーに就職・転職を考えている学生・社会人。注文住宅を購入したい人</p> <p>(目次)<br /> Chapter1 住宅業界の最新動向<br /> 01 住宅は10 年で急速な進化を遂げている<br /> 02 住宅メーカーの努力によって超省エネ時代が到来<br /> 03 住宅業界の最大の課題は職人不足にある<br /> 04 扱う商品によって業績が大きく変わる<br /> 05 住宅業界はすべての産業に影響を及ぼす<br /> 06 少子高齢化による空き家問題は中古住宅の活用で解決する<br /> 07 ユーザーニーズの変化に対応し生活しやすい環境を作る<br /> 08 頻発する災害や健康被害に対応しよりよい生活を提供する<br /> 09 バリアフリー化や介護対策にビジネスチャンスがある<br /> Chapter2 業界の基本と構成する人たちの役割<br /> 01 住宅業界の構造を把握する<br /> 02 大手8 社の住宅メーカーを比較し特徴を知る<br /> 03 多岐にわたる業界の職種と規模を知る<br /> 04 住宅業界の多種多様な資格を知る<br /> 05 2 つの販売方法とターゲットの違いを知る<br /> 06 住宅の構造や骨組みの種類と特徴を把握する<br /> 07 古くからある地元工務店の現状<br /> 08 フランチャイズ化とM & A が進む背景を知る<br /> 09 戸建てを建てる住宅メーカーとマンションを建てるゼネコン<br /> 10 土地や建物の売買における不動産会社の働き<br /> 11 ニーズの変化によって業績を上げているリフォーム会社<br /> 12 設計事務所の仕事と業界内でのネットワークを知る<br /> Chapter3 住宅業界の利益構造<br /> 01 建売住宅を一気に作るパワービルダー<br /> 02 住宅メーカーの利益構造を把握する<br /> 03 工務店が利益を得るしくみと大規模な住宅メーカーとの違い<br /> 04 リフォーム会社の利益構造とリフォーム専門業者の特徴<br /> 05 リフォーム売上の上位は住宅メーカーが独占する<br /> 06 不動産会社が利益を上げるしくみ<br /> 07 中古住宅の販売による収益<br /> 08 モデルハウスが並ぶ住宅展示場公園のしくみ<br /> 09 住宅を構成する部材・パーツは多種多様<br /> 10 デザイン性や機能性で変わる建材・設備の値段<br /> 11 総コストに占める施工費・管理費の割合<br /> Chapter4 住宅メーカーの組織構造<br /> 01 住宅メーカーはどんな仕事に分かれている?<br /> 02 自社のビジョンを具現化する経営管理部門<br /> 03 研究開発をくり返す商品開発部門<br /> 04 法令を遵守した間取りを作成する設計部門<br /> 05 低コスト化を目指す資材調達部門<br /> 06 図面や仕様書から材料の数量や原価を算出する積算部門<br /> 07 もっとも多くの人員が配置され顧客のサポートを行う営業部門<br /> 08 企業の成長に関わり品質の鍵を握るアフター部門<br /> 09 注文住宅の引き渡しまでには部門間での連携が重要<br /> 10 仕様打ち合わせにおけるインテリアコーディネーターの仕事<br /> 11 施工現場での住宅メーカー社員の仕事<br /> 12 引き渡し現場での住宅メーカー社員の仕事<br /> 13 リフォーム会社・部門の仕事内容<br /> 14 住宅メーカー社員に求められる人材と能力<br /> 15 住宅メーカー社員の2 種類のキャリアパス<br /> Chapter5 主な設備・部材メーカー<br /> 01 強いつながりを持つ住宅メーカーと設備メーカー<br /> 02 住宅業界全体を支える設備・建材メーカーの分類<br /> 03 トイレやバスルームなどの主な水回りメーカー<br /> 04 顧客ニーズを把握して強みを生かすキッチンメーカー<br /> 05 給湯器・ガスコンロ・IH の主なメーカー<br /> 06 サッシ・建具・床材の主なメーカー<br /> 07 断熱性能や価格、独自性が重要な断熱材の主なメーカー<br /> 08 耐久性や軽さが重要な屋根や外壁材の主なメーカー<br /> 09 価格とデザイン性が重視される照明器具の主なメーカー<br /> 10 室内の温度や湿度を一定に保つ換気、冷暖房の主なメーカー<br /> 11 価格と耐久性、安全性が重要なクロスの主なメーカー<br /> 12 カーテンや畳などそのほかのインテリアの主なメーカー<br /> Chapter6 着工現場で行われる工事内容<br /> 01 責任の所在を明らかにした住宅メーカーの一貫施工<br /> 02 多くの住宅メーカーが施工を外注している<br /> 03 住宅建設の施工にかかる完成までのステップ<br /> 04 解体工事の内容と必要となる手続きや工具<br /> 05 基礎工事の役割と工事内容や近年の傾向<br /> 06 大工工事の工程や内容と職人たちの技術<br /> 07 足場組立工事の重要性や守るべき規定<br /> 08 建具やサッシの設置にかかる工事の内容<br /> 09 屋根工事の内容と屋根の種類や構造<br /> 10 外壁工事の内容と外壁の種類や構造<br /> 11 連帯が不可欠な設備工事の内容と職人たちの技術<br /> 12 専門の電気業者が行う電気工事の手順や内容<br /> 13 専門の水道業者が行う水道工事の内容と流れ<br /> 14 安全に暮らせる住宅に必要な外構工事の内容と流れ<br /> 15 建物内部の最終段階であるクロス貼り工事の内容と流れ<br /> 16 行政や施主による住宅の検査と主なチェック項目<br /> Chapter7 住宅業界各社の生き残り戦略<br /> 01 海外から遅れている日本住宅の大きな問題点<br /> 02 住宅メーカーの差別化戦略<br /> 03 住宅メーカーのサービス・販売努力<br /> 04 銀行も努力している住宅ローン競争<br /> 05 住宅業界の生き残りをかけた商品の開発と戦略<br /> 06 建売、注文住宅の間に位置する企画提案型住宅<br /> 07 IT を取り込む住宅メーカー<br /> Chapter8 住宅業界にまつわる規則・法律・税制<br /> 01 経済波及効果を重視した政府の方針<br /> 02 国民の生命・健康・財産保護の最低基準を示す建築基準法<br /> 03 大きな地震が発生するたび変化してきた耐震基準<br /> 04 快適な住環境を守る建築基準法の用途地域<br /> 05 建てられる家の大きさを決める建ぺい率と容積率<br /> 06 住宅の仕様の指針である住生活基本法<br /> 07 消費者保護を図る住宅瑕疵担保履行法<br /> 08 同じ住宅に長く住むための長期優良住宅の認定制度<br /> 09 住宅品質確保促進法によって10 年保証されている<br /> 10 省エネ基準の義務化が進む<br /> 11 国土交通省の告示による安心R住宅制度<br /> 12 住宅ローン減税による促進<br /> Chapter9 住宅業界の未来<br /> 01 欠陥住宅問題と悪質リフォーム業者への対応<br /> 02 健康・介護を考慮した住宅設計<br /> 03 違法建築問題と公共団体のチェック機能<br /> 04 3D プリンター住宅と建設ロボットの介入<br /> 05 未来の住宅スマートホームの展望<br /> 06 電気の自給自足ができる家ZEH の浸透<br /> 07 災害に耐えるレジリエンス住宅<br /> 08 時代に合わせた空き家問題への対策<br /> 09 成長を続ける中古住宅市場の行方**</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,760円 |
 図解即戦力 商社のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 [改訂2版]【電子書籍】[ 治良博史 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は<a href="gihyo.jp/mk/dp/ebook/2023/978-4-297-14985-7">Gihyo Digital Publishing</a>も併せてご覧ください。</strong></p> <h2><strong>◆この1冊で商社のすべてを理解できます!◆</strong></h2> <p>大学生の就職希望先として今も昔も根強い人気を誇るのが商社です。商社と聞くと、まず商取引を仲介する会社というイメージを持つかもしれません。しかし現在の商社はそれだけに限らず、あらゆる分野においてモノとカネを投入して儲けを生み出す投資会社という側面がより濃くなっています。本書では、商社業界の歴史や取り巻く状況から、商社マンの仕事や待遇、商社が取り組む新ビジネスまで、現在の商社の姿を理解するために必要な知識をわかりやすく解説しています。</p> <h2><strong>■こんな方におすすめ</strong></h2> <p>・総合商社への就職を目指す学生、転職を目指す社会人</p> <h2><strong>■目次</strong></h2> <p>第1章 商社業界の最新動向<br /> 第2章 商社の変遷<br /> 第3章 日本の7大総合商社<br /> 第4章 分野に特化した専門商社<br /> 第5章 商社の組織構造<br /> 第6章 商社マンの採用・待遇・キャリアパス<br /> 第7章 商社の利益を生み出す8つの機能<br /> 第8章 商社が展開するビジネスモデル事業例<br /> 第9章 商社が手掛ける新ビジネス<br /> 第10章 商社業界の行方</p> <h2><strong>■著者プロフィール</strong></h2> <p><strong>治良 博史</strong>(はるなが ひろし):1953年生まれ。大阪府出身。1976年に一橋大学社会学部卒業後、住友商事に勤務。運輸保険、産業機械の輸出業務、情報電機システム事業、ネットワークシステム事業、映像メディア事業などさまざまな分野の業務に従事し、2004年以降は情報電機システム部長、ネットワークシステム部長、映像メディア事業部長などを歴任。2010年からは海外事業推進センター長、2015年からは一般社団法人・全国携帯電話販売代理店協会の理事・事務局長を務める。2007年以降は一橋大学で如水会寄付講座「商社ゼミ」講師を務め、2016〜2023年は同大学大学院経営管理研究科の非常勤講師として後進の育成に努めてきた。現在はフリー。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,760円 |
 図解即戦力 モバイルゲーム開発がこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 永田峰弘 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>(概要)</strong><br /> **※この商品は固定レイアウトで作成されており,タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また,文字列のハイライトや検索,辞書の参照,引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は Gihyo Disital Publishing ( gihyo.jp/mk/dp/ebook/2021/978-4-297-12085-6 )も合わせてご覧ください。****スマートフォンの普及に伴いモバイルゲーム市場の爆発的な普及により,モバイルゲーム開発に関心を持つ人が増えてきました。本書は1つのモバイルゲームがどのような工程で開発され運用されていくのかを実際の開発現場を踏まえ図解でわかりやすく解説します。</p> <p>(こんな方におすすめ)<br /> ・モバイルゲーム業界に関わるエンジニア<br /> ・モバイルゲーム開発に興味がある人</p> <p>(目次)<br /> 1章 モバイルゲーム開発の基礎知識<br /> 01モバイルゲームの開発とは<br /> 02モバイルゲーム開発に必要な役割<br /> 03モバイルゲーム開発のステップ<br /> 04モバイルゲーム開発におけるチーム運用<br /> 05モバイルゲーム開発の技術要素<br /> 06モバイルゲーム開発の手法<br /> 2章 プロジェクト開始<br /> 07プロジェクトの目的<br /> 08企画の検討<br /> 09コンセプトとUX(体験)イメージの設定<br /> 10企画書の作成<br /> 11プレゼンからプロジェクト発足<br /> 12予算とマイルストンの策定<br /> 13プロジェクトメンバーの確保<br /> 14マネタイズ<br /> 3章 プロトタイプ開発<br /> 15プロトタイプ版の目標設定<br /> 16仕様書の作成<br /> 17プロトタイプの技術検証<br /> 18アートとサウンドのイメージ検討<br /> 19テストプレイとスクラップ&ビルド<br /> 4章 アルファ版開発<br /> 20アルファ版とベータ版<br /> 21プレイサイクルの設計と仕様書の作成<br /> 22アルファ版の技術検証<br /> 23アートのディレクション<br /> 24UIの設計<br /> 25演出とエフェクトのデザイン<br /> 26サウンドのディレクション<br /> 27アルファ版のテストプレイ<br /> 5章 ベータ版とデバッグ<br /> 28世界観の構築<br /> 29アセットの量産<br /> 30プレイサイクルの見直しと全体のレベルデザイン<br /> 31追加機能の開発<br /> 32サーバー環境の構築<br /> 33運用に向けた設計と準備<br /> 34分析情報の設計<br /> 35QAの実施<br /> 36デバッグ<br /> 6章 配信と運用<br /> 37ベータテスト<br /> 38カスタマーサポート<br /> 39配信/申請<br /> 40ゲーム内施策/イベント<br /> 41KPIの分析<br /> 42KPI分析で得た情報の活用<br /> 43タイトルの運用計画<br /> 44ローカライズ<br /> 7章 これからのモバイルゲーム<br /> 45モバイルゲームの歴史と現在<br /> 46近年のモバイルゲーム市場<br /> 47クリエイターの心得<br /> 48ゲームクリエイターになるためには<br /> 49テレワーク**</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 2,728円 |
 図解即戦力 ChatGPTのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 中谷秀洋 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は<a href="gihyo.jp/mk/dp/ebook/2023/978-4-297-14352-7">Gihyo Digital Publishing</a>も併せてご覧ください。</strong></p> <h2><strong>◆ChatGPTのしくみがよくわかる◆</strong></h2> <p>ChatGPTの登場によってAIが身近に感じられるようになりました。AIを使いこなすことによって生活が豊かになる、そんな未来がすぐそこまできています。本書では、「大規模言語モデル」の基本から「トランスフォーマー」や「APIを使ったAI開発」まで、ChatGPTを支える技術を図を交えながら詳しく解説しています。</p> <h2><strong>■こんな方におすすめ</strong></h2> <p>・ChatGPTや大規模言語処理について知りたい人</p> <h2><strong>■目次</strong></h2> <p><strong>●1章 ChatGPT</strong><br /> 01 ChatGPTとは<br /> 02 ChatGPTの便利な機能<br /> 03 プロンプトエンジニアリング<br /> 04 ChatGPTのエンジン(大規模言語モデル)<br /> 05 GPTs(AIのカスタマイズ機能)<br /> 06 ChatGPT以外のAIチャットサービス<br /> 07 AIチャットの利用における注意点<br /> <strong>●2章 人工知能</strong><br /> 08 AI(人工知能)<br /> 09 AIの歴史<br /> 10 生成AIと汎用人工知能<br /> <strong>●3章 機械学習と深層学習</strong><br /> 11 機械学習<br /> 12 ニューラルネットワーク<br /> 13 ニューラルネットワークの学習<br /> 14 正則化<br /> 15 コンピュータで数値を扱う方法<br /> 16 量子化<br /> 17 GPUを使った深層学習<br /> <strong>●4章 自然言語処理</strong><br /> 18 自然言語処理<br /> 19 文字と文字コード<br /> 20 単語とトークン<br /> 21 トークナイザー<br /> 22 Word2Vec<br /> 23 埋め込みベクトル<br /> <strong>●5章 大規模言語モデル</strong><br /> 24 言語モデル<br /> 25 大規模言語モデル<br /> 26 ニューラルネットワークの汎用性と基盤モデル<br /> 27 スケーリング則と創発性<br /> 28 言語モデルによるテキスト生成の仕組み<br /> 29 テキスト生成の戦略<br /> 30 言語モデルによるAIチャット<br /> 31 ローカルLLM<br /> 32 大規模言語モデルのライセンス<br /> 33 大規模言語モデルの評価<br /> 34 大規模言語モデルの学習〜事前学習〜<br /> 35 大規模言語モデルの学習〜ファインチューニング〜<br /> 36 コンテキスト内学習<br /> <strong>●6章 トランスフォーマー</strong><br /> 37 回帰型ニューラルネットワーク(RNN)<br /> 38 注意機構(Attention)<br /> 39 注意機構の計算<br /> 40 トランスフォーマー(Transformer)<br /> 41 BERT<br /> 42 GPT(Generative Pretrained Transformer)<br /> <strong>●7章 APIを使ったAI開発</strong><br /> 43 OpenAI APIの利用<br /> 44 テキスト生成API(Completion API等)<br /> 45 OpenAI APIの料金<br /> 46 テキスト生成APIに指定するパラメータ<br /> 47 テキスト生成APIと外部ツールの連携〜Function Calling〜<br /> 48 埋め込みベクトル生成APIと規約違反チェックAPI<br /> 49 OpenAI以外の大規模言語モデルAPIサービス<br /> 50 Retrieval Augmented Generation(RAG)<br /> <strong>●8章 大規模言語モデルの影響</strong><br /> 51 生成AIのリスクとセキュリティ<br /> 52 AIの偏りとアライメント<br /> 53 ハルシネーション(幻覚)<br /> 54 AIの民主化<br /> 55 大規模言語モデルの多言語対応<br /> 56 AIと哲学</p> <h2><strong>■著者プロフィール</strong></h2> <p><strong>中谷秀洋</strong>:サイボウズ・ラボ(株)所属。子供のころからプログラムと小説を書き、現在は機械学習や自然言語処理、LLMを中心とした研究開発に携わる。著書に『[プログラミング体感まんが]ぺたスクリプト ── もしもプログラミングできるシールがあったなら』『わけがわかる機械学習 ── 現実の問題を解くために、しくみを理解する』(ともに技術評論社)がある。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 2,640円 |
 図解即戦力 不動産業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書[改訂2版]【電子書籍】[ 畑中学 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>(概要)</strong><br /> <strong>※この商品は固定レイアウトで作成されており,タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また,文字列のハイライトや検索,辞書の参照,引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing ( gihyo.jp/mk/dp/ebook/2022/978-4-297-13183-8 )も合わせてご覧ください。</strong><br /> 国内総生産の1割を占める不動産業は、「開発」「分譲」「流通」「賃貸」「管理」「証券化」の6つに分けられます。平均年収は銀行業界と肩を並べるランキング位置にあり、高収入をめざす労働者の就職・転職市場としても活況を呈する業界です。コロナ禍の影響や新築住宅の着工数減少もあり国内需要は縮小傾向にある一方で、不動産関連の事業者や従業員の数は増えています。本書は不動産事業の基本知識からビジネスモデル、最新のトピックに加え、流動的な人材市場である不動産業界の職場環境(2章)や必須スキルと資格(9章)など、就職転職に役立つ情報を提供します。改訂版ではカーボンニュートラルへの取り組みや、コロナ禍や戦争の影響による業界の変容や抱える問題点を解説しています。</p> <p><strong>(こんな方におすすめ)</strong><br /> ・不動産業界(開発、分譲、流通、賃貸、管理、証券化)に就職・転職を考えている人<br /> ・不動産業界に進出を考えている経営者・起業家、取引・協業関係者(ex.住宅ローン融資担当の新人銀行マンなど)</p> <p><strong>(目次)</strong><br /> <strong>Chapter 1 不動産業界の基礎知識と現状</strong><br /> 01 「取引業」と「賃貸・管理業」に分類される不動産業<br /> 02 そもそも「不動産」とは何か<br /> 03 多くの法律や制度に制限を受ける不動産業務<br /> 04 日本経済への影響が大きい不動産<br /> 05 従業員一人当たりの付加価値額が高い不動産業<br /> 06 建設業、金融業との相互補完関係で成り立つ不動産業<br /> 07 上昇基調が続く不動産価格<br /> 08 小規模事業者が圧倒的に多い不動産業<br /> 09 不動産業界の従業者数と男女の構成比<br /> 10 不動産業の関係職種<br /> 11 不動産業における仕事の特色<br /> <strong>Chapter 2 不動産業の各事業の構成と流れ</strong><br /> 01 不動産事業の構成と概要<br /> 02 明治・大正期に成立した不動産業<br /> 03 四大財閥を中心に進んだ開発事業と私鉄の沿線開発で発展した分譲事業<br /> 04 大正時代に専業化した流通事業と戦後から始まった管理事業<br /> 05 政府主導で整えられた住宅ローン制度<br /> 06 不動産の種類と所有者の意向で変わるプロジェクトの流れ<br /> 07 3つの具体的なケースで見る各プロジェクトの流れ<br /> 08 各事業のプロジェクトが終わるまでのタイムスケジュール<br /> 09 開発やマンション分譲は大手企業、戸建て分譲はパワービルダーが牽引<br /> 10 流通事業は大手が優位 賃貸、管理事業は課題克服が鍵<br /> ■不動産業界の勢力図<br /> <strong>Chapter 3 開発・分譲に関連する事業と業務</strong><br /> 01 大手がリードする開発事業、中小が活躍する分譲事業<br /> 02 開発賃貸と再開発・不動産活用の2つの事業<br /> 03 開発賃貸事業の5つの業務<br /> 04 再開発・不動産活用事業の6つの業務<br /> 05 一戸建て・土地分譲、マンション分譲の2つの分譲事業<br /> 06 戸建て・土地分譲事業の5つの業務<br /> 07 マンション分譲事業の6つの業務<br /> 08 加速する日本の不動産開発技術の海外進出<br /> 09 バブル期の年収倍率に近づきつつある住宅価格<br /> 10 カーボンニュートラルへ向けた取り組みと補助制度<br /> 11 省・再生エネルギーで注目されるスマートシティとZEH<br /> <strong>Chapter 4 流通に関連する事業と業務</strong><br /> 01 販売代理業務・媒介業務とリノベーション事業の業務<br /> 02 マンション、戸建て、土地区画の販売代行<br /> 03 物件情報の学習から契約・諸手続きまで<br /> 04 一戸建てとマンションの分譲で異なる業務<br /> 05 個人・法人仲介、売買・賃貸仲介に分けられる媒介業務<br /> 06 売主の探索から物件の引き渡しまで<br /> 07 売買仲介業務を支えるネットワークシステム「レインズ」<br /> 08 中古住宅の状態や性能を明確にし取引が活性化する時代へ<br /> 09 品質の説明責任が明確化された契約不適合責任<br /> 10 利益が大きい分、リスクも高いリノベーション事業の業務<br /> 11 リノベーション前の不動産の見極めが重要な業務<br /> 12 「安心R住宅」制度で中古住宅のマイナスイメージを払拭<br /> 13 付加価値・周辺サービスの拡充・業務シェアがポイント<br /> <strong>Chapter 5 賃貸管理に関連する事業と業務</strong><br /> 01 不動産業の基幹事業、賃貸業務と管理業務<br /> 02 賃貸借(媒介)業務と転貸借(サブリース)業務<br /> 03 入居者募集から鍵の引き渡しまで<br /> 04 入居審査、維持管理、空室対策提案の3つで構成される業務<br /> 05 管理の委託から空室提案まで<br /> 06 集客に重要な不動産情報サイト<br /> 07 個人大家業の始まりと現状<br /> 08 不動産情報の仕入れから空室対策まで<br /> <strong>Chapter 6 ビル・マンション管理に関連する事業と業務</strong><br /> 01 建物の管理に比重を置く管理業務<br /> 02 プロパティマネジメントからバリューアップ工事まで<br /> 03 管理業で特に重要なビルメンテナンスの仕事<br /> 04 マンション管理業の根幹は基幹事務<br /> 05 管理組合との打ち合わせから区分所有者の対応まで<br /> 06 法律の知識と対人スキルが必須<br /> 07 必要とされる老朽化対策<br /> <strong>Chapter 7 不動産証券化・投資その他に関連する事業と業務</strong><br /> 01 不動産を取得し、投資家に販売・配当する事業<br /> 02 アレンジメント、アセット、プロパティの3つで構成される業務<br /> 03 収益不動産の仕入れが重要<br /> 04 不動産の仕入れから引き渡しまで<br /> 05 厳格化したサブリース契約の規制と登録、収益不動産の融資審査<br /> 06 キャッシュフローを重視<br /> 07 必要不可欠な不動産に関わる税金の知識<br /> <strong>Chapter 8 不動産業界で必要とされるスキルと資格</strong><br /> 01 トラブルなく仕事を進めるための基礎知識とスキル<br /> 02 最も必要なのは金融と法律の知識<br /> 03 国家資格や公的資格のほか、さまざまな民間資格がある<br /> 04 宅地建物取引士は不動産取引の法務の専門家<br /> 05 不動産鑑定士は適正地価を判断する不動産価格の専門家<br /> 06 マンション管理士、管理業務主任者はマンション管理の専門家<br /> 07 不動産業界で近年注目されている 公認 不動産コンサルティングマスター<br /> 08 スキル・知識を証明し価値を高めるその他の資格<br /> 09 建築士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁護士との協業<br /> <strong>Chapter 9 不動産業界の職場とキャリアプラン</strong><br /> 01 瞬発力が求められる不動産業界の職場<br /> 02 求められる人材像は会社の規模で異なる<br /> 03 企業規模や事業などによって異なる不動産会社の給与形態<br /> 04 不動産の流通量が決め手となる都市部と地方や郊外の業務構造<br /> 05 不動産業界における4つのキャリアプラン<br /> 06 入職者と離職者がほぼ同数の不動産業界での転職<br /> 07 創業しやすく開業率は高いが廃業率は全種平均と同じ不動産業<br /> <strong>Chapter 10 不動産業界の新規ビジネスと将来像</strong><br /> 01 人口減少と少子高齢化により生まれた新たなビジネス<br /> 02 建設業就業者と大工の減少により住宅関連業は減退へ<br /> 03 不動産にさらなる付加価値を与える不動産テック<br /> 04 不動産会社や利用者をサポートする日本の不動産テック<br /> 05 高齢化の波を受けて進出した相続関連事業<br /> 06 コンパクトシティ化による地方再生<br /> 07 空き家ごとの特徴を活かした空き家対策を推進画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,760円 |
 図解即戦力 PMBOK第6版の知識と手法がこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 株式会社TRADECREATE イープロジェクト 前田和哉 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p>本書はPMBOKガイド第6版が提唱する「5つのプロセス群」「10の知識エリア」「49のプロセス」の要点をわかりやすく解説します。社内のプロジェクトをマネジメントするために必要な知識と手法がよくわかります。PMP試験の対策用としてもおすすめできる1冊です。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 2,178円 |
 図解即戦力 工作機械業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 永井知美 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>(概要)</strong><br /> 工作機械は、あらゆる機械や部品類の製造に用いられており、性能の優劣が製品の競争力を大きく左右します。そのため、各国とも工作機械産業を戦略的基幹産業と位置付け、その発展に力を尽くしています。本書は、そのような工作機械業界を簡潔かつ網羅的に解説しており、就職・転職・取引にあたっての業界研究で役立つ情報が満載の1冊です。</p> <p><strong>(こんな方におすすめ)</strong><br /> ・工作機械業界に入ったばかりの方、工作機械業界と取引のある方</p> <p><strong>(目次)</strong><br /> <strong>Chapter 1 ものづくりを支える工作機械</strong><br /> 01 工作機械とは何かマザーマシンと呼ばれる工作機械<br /> 02 工作機械の加工方法と種類目的に合わせた多種多様な製品<br /> 03 生産額で世界3位の日本工作機械業界1日本の製造業で健闘する数少ない業界<br /> 04 生産額で世界3位の日本工作機械業界2コロナ禍で打撃受けるも需要は回復基調<br /> 05 工作機械が注目される理由機械の性能を左右する工作機械<br /> 06 日本の工作機械の強み1高性能・リーズナブル<br /> 07 日本の工作機械の強み2きめ細かなサービス<br /> 08 日本の工作機械の強み3デジタル化へいち早く取り組む<br /> 09 日本の工作機械業界の立ち位置高位機種でも欧米に迫る<br /> 10 工作機械業界の歩み1起源はなんと古代エジプト<br /> 11 工作機械業界の歩み1NC工作機械で飛躍した日本<br /> <strong>Chapter 2 工作機械の種類・サービス</strong><br /> 01 多種多様な工作機械1ニーズに合わせて製品を展開する工作機械業界<br /> 02 多種多様な工作機械2工作機械の加工方法<br /> 03 多種多様な工作機械3NC工作機械とは何か<br /> 04 主な工作機械1旋盤<br /> 05 主な工作機械2マシニングセンタ<br /> 06 主な工作機械3ターニングセンタ(複合加工機)<br /> 07 主な工作機械4その他の工作機械<br /> 08 計測、制御計測装置、制御ソフトウェア<br /> 09 工作機械メーカーのサービス1アフターサービスの重要性<br /> 10 工作機械メーカーのサービス2工作機械の設計から立ち上げまで受託する「ターンキー」<br /> <strong>Chapter 3 工作機械業界のビジネスモデル</strong><br /> 01 業界のしくみ1工作機械メーカー<br /> 02 業界のしくみ2サプライヤー<br /> 03 業界のしくみ3収益構造<br /> 04 工作機械業界の特徴1受注生産が主でリードタイムが長い<br /> 05 工作機械業界の特徴2労働集約型から知識型産業へ<br /> 06 工作機械の価値1ビジネスモデルの進化<br /> 07 工作機械の価値2サポート体制の充実とデジタル化の重要性<br /> 08 イベント・見本市への取り組みJIMTOFは世界有数の工作機械見本市<br /> 09 工作機械業界の主要ユーザー1自動車業界1最大のユーザー<br /> 10 工作機械業界の主要ユーザー2自動車業界2電動化が進展するとどうなるのか<br /> 11 工作機械業界の主要ユーザー3一般機械<br /> 12 工作機械業界の主要ユーザー4電機業界、半導体業界<br /> <strong>Chapter 4 工作機械業界に求められる人材</strong><br /> 01 工作機械業界の業務内容工作機械業界の現状と「人」の重要性、業務内容<br /> 02 求められる資質1技能・知識、グローバル化への対応能力<br /> 03 求められる資質2開発・設計:高まるソフトの重要性<br /> 04 求められる資質3製造・エンジニアリング<br /> 05 求められる資質4営業、マーケティング<br /> 06 求められる資質5アフターサービス<br /> 07 求められる資質6企業活動を裏から支える管理系業務<br /> 08 工作機械業界の給与水準景気動向に左右される給与水準<br /> 09 工作機械業界での勤務勤務時間、休暇<br /> 10 工作機械業界の研修体制社員教育、福利厚生<br /> 11 多様な人材の採用ダイバーシティ<br /> <strong>Chapter 5 工作機械業界の主要メーカー</strong><br /> 01 工作機械メーカーの特徴1オーナー企業が多く自己資本比率が高い<br /> 02 工作機械メーカーの特徴2様々なタイプの企業が市場をすみ分け<br /> 03 世界最大級の工作機械メーカーDMG森精機、先端分野を強化<br /> 04 世界トップクラスの工作機械メーカー海外生産で先鞭をつけたヤマザキマザック<br /> 05 強みはハイエンド製品総合大手の牧野フライス製作所<br /> 06 日本で作って世界で勝つ独自技術に強みを持つ総合大手のオークマ<br /> 07 有力兼業メーカー自動車業界の大変革に備えるジェイテクト<br /> 08 グローバルに活躍ニッチ機種でグローバルに展開するシギヤ精機製作所<br /> 09 NC装置で市場を席巻工作機械用NC装置で世界首位のファナック<br /> <strong>Chapter 6 世界の工作機械産業</strong><br /> 01 世界の工作機械需要に影響する中国中国がけん引した世界の工作機械需要<br /> 02 主要国の工作機械の輸出入生産高・輸入額でも首位の中国輸出は日独2強<br /> 03 世界の工作機械のシェア世界の工作機械メーカーの勢力図<br /> 04 欧州の工作機械産業欧州の工作機械メーカー<br /> 05 米国の工作機械産業米国の工作機械メーカー<br /> 06 韓国の工作機械産業韓国の工作機械メーカー<br /> 07 台湾の工作機械産業台湾の工作機械メーカー<br /> 08 中国の工作機械産業中国の工作機械メーカー<br /> 09 工作機械業界における法規制輸出管理(外国為替及び外国貿易法、ホワイト国・非ホワイト国)<br /> 10 製品の安全のためにCE(Conformit? Europ?enne)マーク規制<br /> <strong>Chapter 7 工作機械業界の技術トレンド</strong><br /> 01 コロナ禍で進展するデジタル化1コネクティッド・サービス<br /> 02 コロナ禍で進展するデジタル化2デジタルツインで作業の効率化<br /> 03 複数の加工を1台で多機能化が進展する工作機械<br /> 04 人手不足をカバーするために工作機械の自動化・知識化<br /> 05 顧客がしたいことを1つの窓口でトータルソリューションへのニーズ<br /> 06 超精密な加工超精密・超大型・複雑形状加工、非金属の脆性材切削ニーズの高まり<br /> 07 自動化の推進ロボットと工作機械を組み合わせるニーズも<br /> 08 工作機械と環境問題環境意識の高まり<br /> 09 今後需要の伸びが期待できるユーザー業界1航空機・宇宙産業<br /> 10 今後需要の伸びが期待できるユーザー業界2環境関連、医療<br /> <strong>Chapter 8 工作機械業界の展望</strong><br /> 01 中長期的に需要は拡大の見通し1国内外で需要拡大<br /> 02 中長期的に需要は拡大の見通し2環境関連、生産現場の自動化・高度化需要が増加<br /> 03 米中貿易摩擦とコロナ禍の影響サプライチェーン再構築の動きも<br /> 04 アジア勢の追い上げ1工作機械もモジュラー型に変わる?<br /> 05 アジア勢の追い上げ2日本の工作機械メーカーはコモディティ化を免れるのか<br /> 06 日本メーカーの戦略1デジタル技術の活用<br /> 07 日本メーカーの戦略2アナログ面の強みを生かす<br /> 08 日本メーカーの戦略3さらに高度な工作機械を</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,650円 |
 図解即戦力 社会保険・労働保険の届け出と手続きがこれ1冊でしっかりわかる本【電子書籍】[ 小岩和男【監修】 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>(概要)</strong><br /> 本書は社会保険と労働保険のしくみと手続きがしっかりわかる教科書です。従業員の入社・退社時、出産・育児・介護、病気・ケガなどの発生時の手続き、保険料の計算と納付、休業制度や給付金の請求まで、ケースに応じてわかりやすく解説。マイナンバーの取扱い・定年再雇用の手続きにもしっかり対応して、人事・労務担当者必携の1冊です!<実務に役立つチェックシートのダウンロードサービス付き></p> <p><strong>(こんな方におすすめ)</strong><br /> ・会社で社会保険・労働保険の実務を担当する方<br /> ・従業員に必要な保険制度を理解したい個人事業主<br /> ・手当て・休業などの保険制度を利用したい被保険者</p> <p><strong>(目次)</strong><br /> <strong>第1章 社会保険・労働保険の基本をおさえる</strong><br /> 1 社会保険と労働保険を知ろう<br /> 2 医療保険の種類と給付対象を知ろう<br /> 3 年金制度の種類としくみを知ろう<br /> 4 40歳から徴収となる介護保険料(健康保険料と併せて納付)<br /> 5 労災保険と雇用保険のしくみと役割<br /> 6 労災保険適用外の人でも入れる特別加入制度<br /> 7 社会保険に加入義務のある事務所とは<br /> 8 労働保険の成立と保険料申告・納付手続き<br /> 9 役員と従業員の社会保険・労働保険の加入義務<br /> 10 パートタイマー・アルバイトの社会保険・労働保険の加入義務<br /> 11 社会保険・労働保険でのマイナンバーの取り扱い<br /> <strong>第2章 従業員の入社時・退職時の手続き</strong><br /> 1 従業員入社のときの手続きの流れを知ろう<br /> 2 社会保険・雇用保険の手続きに必要な情報を取得する<br /> 3 加入する必要がある保険の種類と加入要件<br /> 4 入社時の健康保険・厚生年金保険の加入手続き<br /> 5 入社時の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届の作成<br /> 6 入社時の労災保険・雇用保険の加入手続き<br /> 7 外国人を雇い入れるときに確認すること<br /> 8 外国人の社会保険の手続きとは<br /> 9 外国人を雇用した際の届け出<br /> 10 従業員が退職するときの手続きの流れを知ろう<br /> 11 退職時の健康保険・厚生年金保険の喪失手続き<br /> 12 退職者の健康保険の任意継続(最大2年)の手続き<br /> 13 退職後すぐに就職しない人の医療保険・年金保険の手続き<br /> 14 退職時の雇用保険の失業給付について知ろう<br /> 15 退職時の雇用保険の喪失手続き<br /> 16 退職時に作成する雇用保険の離職証明書<br /> 17 退職後も傷病手当金の給付を受けるには<br /> 18 退職後も労災保険からの給付を受けるには<br /> <strong>第3章 妊娠・出産・育児・介護に伴う手続き</strong><br /> 1 従業員の出産・育児に伴う給付や手続きの流れを知ろう<br /> 2 産前産後休業中の社会保険料免除の手続き<br /> 3 育児休業中の社会保険料免除の手続き<br /> 4 出産したときの出産育児一時金の給付手続き<br /> 5 産休中に賃金が出ない場合の出産手当金の支給手続き<br /> 6 退職後にも受けられる出産・育児に伴う給付の要件<br /> 7 育児休業中の収入を補う育児休業給付金のしくみ<br /> 8 育児休業給付金の初回申請の手続き<br /> 9 育児休業給付の手続き (2カ月ごとの支給申請)<br /> 10 3歳未満の子を療育する人への将来年金を減らさない特例制度<br /> 11 介護休業で賃金が減った人への給付金の支給手続き<br /> <strong>第4章 病気・ケガ・死亡に伴う手続き</strong><br /> 1 労災保険と健康保険の違いと給付内容を知ろう<br /> 2 仕事中・通勤中にケガをしたときの初期対応<br /> 3 交通事故など相手がいる事故のとき<br /> 4 仕事中・通勤中のケガなどで治療を受けるとき<br /> 5 従業員や被扶養者が医療費を立て替えたとき<br /> 6 治療費が高額になったとき<br /> 7 傷病による休業で収入が減ったとき<br /> 8 従業員に障害が残ったとき<br /> 9 従業員が亡くなったとき<br /> <strong>第5章 従業員の各種変更手続き</strong><br /> 1 氏名・住所が変わったとき<br /> 2 扶養家族のしくみについて知ろう<br /> 3 扶養する家族が増えたとき<br /> 4 扶養する家族が減ったとき<br /> 5 在籍出向や転籍出向をしたとき<br /> 7 海外赴任したとき<br /> 8 雇用保険被保険者証・健康保険被保険者証・年金手帳を紛失したとき<br /> <strong>第6章 定年再雇用・高齢者など年齢で発生する手続き</strong><br /> 1 年齢ごとに発生する手続きについて知ろう<br /> 2 【60歳・65歳の手続き】定年退職をしたときの手続き<br /> 3 【60歳以上の手続き】従業員の定年再雇用時の手続き<br /> 4 【60〜64歳の手続き】高年齢雇用継続給付の手続き<br /> 5 【65歳の手続き】介護保険料の徴収終了<br /> 6 老齢年金の支給のしくみを知ろう<br /> 7 【65歳の手続き】老齢年金の受給手続き<br /> 8 在職中の老齢厚生年金のしくみを知ろう<br /> 9 在職老齢年金の支給停止のしくみと手続き<br /> 10 【70歳・75歳の手続き】社会保険の上限年齢と手続き<br /> <strong>第7章 社会保険料・労働保険料の決め方・納め方</strong><br /> 1 社会・労働保険料の決定から納付までの流れを知ろう<br /> 2 社会保険料計算の基準となる標準報酬月額とは<br /> 3 社会保険料の算出と控除方法<br /> 4 報酬月額の算定などは賞与と現物給与に注意する<br /> 5 標準報酬月額は毎年7月の定時決定(算定基礎届)により決定する<br /> 6 算定基礎届の対象者を確認する<br /> 7 算定基礎届の集計方法<br /> 8 算定基礎届の記入方法<br /> 9 報酬が2等級以上変わったら月額変更届を提出する<br /> 10 月額変更届の集計方法<br /> 11 月額変更届の記入方法<br /> 12 賞与を支払ったら賞与支払届を提出する<br /> 13 労働保険料の決定から納付までの流れを知ろう<br /> 14 労働保険の対象となる労働者と賃金<br /> 15 事業の種類によって異なる労災保険率<br /> 16 雇用保険料の算出と控除方法<br /> 17 毎年6月1日〜7月10日に行う労働保険の年度更新の申告納付<br /> 18 労働保険料の申告と納付の方法<br /> 19 労働保険料の算出と集計表・申告表の記入方法<br /> <strong>第8章 会社に変更があった際の手続き</strong><br /> 1 事業所の名称・所在地が変わったときの手続き<br /> 2 事業所が増えた、移転した、廃止したときの手続き<br /> 3 代表者が変わったときの手続き<br /> 4 会社が社会保険・労働保険をやめるときの手続き<br /> <strong>第9章 電子申請と届け出状況の確認・訂正手続き</strong><br /> 1 電子申請(e-Gov)のしくみと流れを知ろう<br /> 2 電子申請の事前準備<br /> 3 電子申請の手続き<br /> 4 社会保険・労働保険の届け出状況を確認する<br /> 5 間違って届け出したときの訂正方法(社会保険)<br /> 6 間違って届け出したときの訂正方法(労働保険)</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,650円 |
 図解即戦力 マスコミ業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 中野明 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は<a href="gihyo.jp/mk/dp/ebook/2023/978-4-297-13734-2">Gihyo Digital Publishing</a>も併せてご覧ください。</strong></p> <h2><strong>【放送・新聞・出版・広告・ネットメディアの業界構造、仕事内容、求められる資質、問題点まで最新必須知識をこれ1冊でまるごと解説!】</strong></h2> <p>本書では、テレビ・ラジオの放送業界、新聞業界、出版業界、いわゆるマスコミ四媒体はもとより、広告業界とネットメディアについても多くのページを割いて解説しています。業界のしくみから、収益構造、仕事内容、求められる人材、問題点まで、マスコミ業界を網羅した、業界に就職したい人にとっての新スタンダード書籍です。</p> <h2><strong>■目次</strong></h2> <p><strong>Chapter 1 マスコミとは何か</strong><br /> 01 「メディア」と「コミュニケーション」の関係<br /> 02 マスコミ四媒体とは何か<br /> 03 インターネットが持つ3つの潜在能力<br /> 04 目を見張るインターネット広告の進展<br /> 05 マスメディア業界を俯瞰する<br /> 06 マスメディア業界から求められる「人財」<br /> <strong>Chapter 2 放送</strong><br /> 01 そもそも「放送」とは何か<br /> 02 日本における放送の始まり<br /> 03 放送業界はどんな構造になっているのか<br /> 04 放送市場の構成比が変化してきている<br /> 05 地上波テレビ広告費は1兆6,768億円に沈んだ<br /> 06 キー局を中心に全国各地にネットワークを結ぶ<br /> 07 キー局・準キー局・中京局とは何か<br /> 08 底堅い「日テレ」、苦戦の「フジ」<br /> 09 日本の放送業界に君臨する「NHK」<br /> 10 テレビ放送局で働く人々の仕事内容は<br /> 11 テレビ放送のCMにはどんな種類があるか<br /> 12 テレビ視聴者の高齢化が進んでいる<br /> 13 視聴率に影響を及ぼすタイムシフト視聴<br /> 14 テレビ業界にDXの大波が押し寄せている<br /> 15 2年連続のプラス成長となったラジオ広告市場<br /> 16 4系列のラジオ放送ネットワーク<br /> 17 radikoとポッドキャスト<br /> <strong>Chapter 3 新聞</strong><br /> 01 新聞は私信から生まれた<br /> 02 垂直統合型になっている新聞業界<br /> 03 発行部数・売上がともに急降下している<br /> 04 下落に歯止めがかからない新聞広告費<br /> 05 新聞を種類別に見ると多様さがわかる<br /> 06 新聞社には多彩な職種がある<br /> 07 新聞社で働く人は減少傾向にある<br /> 08 若年層の新聞離れが進んでいる<br /> 09 販売部数トップの「読売新聞」<br /> 10 「朝日」「読売」「日経」の激しい売上争い<br /> 11 成功例といえる「日経電子版」の進展<br /> 12 配布エリアで影響力を持つブロック紙と地方紙<br /> 13 ポッドキャストでニュースを聴く<br /> 14 フェイクニュースとの闘い<br /> 15 新聞社にニュースを配信する<br /> <strong>Chapter 4 出版</strong><br /> 01 第3次情報革命が出版社を生んだ<br /> 02 水平分業が特徴の出版・雑誌業界<br /> 03 出版業界の市場規模推移<br /> 04 小規模企業が圧倒的に多い出版業界<br /> 05 水平分業型ビジネスモデルで仕事をこなす<br /> 06 一ツ橋グループの「小学館」と「集英社」<br /> 07 デジタル化を推進する「講談社」<br /> 08 さらなる市場拡大が予想される電子書籍<br /> 09 下げ止まらない雑誌市場規模<br /> 10 雑誌広告費は10年前の半分に減少<br /> 11 コアなターゲットにアピールする雑誌<br /> 12 デジタルマンガが進展している<br /> 13 デジタル雑誌読み放題サービスの定着<br /> 14 出版物にRFIDを導入する<br /> <strong>Chapter 5 広告</strong><br /> 01 広告とマスコミュニケーションの深い関係<br /> 02 キープレーヤーとしての広告会社とその周辺に集う企業群<br /> 03 過去最高を記録した広告市場規模<br /> 04 マスコミ四媒体の3大クライアント<br /> 05 プロモーションメディア広告とは何か<br /> 06 「電通」に「博報堂DYHD」「サイバーエージェント」が続く<br /> 07 日本の広告業を牛耳る「電通」<br /> 08 世界8位につける「博報堂DYHD」<br /> 09 頭角をあらわす「サイバーエージェント」<br /> 10 コンサルティング系広告会社の躍進<br /> 11 広告会社の3つのセクション<br /> 12 広告会社で働く人々の仕事内容と求められる資質<br /> 13 広告業界には多様な広告関連会社がある<br /> 14 規模の格差が大きい広告業界<br /> <strong>Chapter 6 ネットメディア</strong><br /> 01 5分類で考えるネットメディア<br /> 02 オンラインコンテンツ市場の規模推移<br /> 03 世界で最も大きな広告会社「Google」<br /> 04 ソーシャルメディアの巨人「Facebook」<br /> 05 プラットフォーマーは新たなマスメディアか<br /> 06 日本で大きな影響力を持つ「Zホールディングス」<br /> 07 人気を集めているニュースアプリ<br /> 08 ソーシャルメディアによる広告ターゲットの絞り込み<br /> 09 サブスクリプション型動画配信の進展<br /> 10 ネットで息を吹き返した音楽業界<br /> 11 3次元仮想空間メタバースは普及するのか<br /> 12 ChatGPTは次世代のマスメディアなのか<br /> 13 伸びる動画インターネット広告<br /> 14 かつての主流、予約型広告と現在の主流、運用型広告<br /> 15 運用型広告を支えるリアルタイムビッディング<br /> 16 サードパーティークッキーの制限<br /> 17 ネット広告ビジネスの主なプレイヤー<br /> 18 ネットメディアで働く人々<br /> 19 ネットメディアとコンプライアンス<br /> <strong>Chapter 7 マスコミの未来</strong><br /> 01 マスコミは「マスゴミ」なのか<br /> 02 危機に瀕する従来型マスメディア<br /> 03 DXに成功したニューヨークタイムズ<br /> 04 戦略としてのデジタルファースト<br /> 05 デジタルを経営基盤に据える</p> <h2><strong>■著者プロフィール</strong></h2> <p><strong>中野明</strong>:ノンフィクション作家。1985年、立命館大学文学部哲学科卒。同志社大学理工学部嘱託講師。情報通信、経済経営、歴史文化の分野で執筆する。情報メディア関連の著作としては、『IT全史──情報技術の250年を読む』(祥伝社)、『GAFA「強さの秘密」が1時間でわかる本』(学研プラス)、『ブロードバンド社会がやって来る』(PHP)、『通信業界の動向とカラクリがよくわかる本』(秀和システム)など多数。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,980円 |
 図解即戦力 UMLのしくみと実装がこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 株式会社フルネス 尾崎惇史 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>(概要)</strong><br /> <strong>※この商品は固定レイアウトで作成されており,タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また,文字列のハイライトや検索,辞書の参照,引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing ( gihyo.jp/mk/dp/ebook/2022/978-4-297-12867-8 )も合わせてご覧ください。</strong><br /> UMLはオブジェクト指向技術を使ってシステムを設計する際に利用する図とその目的、及び記法を定めたものです。近年ではすっかり定着し、開発者同士の共通フォーマットとしての利用はもとより、システム開発の納品物に加えられるまでになってきました。本書はそんなUMLの全体像をイラストを使ってわかりやすく解説します。</p> <p><strong>(こんな方におすすめ)</strong><br /> ・UMLを利用してシステム開発を行いたい初心者(IT企業に関わる新人エンジニアおよび開発系営業)</p> <p><strong>(目次)</strong><br /> <strong>1章 UMLの基礎知識</strong><br /> 01 概要 〜UML(統一モデリング言語)とは〜<br /> 02 歴史 〜UMLの起こり〜<br /> 03 バージョンアップ 〜UMLの改善〜<br /> 04 モデリング 〜UMLの根底となる考え方〜<br /> <strong>2章 オブジェクト指向</strong><br /> 01 オブジェクト指向とは<br /> 02 オブジェクト・クラスの静的構造<br /> 03 オブジェクト・クラス間の関係<br /> 04 オブジェクト・クラスの動的構造<br /> 05 オブジェクト指向の3大要素<br /> <strong>3章 UMLの全体像</strong><br /> 01 UMLの図の種類と分類<br /> 02 図の要素 〜UMLを構成する代表的な図形や線〜<br /> 03 共通メカニズム 〜UMLの補足情報の記載〜<br /> 04 ツール 〜UMLをより便利に扱う〜<br /> <strong>4章 UMLにおける構造図の基本文法</strong><br /> 01 オブジェクト図 〜図と図を構成する要素図形〜<br /> 02 オブジェクト図 〜要素の関係性を示す関連線〜<br /> 03 クラス図 〜図と図を構成する要素図形〜<br /> 04 クラス図 〜要素の関係性を示す関連線〜<br /> 05 合成構造図 〜図と図を構成する要素図形〜<br /> 06 パッケージ図 〜図と図を構成する要素図形〜<br /> 07 パッケージ図 〜要素の関係性を示す関連線〜<br /> 08 コンポーネント図 〜図と図を構成する要素図形〜<br /> 09 コンポーネント図 〜要素の関係性を示す関連線〜v 10 配置図 〜図と図を構成する要素図形〜<br /> 11 配置図 〜要素の関係性を示す関連線〜<br /> <strong>5章 UMLにおける振る舞い図の基本文法</strong><br /> 01 ユースケース図 〜図と図を構成する要素図形〜<br /> 02 アクティビティ図 〜図と図を構成する要素図形〜<br /> 03 アクティビティ図 〜要素の関係性を示す関連線〜<br /> 04 アクティビティ図の要素図形 〜遷移を制御する制御ノード〜<br /> 05 アクティビティ図の区分 〜要素図形を分ける区分〜<br /> 06 ステートマシン図 〜図と図を構成する要素図形〜<br /> 07 ステートマシン図 〜要素の関係性を示す関連線〜<br /> <strong>6章 UMLにおける相互作用図の基本文法</strong><br /> 01 コミュニケーション図 〜図と図を構成する要素図形〜<br /> 02 コミュニケーション図 〜要素の関係性を示す関連線〜<br /> 03 シーケンス図 〜図と図を構成する要素図形〜<br /> 04 シーケンス図 〜要素の関係性を示す関連線〜<br /> 05 シーケンス図 〜要素図形を分ける区分〜<br /> 06 相互作用概要図 〜図と図を構成する要素図形及び要素の関係性を示す関連線〜<br /> 07 タイミング図 〜図と図を構成する要素図形〜<br /> 08 タイミング図 〜要素の関係性を示す関連線〜<br /> <strong>7章 開発の標準化</strong><br /> 01 開発標準と開発工程<br /> 02 要件定義 〜システム開発の目的を定める〜<br /> 03 設計 〜システム開発の方法を定める〜<br /> 04 製造 〜実際にシステムを作る〜<br /> 05 試験 〜作ったシステムを検証する〜<br /> 06 開発方式<br /> <strong>8章 要件定義におけるUMLの作成</strong><br /> 01 要求の収集<br /> 02 トップダウンアプローチ<br /> 03 ボトムアップアプローチ1<br /> 04 ボトムアップアプローチ2<br /> 05 業務分析<br /> 06 ユースケース分析<br /> <strong>9章 設計におけるUMLの作成</strong><br /> 01 ハードウェアアーキテクチャ設計<br /> 02 ソフトウェアアーキテクチャ設計<br /> 03 クラス設計<br /> 04 相互作用設計<br /> <strong>10章 製造/試験におけるUMLの活用</strong><br /> 01 プログラミング<br /> 02 環境構築<br /> 03 機能試験の作成<br /> 04 システム試験の作成</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 2,640円 |
 図解即戦力 ビッグデータ分析のシステムと開発がこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 渡部徹太郎 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p>近年はビッグデータを分析し、ビジネスに活かすのは当たり前の時代となりました。今後IoTやAIなどの活用が期待される中、データを分析するだけではなく、データを集める・溜める・活用することが重要になってきています。本書は一般的なインターネット事業を展開する企業において、ビッグデータ分析システムをしっかり本番システム化する基本知識を図とともにわかりやすく解説しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 2,398円 |
 図解即戦力 貿易実務がこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 布施克彦 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>(概要)</strong><br /> **※この商品は固定レイアウトで作成されており,タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また,文字列のハイライトや検索,辞書の参照,引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は Gihyo Disital Publishing ( gihyo.jp/mk/dp/ebook/2020/978-4-297-11487-9 )も合わせてご覧ください。****貿易を行う際には、書類の準備や支払いなどの様々な実務が発生します。これらは世界の状況や法律の改正によって手続きが変わることもあり、常に最新の情報を理解しておく必要があります。そこで本書では、貿易全体の流れや関わってくる企業・人、輸出側・輸入側それぞれの実務、必要な書類などをわかりやすく解説します。また、実務の現場で起きるトラブル等を元にしたQ&Aと、知っておきたいキーワード集も収録。最新のインコタームズ2020にも対応!</p> <p>(こんな方におすすめ)<br /> ・仕事で輸出入の実務に関わる人、貿易の流れを知りたい人</p> <p>(目次)<br /> chapter1 貿易の基礎知識<br /> 貿易とは何か 輸出入者とは誰か把握する<br /> 貿易実務の三要素と流れを把握する<br /> 通関業務における商品とカネの動き<br /> 貿易実務に関わるさまざまな業種<br /> 商社と海外代理店はどう違うか<br /> どのようなモノが貿易の対象となるのか<br /> 貿易と国内取引は何が違うのか<br /> デジタル化が進む貿易実務のシステム<br /> chapter2 輸出入の流れ<br /> 輸出実務・輸入実務の大まかな流れ<br /> 買い手探しから交渉・契約までの流れ<br /> 商品の準備から物流・納品までの流れ<br /> 商品出荷後から代金受け取りまでの流れ<br /> 売り手探しから交渉・契約までの流れ<br /> 輸入準備から商品受け取りまでの流れ<br /> 商品受け取りから代金支払いまでの流れ<br /> chapter3 輸出入における交渉<br /> 海外に商品を売るときの輸入者の選び方<br /> 海外から商品を買うときの輸出者の選び方<br /> どのような場合に商社に仲介を依頼するか<br /> オファーを出してもらえる引き合いの出し方<br /> 戦略を交えたオファーの出し方<br /> オファーを出す際の価格の見積もり方<br /> オファーのあとの契約に向けた交渉<br /> 契約後に行うサンプル取引の意味<br /> chapter4 インコタームズと契約書の内容<br /> 契約書の作成における基本的な要件<br /> 契約書のフォームと盛り込むべき条件<br /> インコタームズは貿易の世界統一ルール<br /> インコタームズの定める受け渡し条件<br /> インコタームズの輸出地側での受け渡し条件(1)<br /> インコタームズの輸出地側での受け渡し条件(2)<br /> インコタームズの輸入地側での受け渡し条件(1)<br /> インコタームズの輸入地側での受け渡し条件(2)<br /> L / C 決済のしくみと基本的な機能<br /> L / C を受け取ったら何をチェックすればよいか<br /> L / C 通知銀行の決め方とL / C の決済方法<br /> L / C を伴わない取り立て決済<br /> 主流化が進む送金決済の種類と背景<br /> 新しい決済手段 仮想通貨とTSUーBPO<br /> 外貨建て決済取引における為替業務<br /> 輸送方法で決まる船積み時期と納期の違い<br /> 貿易に必要な海上保険と貿易保険<br /> 契約を結ぶにあたり決めておくべきこと<br /> chapter5 輸出実務1 輸出準備<br /> 商品準備開始に伴う輸出手配のポイント<br /> 輸送手段の手配に必要な実務<br /> 輸出許可と輸出承認の取得<br /> 危険物資を取り締まるキャッチオール規制<br /> 取引の採算を確定させる為替の予約手続き<br /> 海上保険がカバーする損害の範囲<br /> 自社のリスクをカバーする貿易保険を掛ける<br /> 輸出する商品が契約通りか検査する<br /> 梱包方法に対応できるかが交渉のポイント<br /> chapter6 輸出実務2 輸出手続き<br /> 輸出手続き全体の流れを掴む<br /> 海外輸送に使う船舶とコンテナの基礎知識<br /> コンテナヤードに商品を搬入する<br /> フォワーダーに輸出代行を依頼する<br /> 税関申告に向け輸出ポイントへ搬出する<br /> 税関に輸出申告をして審査を受ける<br /> 在来船における輸出船積み手続き<br /> コンテナ船における輸出船積み手続き<br /> 航空機輸送における輸出手続き<br /> chapter7 輸出実務3 代金決済手続き<br /> 船積み後の代金決済実務の流れ<br /> 船積み作業が終わったら船積み通知を送る<br /> 船荷証券(B / L)の機能と記載事項<br /> 輸送形態や記載内容などによるB / L の種類<br /> 輸出者が準備すべき船積み書類の種類と内容<br /> 荷為替手形を作成し銀行に持ち込む<br /> L / C 決済における荷為替手形の取り扱い<br /> B / C 決済における荷為替手形の取り扱い<br /> 航空機輸送貨物の代金決済手段<br /> chapter8 輸入実務1 商品の受け取り<br /> 輸入手続きの大まかな流れ<br /> 契約締結直後の輸入者の実務<br /> 輸入者に求められる輸入許認可<br /> 輸入者に求められる輸入前の手続き<br /> 貨物到着案内を受け取ってからの実務<br /> 在来船からの貨物の引き取り<br /> コンテナ船からの貨物の引き取り<br /> 航空機輸送における貨物の引き取り<br /> 動植物、食品の輸入には検疫が必要<br /> chapter9 輸入実務2 輸入申告と関税<br /> フォワーダーが行う輸入申告と納税手続き<br /> 関税を規定する法律と関税申告の方法<br /> 輸入時の関税をどのように算出するか<br /> 1つの物品に複数ある関税率の優先順位<br /> CIF 金額をもとにした輸入納税額の計算方法<br /> 関税における免税あるいは減税の特例<br /> 事前教示制度と価格評価制度<br /> 輸入申告において優遇される特例輸入者制度<br /> 保税地域は税関が定めた特別区域<br /> 貨物を保税地域に長期間蔵置する<br /> 保税地域内の作業には税関の許可が必要<br /> 税関の承認に必要な申請書の総括<br /> 商品に損傷があった場合の保険会社へのクレーム<br /> 輸出者に対する商品クレームの解決方法<br /> chapter10 貿易書類の書き方・読み方<br /> 貿易書類作成は共通項目を軸に行う<br /> 書類を書くうえで英語力は必要か<br /> 交わす相手によって異なる書類の整理<br /> 最重要書類である契約書作成時の注意点<br /> L / C の機能とL / C 発行依頼書の書き方<br /> 行政機関に対する許認可申請書類<br /> B / L の記載内容と保険証券との相違点<br /> 輸送者が発行する貨物の運送状の種類<br /> インボイスの種類と契約書との相違点<br /> 梱包状態を知らせるパッキングリストの作成方法<br /> グローバル化により複雑になる原産地証明書**</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,650円 |
 図解即戦力 小売業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 中井彰人 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>(概要)</strong><br /> **※この商品は固定レイアウトで作成されており,タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また,文字列のハイライトや検索,辞書の参照,引用などの機能が使用できません。※PDF版をご希望の方は Gihyo Disital Publishing ( gihyo.jp/mk/dp/ebook/2021/978-4-297-12246-1 )も合わせてご覧ください。****「商品を仕入れて消費者に届ける(販売する)」というのが小売の基本です。そんなシンプルなビジネスモデルですが、市場規模(小売販売額)は約118兆円と巨大な業界です。小売業界はこれまでいくつかの業態がその主役の座を交代しつつ成長を続けてきました。本書は、近年の業界の変遷を追いながら、現在進行する再編の動きや直面する課題、そしてECの台頭や消費者行動の変容などによって、大きな転換期を迎えている業界を理解するための知識がしっかりとわかる研究本です。業界全体の動向はもちろん、小売・流通の基本知識から、現在の主流であるチェーンストアの組織や仕事内容、ビジネスのしくみ、そこで抱える問題を、最新のトピックをまじえながら解説していきます。小売業界への就職・転職を考える方にはもちろん、メーカーや流通など小売業界を理解しておきたいという方にも役立つ情報を提供します。</p> <p>(こんな方におすすめ)<br /> ・小売業界に就職・転職を考えている人/メーカーや卸売業など小売業界と関わる流通業に従事している人/小売業界の知識を身につけなければならないエンジニアなど</p> <p>(目次)<br /> Chapter 1 小売業界の動向<br /> 01 個人所得の低下と総中流社会の崩壊<br /> 02 人口減少と高齢化がもたらすマーケットの変化<br /> 03 人口減少と高齢化がもたらす地域格差の拡大<br /> 04 SDGsを前提とした社会への移行<br /> 05 生き残りをかけた業界再編の進行<br /> 06 スマホ普及、5Gが開く新たなマーケティングの時代<br /> 07 キャッシュレス化がもたらす劇的な変化<br /> 08 アフターコロナにおけるインバウンド需要への期待<br /> Chapter 2 小売業界の基本知識<br /> 01 小売・流通の基本的機能<br /> 02 基本的構造である商流と物流<br /> 03 業種別、業態別に見る小売業界の市場規模<br /> 04 日本の小売業を担う組織の変遷<br /> 05 日本の主要小売業のランキング<br /> 06 チェーンストアの普及とその限界<br /> 07 小売業を牽引する業態の推移<br /> 08 チェーンストアを支えるITインフラのイノベーション<br /> 09 チェーンストアを支える物流機能<br /> 10 5フォース分析が導く業界再編の可能性<br /> Chapter 3 主な職種と仕事内容<br /> 01 トップダウンが基本 チェーンストアの組織構成<br /> 02 マネジメントの3階層(トップ・ミドル・ローワー)<br /> 03 小売業におけるトップマネジメントの仕事<br /> 04 経営の根幹にも深くつながるバイヤーの仕事<br /> 05 プライベートブランド開発担当者の仕事<br /> 06 小売チェーンの業績を左右する店舗開発の仕事<br /> 07 本部と店舗の橋渡し スーパーバイザーの仕事<br /> 08 小売業の生命線 物流担当者の仕事<br /> 09 EC担当者、広告宣伝担当者の仕事<br /> 10 現場をつかさどる店長の仕事<br /> 11 パートタイム人材を中心とした店舗スタッフの意識を高める<br /> Chapter 4 業態の変遷の歴史とその背景<br /> 01 ダイエーが牽引したチェーンストアの台頭<br /> 02 ロードサイドマーケットの誕生<br /> 03 ホームセンター、紳士服チェーン、家電量販店などが郊外に出現<br /> 04 バブル崩壊後の金融危機が誘因 総合スーパーの大再編<br /> 05 2000年以降のロードサイドの変化<br /> 06 女性マーケットの確立による新しい専門店チェーンの躍進<br /> 07 総合小売業の衰退と目的別専門店モール<br /> 08 郊外型大規模複合施設で専門店との共存<br /> 09 ネットインフラの整備によるECの台頭<br /> Chapter 5 各業態の知識 百貨店<br /> 01 百貨店の市場規模推移と主要プレイヤー<br /> 02 百貨店の出自と商業立地の変化による現況<br /> 03 百貨店市場低迷の背景<br /> 04 百貨店の成長と衰退の遠因 消化仕入<br /> 05 地方百貨店の相次ぐ閉鎖とその背景<br /> 06 インバウンド需要の受け皿としての新たな可能性<br /> 07 生き残りを賭けた新たな戦略<br /> Chapter 6 各業態の知識 スーパーマーケット<br /> 01 スーパーの市場規模推移、主要プレイヤー<br /> 02 高度成長と共に成長して小売の王者になった総合スーパー<br /> 03 バブル経済崩壊と金融危機で大規模再編へ<br /> 04 総合スーパーが生きられる立地<br /> 05 総合スーパーの停滞とこれから<br /> 06 日本型食品スーパーの成立と普及<br /> 07 地域有力企業の越境と再編に揺れる地場食品スーパー<br /> 08 全国制覇を進めるイオンとリージョナルトップ<br /> 09 プロセスセンターの標準装備化がさらなる再編を促す<br /> Chapter 7 各業態の知識 コンビニエンスストア<br /> 01 コンビニエンスストアの市場規模と主要プレイヤー<br /> 02 フランチャイズによる組織構成<br /> 03 世界トップクラスのチェーンストアインフラ<br /> 04 コンビニが拓いたプライベートブランド(PB)<br /> 05 ドミナント戦略とフランチャイズとのコンフリクト<br /> 06 コンビニ成長力の源泉は新たなニーズ開拓とチャレンジ<br /> Chapter 8 各業態の知識 専門店チェーン<br /> 01 再編でトップが入れ替わるドラッグストア<br /> 02 マツキヨココカラが業界再編に拍車をかける<br /> 03 ホームセンターの市場規模と主要プレイヤー<br /> 04 マーケット縮小をにらみ再編が進むホームセンター<br /> 05 ECシフトが進む家電市場と主要プレイヤー<br /> 06 逆張り戦略で差別化を実現 ドン・キホーテ<br /> 07 北海道から全国展開 大都市攻略も進めるニトリ<br /> 08 専門店が集積する巨大施設 ショッピングセンター<br /> Chapter 9 各業態の知識 EC<br /> 01 EC市場動向と商品別市場の構成<br /> 02 どこでも買い物ができるECの基本的な仕組み<br /> 03 ECが変えたマーケティングの世界<br /> 04 ECモール出店と自社ECサイトのメリット、デメリット<br /> 05 ECチャネルと新たな「経済圏」<br /> 06 デジタル経済圏の覇権争いが激化<br /> 07 今後本格化が期待されるリアル店舗とバーチャルの連携<br /> Chapter 10 小売業界の展望と課題<br /> 01 コロナ禍を経て加速するECシフト<br /> 02 5G時代の到来が小売業にもたらす変化<br /> 03 消費者の行動を分析し新たなビジネスへつなげる<br /> 04 D2Cが生み出すリアル店舗の新しい価値<br /> 05 デジタル武装でチェーンストア理論を超える<br /> 06 地域一番店になるか ローコスト一番店になるか<br /> 07 高齢化の地方を乗り切るコミュニティ共助<br /> 08 求められるSDGsを意識した経営<br /> 付章 情報収集のためのヒント<br /> 01 面接、商談は相手先の事前情報収集が成功の決め手<br /> 02 業界の動向や主要プレイヤーを知るための情報収集<br /> 03 ライバル企業や上位企業の動向を知るための情報収集<br /> 04 業界の将来や周辺環境を知るための情報収集**</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,650円 |
 図解即戦力 IT投資の評価手法と効果がこれ1冊でしっかりわかる教科書【電子書籍】[ 國重靖子 ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><strong>(概要)</strong><br /> 本書は、IT投資の評価手法とその効果を図解でわかりやすく解説した書籍です。汎用機などの IT資産を対象にした従来の評価手法に加え、モバイル機器や情報セキュリティなどの投資効果を定量的に測定する手法も解説しています。モデル例も含めて解説しているため、誰でも即、実務に使えるガイドラインとなるでしょう。さらに、役員向けにIT投資の稟議申請をするときの効果的な企画書の書き方についても紹介しています。職業柄、多くのリーディングカンパニーで幾多もの社内稟議書に目を通してきた著者だからこそ言える貴重なアドバイスも満載です。</p> <p><strong>(こんな方におすすめ)</strong><br /> ・IT投資の評価を担当する人<br /> ・システムエンジニア</p> <p><strong>(目次)</strong><br /> <strong>1章 IT投資効果の評価とは</strong><br /> 01 IT投資評価とは<br /> 02 IT投資とは<br /> 03 IT投資プロジェクトの種類<br /> 04 IT投資評価の目的<br /> 05 IT投資評価に関わる人の立場と役割<br /> 06 IT投資プロジェクトの評価のタイミング<br /> 07 IT投資ポートフォリオとは<br /> 08 IT投資評価の実態と課題<br /> <strong>2章 投資額の算定</strong><br /> 09 投資額の試算方法<br /> 10 クラウド環境利用の場合の考え方<br /> 11 ITコストの分類管理<br /> 12 機器費用の算定上の留意点<br /> 13 社内人件費の算定上の留意点<br /> 14 TCO(Total Cost of Ownership)とは<br /> 15 共通費の配賦の考え方<br /> <strong>3章 投資効果の評価方法</strong><br /> 16 効果額の試算方法<br /> 17 財務的手法〜ROI<br /> 18 財務的手法〜回収期間法<br /> 19 貨幣の時間的価値<br /> 20 財務的手法〜NPV法<br /> 21 財務的手法〜IRR法<br /> 22 非財務的手法〜妥当性評価<br /> 23 非財務的手法〜ユーザー満足度評価<br /> 24 非財務的手法〜SLA<br /> 25 非財務的手法〜情報セキュリティ投資の評価<br /> 26 情報セキュリティ投資の評価のモデル例<br /> 27 財務的手法〜ABC/ABM<br /> 28 非財務的手法〜IT-BSC<br /> 29 IT-BSCによる評価のモデル例<br /> 30 企画書/報告書の作成<br /> <strong>4章 IT投資評価の事例研究</strong><br /> 31 システム開発投資の事前評価の事例<br /> 32 ソーシャルメディアの投資効果の事後評価の事例<br /> 33 モバイル投資の効果測定の事例<br /> 34 セキュリティ投資の効果額の事前評価の事例<br /> 35 IT投資効果評価フレームワークの事例<br /> <strong>5章 投資対効果が未達の場合の対応</strong><br /> 36 「投資額」が予想を超えた場合の対応〜初期費用が予想を超えるケース<br /> 37 「投資額」が予想を超えた場合の対応〜ランニングコストが予想を超えるケース<br /> 38 「効果額」が予想を下回った場合の対応<br /> <strong>6章 開発プロジェクトの投資評価</strong><br /> 39 開発プロジェクトの評価におけるチェック項目<br /> 40 IT投資評価チェックリストの概要<br /> 41 構想・企画段階でのチェック項目<br /> 42 開発開始段階でのチェック項目<br /> 43 開発完了後のチェック項目<br /> <strong>7章 ベンダー見積もりの妥当性評価</strong><br /> 44 ベンダー見積もりの妥当性評価のための前提知識<br /> 45 ベンダー見積もり依頼時の留意点<br /> 46 FP法の応用による開発費の妥当性評価<br /> 47 工数予測モデル構築による開発費の妥当性評価<br /> 48 WBSによる運用委託費の妥当性評価</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 2,728円 |