bms A1 [本・雑誌・コミック]
楽天市場検索
本・雑誌・コミック
小説・エッセイ (0)
資格・検定 (0)
ライフスタイル (0)
ホビー・スポーツ・美術 (0)
絵本・児童書・図鑑 (0)
語学・辞典・年鑑 (0)
学習参考書・問題集 (0)
旅行・留学 (0)
人文・地歴・社会 (0)
ビジネス・経済・就職 (0)
PC・システム開発 (0)
科学・医学・技術 (1) (bms A1)
コミック (0)
ライトノベル (0)
ボーイズラブ (0)
ティーンズラブ (0)
エンターテインメント (0)
写真集 (0)
古書・希少本 (0)
楽譜 (0)
雑誌 (0)
新聞 (0)
洋書 (14) (bms A1)
カレンダー (0)
ポスター (0)
パンフレット (0)
その他 (37) (bms A1)
本・雑誌・コミック
小説・エッセイ (0)
資格・検定 (0)
ライフスタイル (0)
ホビー・スポーツ・美術 (0)
絵本・児童書・図鑑 (0)
語学・辞典・年鑑 (0)
学習参考書・問題集 (0)
旅行・留学 (0)
人文・地歴・社会 (0)
ビジネス・経済・就職 (0)
PC・システム開発 (0)
科学・医学・技術 (1) (bms A1)
コミック (0)
ライトノベル (0)
ボーイズラブ (0)
ティーンズラブ (0)
エンターテインメント (0)
写真集 (0)
古書・希少本 (0)
楽譜 (0)
雑誌 (0)
新聞 (0)
洋書 (14) (bms A1)
カレンダー (0)
ポスター (0)
パンフレット (0)
その他 (37) (bms A1)
52件中 1件 - 30件
1 2
| 商品 | 説明 | 価格 |
|---|---|---|
 STOP! IT'S NOT TOO LATE Adding Years to Your Life and Life to Your Years Using the BMS Ecosystem【電子書籍】[ Dr. Harris E. Phillip ] 楽天Kobo電子書籍ストア | <p><em><strong>Dr. Harris E. Phillip</strong></em> discusses in <strong>STOP! IT'S NOT TOO LATE:</strong> that one can find good health by understanding what makes us humans - Body, Mind, and Spirit. We often focus only our body and fail to take care of the other key parts. This book discusses that balance is essential when taking care of yourself. You can start at any age and enjoy life to its fullest by taking care of your body, mind, and spirit.</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,805円 |
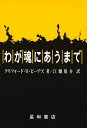 三省堂書店オンデマンド 星和書店 わが魂にあうまで 三省堂書店 | 著者:C.W.ビーアズ 訳者:江畑敬介 本書は、ビーアズ自身の悲惨な入院生活を原体験として、精神病者の処遇を改善し、精神疾患の予防運動を開始するために書かれたもので、アメリカ精神 衛生運動の歴史的原点となった。 | 2,640円 |
 三省堂書店オンデマンド星和書店 精神科治療学 第21巻増刊号 三省堂書店 | ◆内容紹介 本増刊号は、症状性(器質性)精神障害を広く網羅した辞書的な治療ガイドラインである。症状性精神障害(何らかの外因によって精神症状が引き起こされる病態)と器質性精神障害(脳そのものの変性に疾病が由来する場合(アルツハイマー病など))の両方を含めた。ただし神経内科疾患は、頻度が高く精神科医がコンサルトされる可能性が高いもののみを取り上げた。現在、精神医療の第一線で活躍している執筆陣を揃え、現時点における最も充実した症状性(器質性)精神障害の治療ガイドラインとして、精神医療に従事するすべての方々に役立つ。編集:「精神科治療学」編集委員会 B5判 並製 426頁 通巻236号発刊にあたり 兼本浩祐第1章 全身疾患に精神疾患が由来する病態1. 代謝・内分泌疾患 一宮洋介 1-1.甲状腺機能亢進症(subclinical hyperthyroidismを含む) 氏家 寛 1-2.甲状腺機能低下症(subclinical hypothyroidismを含む) 氏家 寛 1-3.クッシング症候群 森田佳寛,郭 哲次,篠崎和弘 1-4.Addison病 岩田正明,挟間玄以 1-5.アルドステロン分泌亢進症(Hyperaldosteronism) 稲見康司 1-6.褐色細胞腫(Pheochromocytoma) 稲見康司 1-7.副甲状腺機能亢進症 沼田周助 1-8.副甲状腺機能低下症・偽性副甲状腺機能低下症・Fahr病 沼田周助 1-9.糖尿病(高浸透圧性昏睡を含む) 堀川直史,大村裕紀子,國保圭介 他 1-10.低血糖性昏睡(インスリノーマを含む) 堀川直史,大村裕紀子,國保圭介 他 1-11.ウィルソン病 天野直二 1-12.急性ポルフィリア 岸 泰宏 1-13.末端肥大症における精神症状 高木潤子,仲宗根裕子,森川 亮 他 1-14.尿崩症 栃本真一,倉田孝一 1-15.高プロラクチン血症 兼田康宏 1-16.下垂体機能低下症 大原一幸 1-17.更年期障害とホルモン補充療法 中山和彦2. 周産期精神障害 岡野禎治3. 膠原病 3-1.全身性エリテマトーデス(SLE)(CNS ループスを含む) 前川和範 3-2.慢性関節リウマチ 西村勝治 3-3.その他の膠原病 西村勝治4. ベーチェット病 中野祐子,南光進一郎5. 肝性脳症 5-1.肝実質障害(壊死型) 深津孝英,兼本浩祐 5-2.肝性脳症—門脈-大循環短絡路形成による側副血行路(シャント)型— 前川和範6. 肝移植 野間俊一,林 晶子,林 拓二7. 腎障害 7-1.腎不全 松木秀幸,松木麻妃,小林清香 他 7-2.透析 松木秀幸,松木麻妃,小林清香 他 7-3.腎移植 小林清香,松木秀幸,西村勝治 他8. 気管支喘息 大友好司,丹羽真一9. 慢性呼吸不全 小野光弘10. 心筋梗塞に伴ううつ病 鳥居洋太,木村宏之,尾崎紀夫11. うっ血性心不全 加茂登志子12. 重症貧血 小森 薫,小森実穂13. がん 13-1.がんに起因する精神科疾患 伊藤達彦,内富庸介 13-2.悪性腫瘍の遠隔効果“Paraneoplastic syndrome” 小早川 誠,岡村 仁14. サルコイドーシス 人見佳枝15. Adrenoleucodystrophy 塩川宏郷16. Chorea-acanthocytosis 齊藤清子,寺田整司,氏家 寛 他17. リウマチ熱および小舞踏病 中村雅之,佐野 輝18. 感染症 18-1.HIV感染症 太田直子,赤穂理絵 18-2.Whipple病 渡辺知佳子,三浦総一郎 18-3.寄生虫感染と精神障害 木村英作 18-4.インフルエンザ 飯村東太,東 孝博 18-5.帰国者の感染症 18-5-1.マラリア 木村幹男 18-5-2.その他(ウィルス性脳炎) 木村幹男第2章 特定の物質の不足ないしは過剰に疾患が由来する病態1. 依存性物質 1-1.アルコール 齋藤利和 1-2.覚せい剤乱用によって生じた精神病の治療 中元総一郎,大川和男,小田晶彦 1-3.鎮咳薬(methylephedrine,ephedrine) 加藤 信 1-4.メチルフェニデート(Methylphenidate:MPD) 鈴木利人,新井平伊 1-5.大麻(カナビス,ハシッシ) 妹尾栄一 1-6.ペンタゾシン 北林百合之介,岡 正悟,福居顯二 1-7.コカイン関連障害 氏家 寛 1-8.アヘン剤 竹林 実 1-9.有機溶剤 尾崎 茂 1-10.LSD,その他幻覚剤など(psilocybinなど) 永井 宏 1-11.フェンシクリジン 岩間久行 1-12.MDMAほか脱法ドラッグ 妹尾栄一 1-13.ベンゾジアゼピンを含む鎮静・睡眠薬 稲田 健,石郷岡 純 1-14.バルビツール酸による精神および行動の障害 伊賀淳一,大森哲郎 1-15.ニコチン(喫煙)による薬剤性精神障害 仙波純一2. 毒物 2-1.有機水銀中毒(organic mercury poisoning) 宮川太平,藤瀬 昇 2-2.その他の重金属中毒 綱島浩一 2-3.一酸化炭素中毒 山本理絵,鈴木陽介,市村 篤 他 2-4. PCB中毒 石丸昌彦3. ビタミン欠乏症 3-1.チアミン(ビタミンB1)欠乏(ウェルニッケ・コルサコフ脳症) 吉本博昭 3-2.その他のアルコールに関連する神経内科的症状(Marchiafava-Bignami病,central pontine myelinolysisを含む) 須藤 哲,和田有司 3-3.ナイアシン欠乏によるペラグラ 新藤和雅 3-4.ビタミンB12欠乏症(亜急性脊髄連合変性症) 田口朋広,中野今治 3-5.葉酸 三輪英人4. 非依存性医薬品 4-1.グルココルチコイド 中川 伸,小山 司 4-2.蛋白同化ホルモン 原 隆 4-3.経口避妊薬に由来する精神神経症状 油井邦雄 4-4.インターフェロン 鈴木映二 4-5.降圧薬 尾鷲登志美,上島国利 4-6.Lidocaine 玉置寿男,本橋伸高 4-7.ジギタリス 幸田るみ子,大坪天平 4-8.抗ヒスタミン薬の服用に伴う精神症状 宮地伸吾 4-9.抗がん剤 稲垣正俊,内富庸介 4-10.抗生物質 堀川直史,大村裕紀子,國保圭介 他 4-11.抗精神病薬による精神障害 伊藤千裕 4-12.抗うつ薬に由来する病態 渡部雄一郎,染矢俊幸 4-13.抗てんかん薬 松浦雅人 4-14.制吐剤による薬物性精神障害 仙波純一 4-15.抗パーキンソン薬 野田隆政,平林直次 4-16.非ステロイド系消炎鎮痛剤 和田 健第3章 脳に限定した疾病過程が明らかな外因に由来する病態1. 中枢神経系の感染疾患 1-1.単純ヘルペス脳炎 大久保 拓,新井平伊 1-2.その他の脳髄膜炎 大久保 拓,新井平伊 1-3.進行麻痺および梅毒感染症 長根亜紀子,鈴木利人,新井平伊 1-4.クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD) 高橋 正 1-5.脳膿瘍 宮川晃一,新井平伊2. 頭部外傷 2-1.頭部外傷による高次機能障害,精神症状 柴田展人,新井平伊 2-2.老人の頭部外傷(慢性硬膜下出血) 一宮洋介 2-3.児童の頭部外傷 菊地祐子,一宮洋介 2-4.減圧症 山田佳幸 2-5.ボクサー脳症(boxer's encephalopathy) 金子 稔3. 脳血管障害 3-1.多発性脳梗塞による認知症 馬場 元 3-2.くも膜下出血 景山春奈,木村通宏 3-3.高血圧性脳症 儀藤政夫,江渡 江 3-4.一過性脳虚血発作 今井兼久,井関栄三4. 片頭痛 城甲泰亮5. 一過性全健忘 荻原朋美6. 脳腫瘍 大東祥孝7. 正常圧水頭症 鬼頭 恆8. 脳脊髄液減少症 岡崎 翼第4章 脳に限定した特発性の疾病過程が認知症をもたらす病態1. 皮質性 1-1.アルツハイマー病 黄田常嘉,新井平伊 1-2.前頭・側頭型認知症(FTD) 池田研二 1-3.その他の非アルツハイマー型変性認知症 天野直二2. 皮質下性 2-1.レビー小体型認知症 井関栄三 2-2.パーキンソン病に伴う精神症状 森 秀生 2-3.皮質基底核変性症 岡田八束 2-4.進行性核上性麻痺 篠山大明 2-5.ハンチントン病 黒田重利 2-6.Hallervorden-Spatz症候群 新井信隆3. 精神症状をきたす脊髄小脳変性症 高橋竜哉第5章 てんかんに伴う精神症状・てんかんを主要な兆候の1つとする脳疾患1. 急性発作間欠期精神病(交代性精神病を含む)の治療 足立直人2. 発作後精神病 兼本浩祐3. 慢性てんかん性精神病 加藤昌明,大沼悌一4. Aura continua 本岡大道5. てんかん性不機嫌症 川崎 淳6. 人格特性(側頭葉てんかんにおけるGeschwind症候群とAufwachepilepsieにおける前頭葉障害を含む) 原 広一郎,松浦雅人7. 非けいれん性てんかん発作重積状態 伊藤ますみ8. 環状20番染色体 井上有史9. 獲得性てんかん性失語(Landau-Kleffner症候群) 森川建基10. 徐波睡眠時に持続性棘徐波を示すてんかん(CSWS症候群) 森川建基11. 進行性ミオクローヌスてんかん症候群(progressive myoclonic epilepsy syndrome:PME) 人見健文,池田昭夫12. MELAS(mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes) 井内盛遠,池田昭夫第6章 睡眠障害1. ナルコレプシー 神林 崇,兼子義彦,石川博康 他2. 睡眠時無呼吸症候群 若山英雄,塩見利明3. Kleine-Levin症候群 向井淳子,大川匡子4. 睡眠時遊行症(夢中遊行) 岡靖 哲,井上雄一5. 夜驚 井上雄一,岡靖 哲6. REM睡眠行動障害 内山 真7. 概日リズム睡眠障害 大川匡子,村上純一第7章 その他の児童期より発現する器質性精神障害を伴う疾患1. 先天性代謝異常 1-1.フェニルケトン尿症 十一元三 1-2.リピドーシス 岡田 俊 1-3.Lesch-Nyhan 症候群 小平かやの2. 染色体異常および染色体異常が疑われる疾患 2-1.Klinefelter症候群 村瀬聡美,尾崎紀夫 2-2.Turner症候群 渡辺慶一郎,金生由紀子 2-3.ダウン症候群 野邑健二 2-4.CATCH22症候群 小石誠二 2-5.Prader-Willi症候群 水野智之 2-6.Angelman症候群 橋本大彦 2-7.脆弱X症候群 小石慎子 2-8.滑脳症,その他の大脳異形成(脳梁欠損症を含む) 長尾圭造,高浜三穂子 2-9.レット症候群 石井 卓 2-10.結節性硬化症,その他の母斑症 飯田順三コラム・アメンチア 小高文聰,中山和彦・急性外因反応諸型 大島智弘,清水寿子,兼本浩祐・せん妄 田所ゆかり,兼本浩祐・コルサコフ症候群 小阪憲司・過敏情動性衰弱状態(hyperasthetisch-emotionelle Schwachezustand) 柴山雅俊・通過症候群 一宮洋介・もうろう状態(twilight condition, Dammerzustand) 大島智弘,兼本浩祐 鑑別覚書 兼本浩祐 | 6,490円 |
 三省堂書店オンデマンド星和書店 精神科治療学 Vol.32 No.8 Aug.2017 三省堂書店 | ◆内容紹介 ページ数:140ページ 【特集】「身体症状症および関連症群」の臨床・特集にあたって 仙波純一・身体症状症の概念 磯村周一,鬼塚俊明・DSM-5によって失われた身体症状症に関連する歴史的概念 野間俊一・身体症状症 宮地英雄・身体症状症,疼痛が主症状のもの(従来の疼痛性障害) 西原真理・病気不安症(従来の心気障害) 新里和弘・変換症/転換性障害(機能性神経症状症) 安田貴昭,倉持 泉,吉益晴夫・作為症/虚偽性障害 安藤久美子・DSM-5における身体醜形障害─その診断や臨床像を中心に─ 松永寿人,松井徳造,橋本 彩・自己臭恐怖症の臨床 塩路理恵子,谷井一夫,石山奈菜子・慢性疲労症候群 岡 孝和・線維筋痛症 芦原 睦,井上敦裕・医学的に説明困難な身体症状─MUS(medically unexplained symptoms)および FSS(functional somatic syndrome)─ 岡田宏基・身体症状症と精神分析 白波瀬丈一郎・身体症状症の認知行動療法 吉野敦雄,岡本泰昌,神人 蘭 他・「身体症状症および関連症群」の薬物療法 仙波純一〔オピニオン〕身体症状症と中枢性過敏症候群(あるいは線維筋痛症) 戸田克広研究報告・治療に難渋した抑うつ症状と幻聴に対して修正型電気けいれん療法が著効したレビー小体型認知症の1例 上田淳哉,袖長光知穂,浅利翔平 他臨床経験・強迫症患者の入院治療における多職種連携モデル─その有効性や留意すべき点について─ 向井馨一郎,林田和久,吉田賀一 他・資料 精神科病棟における超低体重神経性無食欲症の臨床的検討─2004年1 月から2013年12月まで10年間に経験した症例をもとに─ 齋藤慎之介,吉成美春,小林聡幸連載〔オピニオン〕・制度依存型スティグマ─現代の社会防衛─ 大西次郎 | 3,168円 |
 三省堂書店オンデマンド星和書店 精神科治療学第31巻08号 三省堂書店 | ◆内容紹介 【特集】 LGBTを正しく理解し,適切に対応するために・特集にあたって松本俊彦・LGBTと精神医学針間克己・LGBTの人権と医療東 優子・性別越境・同性間性愛文化の普遍性三橋順子・西洋精神医学における同性愛の扱いの変遷平田俊明・トランスジェンダーの歴史松永千秋・LGBTの医療と法山下敏雅・LGBTの生物学的基盤坂口菊恵・LGBTと認知行動療法石丸径一郎・ゲイ・バイセクシュアル男性のメンタルヘルスと自傷行為日高庸晴・トランスジェンダーと自傷・自殺─ライフステージを反映したリスクとその対策─松本洋輔・ゲイ・レズビアンと精神療法林 直樹・レスビアンと心理援助金城理枝・トランスジェンダーと精神療法康 純・LGBTにおけるHIV 感染症と薬物依存嶋根卓也・解離・トラウマとLGBT塚本 壇・LGBTの就職活動─約13人に1人の求職者のためにできること─藥師実芳・トランスジェンダー生徒の支援土肥いつき・回復とトランスジェンダー倉田めば・性的マイノリティのリプロダクティブ・ヘルス/ライツ中塚幹也・発達障害とLGBT中山 浩研究報告・プライマリケアでのうつ病診療における協同的ケアの有用性の検討安田貴昭,五十嵐友里,堀川直史 他臨床経験・統合失調症にパーキンソン病を併発し抗パーキンソン病治療にて運動症状・精神症状とも著明な改善を呈したケース林 眞弘,東 光太郎,堺 奈々資料・長期通院てんかん患者における臨床的特性─続報─和田一丸 | 3,168円 |
 三省堂書店オンデマンド 星和書店 臨床精神薬理16-11 三省堂書店 | ◆内容紹介 ページ数:152ページ 【特集】 拒薬・服薬困難患者への対応 ・統合失調症入院患者における拒薬とその治療的対応三澤 史斉・ケア対象者のリカバリーを支える服薬支援と看護師の役割大橋 明子,萱間 真美・認知症患者の拒薬に対する治療的対応櫻井 博文,羽生 春夫・救急医療の現場における昏迷,拒食,拒薬八田耕太郎・拒薬・嚥下困難などの患者に対する剤形の選択吉尾 隆・精神科医療における強制医療は許されるか? 北村 俊則,北村 總子・<症例報告>教育入院により拒薬と再入院の繰り返しから服薬と通院が可能になった統合失調症の1例渡部 和成 | 3,190円 |
 三省堂書店オンデマンド星和書店 こころのりんしょう a・la・carte 第28巻02号 三省堂書店 | ◆内容紹介 《今回の特集:解離性障害》 複雑化する人間関係・社会の中で増え続けているといわれている解離性障害。 その多彩な症状とはどんなものなのか?対処法は? 本特集では、交代人格や健忘、離人などの個々の症状についてその原因や治療法などをわかりやすく解説。 また、トラウマ、虐待、脳科学、解離判定法などをめぐって最新の知見も紹介する。 解離性障害の正しい理解、より効果的な患者さんのケアのための情報が満載。 【特集】解離性障害 ・特集にあたって 岡野憲一郎,柴山雅俊,奥田ちえ 第1部 解離性障害 Q&A集 Q1解離という言葉の語源は? 誰が,いつごろ,命名したのでしょうか? Q2解離とは,どのような症状,あるいは現象をいうのでしょうか? Q3解離は,誰にでもみられるでしょうが,どうなると障害ということになるのでしょうか? Q4解離性障害という疾患名は,いつごろから使われるようになったのでしょうか? Q5解離性障害は,どのような原因で起こると考えられていますか? Q6解離性障害は虐待やレイプなど心的外傷(トラウマ)体験と関係があるでしょうか? Q7憑依現象,神懸り,狐憑き,幽体離脱などは,解離性障害の一種と考えられますか? Q8宗教儀礼で見られる「トランス」は解離性障害でしょうか? Q9解離性障害は,文化や時代と関係があると考えられますか? Q10白昼夢をみる,空想にふけることは解離性障害の一種ですか? Q11解離性障害は増えたといわれますが本当に増えているのでしょうか? 増えているとしたら,その原因は? また,日本にいまどれぐらい解離性障害の患者がいるのでしょうか? Q12リストカットなど自傷行為をしているときは,解離状態にあるのでしょうか? Q13患者さんには苦しみの実感はあるのでしょうか? それは周囲には伝わりにくいものでしょうか? Q14プチ解離といわれるような一過性の解離現象が多く見られるようですが。またプチ解離とBPDは,一見似ているように見えますが,違いを説明してください。 Q15高機能広汎性発達障害に解離症状が見られることはありますか? Q16ガンザー症候群とは何ですか? Q17解離性障害はパーソナリティ障害と関係がありますか? 他の精神疾患と併発することがありますか? Q18解離性障害に幻覚や妄想がみられるとしたら,どんな症状でしょうか? Q19解離性障害と詐病は,どこで見分けられますか? Q20解離性障害は男性と女性,どちらの割合が多いですか? また,その理由は? Q21家族に解離性障害の人がいる場合,自分も解離性障害になる可能性はありますか? Q22解離性障害(解離症状)は自分で抑制することができますか? Q23多重人格障害と解離性同一性障害は,同じでしょうか? Q24多重人格障害(MPD)は,実際に存在する精神障害でしょうか? 頭の中で勝手に作り上げられた虚構なのでしょうか? Q25解離性同一性障害が,治療関係の中で誘発される,あるいは過剰に診断される可能性はありますか? Q26解離性同一性障害において,患者さん自身あるいは治療者が,それぞれの人格を把握するにはどのようにすればよいですか? Q27解離性同一性障害において,人格の統合はどのように進めればよいですか? Q28解離性同一性障害の患者さんで,人格の1人が触法行為をした場合,責任の所在はどうなるのでしょうか? Q29解離性同一性障害の患者さんの人格のうち,患者さんに危害を加えるような(自傷や自殺行為をする)人格がいる場合の対応を教えてください。 Q30「想像上の仲間(Imaginary Compan-ion)」と解離性同一性障害にみられる「人格」とはどのように違うのですか? Q31「想像上の仲間(Imaginary Compan-ion)」をもつ若者が増えているといわれます。ネット上のサイバー空間ゲームとの関係が考えられないでしょうか? Q32器質的な原因による記憶障害と,解離性障害による記憶障害の違いを教えてください。 Q33解離性障害の発症に,好発時期(年齢)はありますか? Q34思春期など成人以前に発症した人と,成人後に発症した人では,解離性障害の症状・程度などに違いがみられますか? Q35解離性障害をもつ患者さんの家族や友人は,どのような対応を心がければよいですか? Q36解離性障害の治療に,EMDRは有効ですか? Q37解離性障害の治療法にはどんなものがありますか? 解離性障害の治療には入院が必要ですか? Q38解離性障害に有効な薬物はありますか? Q39解離性障害の患者さんとの面接,治療に際して,留意すべきポイントを教えてください。 Q40解離性障害は,回復するものでしょうか? その場合,実際にどれくらい回復しているのでしょうか? Q41解離性障害は再発することはありますか? Q42解離性障害の診断にあたって,特に留意すべき点を教えてください。 Q43解離性障害の患者さんのための自助グループや家族会などはありますか? Q44解離性障害に関する参考文献・研究データ・ウェブ上のサイトなどで,これはぜひ読んでおくべきというものをご推薦ください。 Q45解離性健忘とは,どのような障害ですか? Q46解離性遁走とはどのような障害ですか? Q47離人症性障害とは,どのような障害ですか? Q48解離性昏迷とはどのような障害ですか? Q49解離性障害ではどのような身体症状がみられますか? Q50ヒステリーと解離性障害(特に解離性転換障害)は,違うものですか? 第2部 ・〈座談会〉解離性障害によりよく対応するために—その出会いから症候学まで— 岡野憲一郎,柴山雅俊,奥田ちえ,野間俊一 ・解離研究の歴史 野間俊一 ・病的解離性のDES−Taxon簡易判定法—解離性体験尺度の臨床的適用上の工夫— 田辺肇 ・解離性障害と犯罪 松本俊彦 ・子ども虐待と解離—発達精神病理学的視点から— 白川美也子 ・現代社会と解離—仮面とヴェール— 柴山雅俊 ・トラウマと解離—PTSDの外側と内側— 金吉晴 ・脳科学から見た解離—そのスイッチングのメカニズムについて— 岡野憲一郎 ・構造的解離理論の基本概念と治療アプローチ 奥田ちえ ・解離性障害の疫学と虐待の記憶 岡村毅ほか ・〈生き残る〉ということ—対処反応としての解離性障害— 大矢大 【特別寄稿】 ・「パターン」と意識障害のアトラス—解離の理解のために— 安永浩 【連載】 ・アメリカ こころの臨床ツアー 第2回 丹野義彦 ・認知療法NEWS 第49号 ・日本EMDR学会ニューズレター 第18号 ・NPO法人 日本トゥレット協会会報 第24号 ・バックナンバー案内 | 2,200円 |
 三省堂書店オンデマンド星和書店 精神科治療学 第22巻04号 三省堂書店 | ◆内容紹介 【今月の特集:いま「解離の臨床」を考える II】 前号に引き続き「解離」について特集。うつ病やアスペルガー障害など、時に解離症状がみられる疾患への対応や、解離の評価尺度について取り上げた。 またフロイト、ジャネ、パトナムがそれぞれ提唱した解離(転換)論の理論的背景を探る。 【特集】 いま「解離の臨床」を考える II ・うつ病における解離 阿部隆明 ・解離と性同一性障害 古橋忠晃 ・アスペルガー障害と解離 野邑健二 ・てんかんと解離 深尾憲二朗 ・外傷性記憶と解離 金 吉晴、栗山健一 ・解離性の尺度化と質問票による把握 田辺 肇 ・なぜフロイトは解離ではなく転換を選んだか 渡邉俊之 ・ジャネと解離 江口重幸 ・解離性同一性障害の解離性障害における位置づけ—解離現象の連続体モデルと類型学的モデル— 岩井圭司、小田麻実 【研究報告】 ・境界性人格障害患者に対する精神療法の2例—漠然とした認知・コミュニケーション様式の改善に注目して— 小羽俊士、濱田馨史、上村 綾 【臨床経験】 ・急速に感染症が重症化し、救命救急センターとの連携により救命した神経性無食欲症の2症例 三宅典恵、高畑紳一、斎藤 浩 他 【総説】 ・社会不安障害に対する有効な治療法の展望—脳画像研究の観点から— 岡島 義、金井嘉宏、金澤潤一郎 他 【カレント・トピックス】 ・触法精神障害者の処遇—英国の制度から学ぶ— 吉川和男 【連載】 〔精神科治療:私の小工夫〕 ・高齢者との会話を発展させ理解を深める試み—高齢者デイケアにおける「質問表」と「ミニ自分史」の作成— 河本純子 〔体験を聴き、症候を読む〕第13回 第II部 症候を読み解く:精神症候から病態心理へ—精神症候学の方法についての覚書— ・第6章 逆ジャクソニズムという考え方(その1)—症候は騙されて作られる— 中安信夫 〔向精神薬—リスク&ベネフィット—〕 ≪比較対照試験≫Donepezil hydrochloride(アリセプト(R))の大腿骨頭置換術後せん妄の発症予防効果:無作為抽出二重盲検プラセボ比較研究 岸 泰宏 | 3,168円 |
 三省堂書店オンデマンド星和書店 精神科治療学Vol.24 増刊号 精神療法・心理社会療法ガイドライン 三省堂書店 | ◆内容紹介 精神療法・心理社会療法の基本的な考え方、各種技法について、編集委員会の総力を挙げた本邦初のガイドライン。 わが国で実践されている各種治療技法を30余紹介し、続いて精神障害別に各種の技法を網羅し、加えて、今日的な問題も踏まえ、希死念慮、がん患者、妊婦、AIDS患者、暴力の意図・殺意をもつ患者などへの対応や、さまざまなカウンセリング場面での特殊病態についても紹介。 精神科外来、病棟ですぐに役立つ、実践に直結した簡便な指南書。精神科医のみならず、臨床心理士やコメディカルスタッフの方々にも役立つ。 発刊にあたり 加藤 敏 第I部 総論 1.治療同盟、医師-患者関係 加藤敏 2.面接空間、治療者の態度、服装 大森健一 3.陽性転移、陰性転移 鈴木國文 4.プラセボ効果—暗黙に作動する精神療法過程— 竹村隆太 5.精神療法・心理社会療法の脳基盤—言語による脳機能の自己制御— 福田正人、八幡憲明、須田真史ほか 6.倫理的配慮 狩野力八郎 7.面接、その始まりから終結まで 牛島定信 第II部 各論 1.技法の各種 1) 支持的精神療法(の前提と目指すところ) 人見一彦 2) 力動的精神療法・精神分析の前提とめざすところ 藤山直樹 3) ユング派精神療法 武野俊弥 4) 心理社会療法 角谷慶子 5) 認知・行動療法(の前提と目指すところ) 大野 裕 6) コミュニティ強化アプローチと家族トレーニング 岡嶋美代、原井宏明 7) 森田療法の前提と目指すところ 北西憲二、中村 敬 8) 集団療法の前提と目指すところ 増野 肇 9) 人間学的精神療法 山中康裕 10) 内観療法 吉本博昭 11) 絶食療法 本郷道夫、田村太作、橋田かなえ 12) 臨床動作法 鶴 光代 13) 思考場療法(TFT) 中口智博 14) 自律訓練法 坂入洋右、佐々木雄二 15) ロゴセラピー 吉田香里 16) フォーカシング指向心理療法 池見 陽 17) 交流分析 芦原 睦、山内麻利子 18) ナラティヴ・セラピー 小森康永 19) 遊戯療法 伊藤良子 20) コミュニティ・ミーティング 相田信男 21) エンカウンター・グループ 野島一彦 22) システムズアプローチ 坂本真佐哉、東 豊 23) 絵画療法について 中村研之 24) コラージュ療法 大澤卓郎 25) 箱庭療法 弘中正美 26) 音楽療法 山下晃弘 27) 詩歌療法 飯森眞喜雄 28) サイコドラマ 高良 聖 29) アニマル・セラピー 横山章光、石坂奈々 30) ダンス/ムーブメントセラピー 宮城 整、遊佐安一郎 31) 異文化間精神療法—「身分けされた文化」を導きとして— 大塚公一郎 32) 認知機能リハビリテーション 岩田和彦 2.精神障害別 1) パニック障害・不安障害 1 薬物療法との統合、薬物療法の不要な病態を導く 岸本年史 2 認知行動療法 井上和臣 3 力動的精神療法 狩野力八郎 4 パニック障害の森田療法 中村 敬 5 グループ療法 坂野雄二 2) 解離性(転換性)障害(身体表現性障害) 1 力動的精神療法 柴山雅俊 2 身体医学的に説明できない症状の認知行動療法 菊池安希子 3 支持的精神療法 水田一郎 3) 強迫性障害 1 力動的精神療法 成田善弘 2 認知行動療法 島田達洋 3 強迫性障害の森田療法 中村 敬 4 (患者に対する)家族の接し方、対応 成田善弘 4) 気分障害(うつ病) 1 薬物療法との統合、薬物療法が不要な病態 坂元 薫 2 力動的精神療法(精神分析的精神療法) 小川豊昭 3 支持的精神療法 井原 裕 4 認知行動療法 福本 修 5 対人関係療法(IPT) 水島広子 6 うつ病の夫婦療法 中村伸一 7 グループ療法 岡島美朗 8 家族の接し方、対応 内海 健 9 職場連携 中西幸子、荒井 稔 5) 統合失調症 1 薬物療法との統合 江畑敬介 2 急性期の精神療法的対応 小林聡幸 3 ソテリア・アプローチ 花村誠一 4 支持的精神療法 加藤 敏 5 ACT 高木俊介 6 統合失調症の認知行動療法 石垣琢磨 7 統合失調症の作業療法 鈴木國文 8 デイケア 福智寿彦 9 心理教育 白石弘巳 10 社会生活技能訓練(SST) 天笠 崇 11 グループ療法(集団精神療法) 池田真人 12 自助グループ 白石弘巳 13 統合失調症の患者に対する家族の接し方・対応について 平山正実 14 統合失調症の職場連携 島 悟 15 地域連携 野口正行 6) 摂食障害 1 精神療法的アプローチ 切池信夫 2 構造化入院治療 永田利彦、山田 恒、切池信夫 3 認知行動療法 切池信夫 4 摂食障害の家族療法 中村伸一 5 力動的精神療法 館 直彦 6 グループ療法 野間俊一 7 (患者に対する)家族の接し方、対応 浜垣誠司 7) 境界性パーソナリティ障害 1 境界性パーソナリティ障害に対する支持的精神療法 大島一成 2 力動的精神療法 牛島定信 3 弁証法的行動療法 坂野雄二 4 境界性パーソナリティ障害に対するグループ療法 大島一成 5 境界性人格障害の家族療法 中村伸一 6 悪性転移の対応 加藤 敏 7 治療しないアプローチ 加藤 敏 8) 反社会性人格障害と非行に対する精神療法・心理社会的療法ガイドライン 西口芳伯 9) PTSD 1 PTSDの認知行動療法 金 吉晴 2 EMDR(眼球運動による脱感作と再処理法) 中口智博 3 被虐待児の生活・集団処遇 小池純代 10) 認知症 1 行動療法的プローチ・環境調整 繁信和恵、池田 学 2 回想法 黒川由紀子 3 作業療法 上城憲司、小川敬之、荻原喜茂ほか 11) 物質依存性障害 1 認知行動療法 松本俊彦 2 薬物依存症の集団療法—埼玉県立精神医療センターでの取り組み— 松崎陽子、成瀬暢也 3 家族療法 小林桜児 4 自助グループ 宮永 耕 5 依存症者をもつ家族に対する支援介入 近藤あゆみ 6 併存性障害をもつ薬物依存患者へのアプローチ 森田展彰 12) アルコール依存 1 久里浜方式 遠藤光一、樋口 進 2 精神療法 芦沢 健 3 アルコール依存のセルフヘルプ・グループ 比嘉千賀 13) 希死念慮をもつ患者、自殺企図患者 1 支持的精神療法 岡島美朗 2 自殺の危険の高い患者に対する精神療法的アプローチ 高橋祥友 3 認知行動療法 水野康弘、張 賢徳 4 家族への接し方 高橋祥友 14) 遺された家族のグリーフワーク 平山正実 15) 腫瘍患者 1 スピリチュアル・ケア (1)ディグニティセラピー 明智龍男 (2)グループ療法 保坂 隆 16) 妊産婦の精神障害 吉田敬子 17) HIV感染症における心理療法 赤穂理絵 18) 疼痛性障害 1 疼痛性障害への精神分析的アプローチ 丸田俊彦 2 認知行動療法 本田哲三、高橋理夏 19) 性機能障害 1 行動療法 阿部輝夫 2 夫婦(あるいはカップル)カウンセリング 大川玲子 20) 病的賭博(ギャンブル依存) 1 初期診断から洞察的精神療法へ 河本泰信 2 病的賭博(ギャンブル依存症)の集団療法と自助グループ 田辺 等 21) 自閉性障害 1 TEACCH 大隈紘子 2 自閉症における応用行動分析学からのアプローチとそのエビデンス 井上雅彦 3 教育支援 東條吉邦 4 自閉症スペクトラム障害の人に対する家族の接し方と対応 小泉晋一、辻井正次 5 家族支援 田中康雄 6 学校との連携 小林潤一郎 7 職場との連携 梅永雄二 22) 登校拒否、ひきこもり 1 精神療法 青木省三、松下兼宗、和迩大樹 2 家族への対応 青木省三、松下兼宗、和迩大樹 3.特殊場面の対応 1) 他人への暴力の意図、殺意を述べる患者への対応 辻 恵介 2) 暴力への対処 中村 満、一瀬邦弘 3) スクールカウンセリング 森岡由起子 4) 産業カウンセリング、EAP 廣 尚典 5) 遺伝カウンセリング 小久保 勲、尾崎紀夫 6) アスペルガー症候群と職場連携 黒木宣夫 7) セクシュアル・ハラスメント被害者への対応 加茂登志子 | 6,490円 |
 三省堂書店オンデマンド星和書店 精神科治療学 第30巻03号 三省堂書店 | ◆内容紹介 【特集】 自殺予防と精神科臨床—臨床に活かす自殺対策—I・特集にあたって松本俊彦・自殺のリスク評価における睡眠問題の意義—心理学的剖検から見えてきた自殺予防のヒント—小高真美・自殺のリスク評価において何に注意すべきか—警察庁データを用いたネットワーク分析から見えてきたこと—白鳥裕貴,太刀川弘和・自殺のリスク評価において何に注意すべきか —消防庁および地方自治体の自損行為データから見えてきたこと—山内貴史,奥村泰之,白川教人 他・向精神薬の過量服用は安全なのか—監察医務院から見えてきた自殺の実態—福永龍繁,谷藤隆信,鈴木秀人 他・自殺念慮のアセスメント—CASEアプローチ— 松本俊彦・対人関係理論に基づく自殺のリスク評価松長麻美,北村俊則・自殺未遂者の初期介入で必要なスキル山田素朋子・複合的自殺対策プログラムの自殺企図予防効果に関する地域介入研究NOCOMIT-J大野 裕・自殺未遂者の再企図予防で重要なもの—ACTION-Jの成果からみえてきたもの—平安良雄,河西千秋・若年者に対する自殺予防のヒント—英国と豪州における実践から— 勝又陽太郎・性的マイノリティの自殺予防日高庸晴,古谷野淳子・自殺予防とメディア—ウェルテル効果とパパゲーノ効果— 太刀川弘和・コミュニティにおける自殺予防因子を考える—自殺希少地域の研究から— 岡 檀・鉄道自殺の現状と予防策松林哲也,澤田康幸,上田路子・宗教は自殺予防に資するのか—日本人と自殺— 島薗 進,堀江宗正・精神科臨床において知っておくべき自死遺族の心理とニーズ白神敬介,川島大輔,川野健治研究報告・人前での行為不安を訴える社交不安障害に対するベンゾジアゼピン系薬物およびβ遮断薬のas-needed useの治療経験多田幸司臨床経験・反復性短期うつ病性障害にlithiumとlamotrigine併用療法が奏効した2症例大竹民子,松田明子,樋口鎮実慢性疼痛に対して,duloxetineを使用した2症例竹内大輔,小野壽之,長谷浩吉 他連載〔付添人の窓—弁護士の見た医療観察法—〕(新連載・第1回)・「付添人は人生の伴走者」の掛け声とともに伊賀興一〔DSM-5をどう見るか?〕(第11回)・私はDSM-5の双極性障害をこう見る仁王進太郎 | 3,168円 |
 三省堂書店オンデマンド星和書店 精神科治療学 第22巻03号 三省堂書店 | ◆内容紹介 【今月の特集:いま「解離の臨床」を考える I】 近年、ちょっとしたきっかけで出現する一過性の退行や解離現象(“小”解離)を呈する患者が増えている、という臨床現場の印象を踏まえ、特集した。 薬物療法的にも精神療法的にも取り扱いの難しい面がある解離現象へのアプローチの一助となる特集。 ■第3回「精神科治療学賞」発表 【特集】 いま「解離の臨床」を考える I ・特集にあたって 兼本浩祐 ・解離と解離性障害—変遷と症候学— 船山道隆、濱田秀伯 ・解離性障害の精神療法 木村宏之 ・今日的な全生活史健忘 大矢 大 ・解離という言葉とその裾野—「リスカ」「OD」「プチ解離」— 兼本浩祐、多羅尾陽子 ・解離と“Imaginary Companion”—成人例について— 大饗広之、浅野久木 ・解離と「霊体験」 千丈雅徳 ・サイバースペースと解離 澤 たか子 ・解離と攻撃性 大饗広之 ・離人症と解離 大東祥孝 ・境界人格障害と解離 岡野憲一郎 ・解離をめぐる青年期症例の治療—解離性自傷患者の理解と対応— 松本俊彦 【研究報告】 ・老年期の不安・焦燥型うつ病にみられる演技的、退行的行動について 上田 諭、小山恵子、黒田裕子 他 【臨床経験】 ・統合失調症患者にみられる「逃げ」—「その場性」に基づく理解の試み— 中嶋 聡 ・抗精神病薬によるQT延長のため投薬調整を余儀なくされた統合失調感情障害の一例 吉澤 一、白川 治、竹内克吏 他 【資料】 ・最近の過量服薬者の傾向について—国立国際医療センターのデータより、5年前のものと比べて— 三澤 仁、加藤 温 【連載】 〔体験を聴き、症候を読む〕第12回 第II部 症候を読み解く:精神症候から病態心理へ—精神症候学の方法についての覚書— ・第5章 自己保存本能の果たす役割—症候は「自己保存の危機」によっても形作られる— 中安信夫 〔向精神薬—リスク&ベネフィット—〕 ・≪精神腫瘍学≫神経因性疼痛を有するがん患者における抗てんかん薬と三環系抗うつ薬の使用状況 大西秀樹 | 3,168円 |
 三省堂書店オンデマンド 星和書店 治療の聲 第09巻01号【特集】安克昌の臨床世界 三省堂書店 | ◆内容紹介 ページ数:104ページ 【特集】安克昌の臨床世界・特集にあたって杉林稔・付——安克昌主要論文リスト・[座談会]安克昌の臨床世界杉林稔,田中究,岩尾俊一郎,岩井圭司,大山朗宏,胡桃澤伸,青山慎介,増元康紀・安克昌先生と私中井久夫・安克昌君の存在を回顧する山口直彦・まず社会の品格と社会の正義とを求めよ——安克昌さんから学び続けたいこと——川本隆史・国際トラウマ解離学会で安さんを想う宮地尚子・「安さん」との時間白川美也子・臨床の神が降りてくるのだ高木俊介・安克昌先生,1995年,仙台岡崎伸郎・安克昌先生のこと——神戸のこと,阪神大震災のことを思い出して——吉岡眞吾・安克昌先生とのこと——夜空の星と内なる道徳律——小川恵・それはシゾフレニーから始まった岩井圭司・安先生の言葉胡桃澤伸・宿題田中究・[講演]解離のルーツをたずねて〜ジャネを中心に〜松本雅彦【治療の聲】・「他者」に気づき関わるケア環境をマネージメントする——6年間自宅に引きこもっていた少女から学んだこと——葛西康子,土田佳織,小川裕佳,笠谷千尋・トラウマからのプロセスという観点で,様々な病的状態の諸相を見直す三好典彦,川本立夫【特別講義】中井久夫,描画症例を語る——暗闇を歩く天使——・中井久夫 | 3,080円 |
 三省堂書店オンデマンド星和書店 こころのりんしょう a・la・carte 第27巻01号 三省堂書店 | ◆内容紹介 【特集】子どものチックとこだわり編集 金生由紀子,宍倉久里江・特集にあたって 金生由紀子第1部 子どものチックとこだわり Q&A集Q1. チックとは何ですか?Q2. チックという名前は何に由来しているのですか? 何かの略称ですか?Q3. チックの症状と,いわゆる「癖」とはどこが違うのでしょうか?Q4. 子どもにチックが起こるのは,育て方がいけなかったので しょうか?Q5. チックはそのうちに治ると言われたのになかなかなくなりませんが,いつまで待ったらよいのでしょうか?Q6. チックと診断される症状には主にどのようなものがありますか?Q7. 複数のチック症状が同時におこることもあるのですか?Q8. 運動性チックとは何ですか?Q9. 音声チックとは何ですか?Q10. チックについて調べていたら,『トゥレット症候群』という 言葉が出てきました。トゥレット症候群とは何ですか?Q11. チック障害にはトゥレット症候群とは異なるものもあるのですか?Q12. チックやトゥレット症候群の原因に遺伝は関係がありますか?Q13. チックやトゥレット症候群の発症率は,男子と女子でどちら に多い傾向がありますか?Q14. チックやトゥレット障害に併発する病気・障害などはありますか?Q15. チックが始まってから落ち着きがなくなったようなのです が,関係はありますか?Q16. チックのある子は登校できなくなることが多いと聞きました が,本当ですか?Q17. チックやトゥレット障害に効果のある治療方法はありますか?Q18. チックやトゥレット症候群についての研究や最近の知見を教 えてください。Q19. チックのことで相談に行った病院で,精神科の薬を処方されました。小さな子どもに精神薬を飲ませるのは抵抗があるのですが,どうしても飲ませなければいけませんか?Q20. チックやトゥレット症候群に対して,精神療法(心理療法) は有効ですか?Q21. チックやトゥレット症候群のある子どもへの接し方や育て方について教えてください。Q22. 子ども自身が納得するように,チックやトゥレット症候群について説明をする方法を教えてください。Q23. チックが始まった頃に比べて,最近症状が増えてきています。このままひどくなる一方なのでしょうか?Q24. 眠っている間はチックの症状が起こらないようです。起きている間だけ,わざとやっていることなのでしょうか?Q25. チックの症状を止めさせてはいけないと言われましたが,ほんとうに自分の意思で止めることはできないのですか?Q26. 叱るとチックがひどくなるようです。チックのある子どもを叱ってはいけないのですか?Q27. 我が家の子どもでチックがある子は1人だけなのですが,他の兄弟がその症状を見て真似をします。真似ているうちに本当のチックになってしまわないでしょうか?Q28. チックのせいで,イジメに遭うのではないかと心配です。幼稚園や保育園,児童館などには行かせない方がよいでしょうか?Q29. チックについて友達からからかわれるので学校に行きたくないと子どもが言っています。どうしたらよいでしょうか?Q30. 最近チックがひどくなってきて,通っている学校から他の生徒の迷惑になるといわれてしまいました。どうしたらよいでしょうか?Q31. チックのある子どもは,どのような学校に行ったらよいので しょうか?Q32. チックがひどくなってきたら,壁に頭をぶつけるなど,危険な行為をするようになってしまいました。よい対処方法を教えてください。Q33. 子どもが,ある時期から突然,特定の「こだわり」・繰り返し行動を始めました。これまでの健診では問題はないと言われてきたのですが,これは何かの病気なのでしょうか?Q34. 子どもの行動を見た知人に「この子は強迫性障害では?」と言われました。強迫性障害とは何ですか?Q35. 強迫性障害は大人の病気だと聞きましたが,子どもでも発症するのですか?Q36. 「こだわり」のある子でこわがりが問題になることがありますが,関係があるのでしょうか?Q37. 「こだわり」や強迫行動のある子どもへの適切な接し方を教えてください。Q38. 「こだわり」が強くなるとともに母親から離れにくくなったのですが,どう対応したらよいでしょうか?Q39. 子どもが,「外はバイキンがいて不潔だ」と言って外に出ようとせず,家族にも外出するなと言います。家族は子どもの言うとおりにすべきなのでしょうか?Q40. 子どもが,「こだわり」のために決まったものしか食べません。健康診断では問題がないのですが,将来の成長が心配です。Q41. 子どもが,家の中にものがいつもきまった位置にないとパニックを起こします。パニックにどのように対応したらよいでしょうか?Q42. 子どもに,「食事の前には手を洗う」と教えたところ,手の皮がむけるほど洗います。無理やり止めたほうがよいでしょうか?Q43. 強迫性障害の子どもに認められる強迫症状にはどのようなものがあるか教えてください。Q44. 子どもの「こだわり」や強迫症状を,薬で治すことはできるのですか?Q45. 子どもの「こだわり」や強迫症状には,「行動療法」が有効だと聞きました。どのような治療法なのか,教えてください。Q46. 強迫性障害の治療には「曝露反応妨害法」が薬と同じくらい効果があると聞きました。どのような治療法なのか,わかりやすく教えてください。Q47. 自閉症の症状の1つに「こだわり」があると聞きましたが,「こだわり」のある子は自閉症の可能性があるのでしょうか?Q48. 自閉症やADHDではチックや「こだわり」が一般よりも 起こりやすいのでしょうか?Q49. チックや「こだわり」の目立つ発達障害には特別な対応が必要でしょうか?Q50. 子どものチックや強迫性障害に関する書籍やインターネットサイト,親の会などがあったら教えてください。第2部 ・〈座談会〉子どものチックとこだわり金生由紀子,笠原麻里,細田のぞみ,中釜洋子,宍 倉久里江・チックの子どもへの小児科での対応——比較的軽症なチックの子を小児科でどうあつかうか——星加明徳・トゥレット症候群の重症例への対応新井卓・小学生にみるチックとこだわり——教育相談の医診を訪れた例を通して——太田昌孝・地域密着型クリニックにおけるチックとこだわりへの診療新井慎一,新井理衣・子どもの強迫性障害の入院治療小平雅基・子どものこだわりへの認知行動療法下山晴彦・子どもの強迫の薬物療法宍倉久里江・チック・強迫の生物学的研究——特にトゥレット症候群について——田渕肇,加藤元一郎・トゥレット症候群の研究と治療の最近の動向金生由紀子・習癖とこだわり,チック小倉正義,本城秀次・トゥレット症候群と発達障害のcomorbidity——強迫性と衝動性の観点から——岡田俊【連載】・ロンドン こころの臨床ツアー 第4回丹野義彦・認知療法NEWS 第44号・NPO法人 日本トゥレット協会会報 第19号・バックナンバー案内 | 2,200円 |
 三省堂書店オンデマンド星和書店 実体験に基づく うつ病対処マニュアル50か条 三省堂書店 | 著者:田村浩二 うつ病を体験し、そして克服した著者が自ら語るうつ病対処法。うつ病の発症、通院、休職、職場復帰までの流れに沿って、役立つ鉄則を50か条にまとめています。実際にうつ病を体験した者でしか語れない、現実に即したうつ病克服のための鉄則は、うつで苦しんでいる人にとって希望の光となるでしょう。 | 1,430円 |
 三省堂書店オンデマンド 星和書店 絵とき精神医学の歴史 三省堂書店 | 内容紹介 絵とき精神医学の歴史 古代ギリシアから21世紀の今日までつづく精神医学の歴史を、大きな挿絵入りの見開きで、通覧しやすくまとめた一冊。平易ながらも凝縮された内容で、専門教養書として最適である。 ・エスプレッソ・ブック・マシーンによって製本された書籍です。 ・表紙はソフトカバーです。 ・装丁がオリジナル書籍とは異なりますのでご了承くださいませ。 | 2,860円 |
 三省堂書店オンデマンド 星和書店 精神科臨床サービス10-3 三省堂書店 | ◆内容紹介 ページ数:148ページ 【特集】 家族のリカバリーをどう支援するか ・特集にあたって 上野容子第1章 総論:今、求められる家族支援とは?・なぜ家族支援か:「援助者としての家族」支援から、「生活者としての家族」支援、そして家族のリカバリー支援へ 大島 巌・家族が期待する支援 川崎洋子・あるべき家族支援サービスネットワーク:英国の家族支援の動向 伊勢田堯、岡崎祐士、針間博彦、西田淳志第2章 家族同士による支えあいの工夫・家族会の維持と運営:情報機器利用のコミュニティづくり 岡嵜清二・家族による相談支援 飯塚壽美・家にひきこもりがちな精神障害者への訪問活動、居場所の提供 小松正泰・家族による家族学習会プログラム 岡田久実子・「兄弟姉妹の会」における支え合いの工夫はピアな関係性から 神谷かほる第3章 家族支援ネットワーク:それぞれの現場における考え方と実践・精神科診療所から発展した家族支援のネットワーク 上ノ山一寛、上ノ山真佐子・訪問による家族支援の新たな方向性 英一也、伊藤順一郎・入院という状況での家族支援 伊藤順一郎、山本啓太、堀内亮、青木和貴、田島瑛子、小河原麻衣、宮地麻美・福祉についての相談支援:兵家連の相談事業 本條義和・地域における自殺関連相談への対応:本人・家族支援ネットワークのために 黒澤美枝・ボランティアによる家族支援 岩崎廣司第4章 専門家が知っておきたい基本技術・家族支援における家族との関係づくり:家族心理教育プログラムに参加した家族の事例を通して 中岡恵理・家族成員(親であるか、きょうだいであるか、など)によるアプローチの違い 馬場安希・家族同士の支え合いの意義と専門家による支援方法 蔭山正子・ひきこもりケースの家族支援 近藤直司、?原和子、太田咲子・心理教育(1):家族グループへの心理教育プログラム 渡邉真里子・心理教育(2):個別家族への心理教育的面接 坂本明子・心理教育(3):訪問による家族心理教育 下寺信次第5章 家族が知っておきたいノウハウ・スティグマにどう対処するか 野村忠良・本人や家族にとって、どういう支援が望ましいか 高橋明紀代・家族にとって何が最良か 竹内政治第6章 こんなご家族へはどのような支援ができるか・精神科訪問看護における利用者の家族への支援 井上 新・医療観察法対象者の家族支援の取り組み:家族が健康を回復するために必要な支援を探って 望月和代、澤下靖典、佐野恵理、新納美美、大澤晶人・自殺で遺された家族 川野健治連載・学説と現実との隙間/〈第3回〉人生の通過症候群としての精神疾患 蟻塚亮二・白衣を捨てよ、町へ出よう/〈第1回〉アウトリーチサービスによる支援:家族支援も視野に入れて(1) 伊藤順一郎 | 2,420円 |
 三省堂書店オンデマンド星和書店 憑依の精神病理 -現代における憑依の臨床- 三省堂書店 | ページ:240頁 臨床医である著者が、自らが経験してきた憑依の患者さんを振り返り、「憑かれた状態」でさまざまな言動を示す場合を中心に取り上げている。精神医学という方法で「憑依現象」を解き明かした名著。 | 2,937円 |
 三省堂書店オンデマンド 星和書店 精神疾患100の仮説 三省堂書店 | 内容紹介 精神疾患100の仮説 改訂版 精神医学では疾患の仮説の数は極めて多く、本書ではこれらを百科事典的に100に集約。それぞれの仮説について根拠、限界、関連仮説に分けて解説する。研究・診療の指針づくりに最適の書。 ・エスプレッソ・ブック・マシーンによって製本された書籍です。 ・表紙はソフトカバーです。 ・装丁がオリジナル書籍とは異なりますのでご了承くださいませ。 | 4,950円 |
 三省堂書店オンデマンド星和書店 こころのりんしょう a・la・carte 第25巻02号 三省堂書店 | ◆内容紹介 《今回の特集:アスペルガー障害》 アスペルガー障害とは、よく知られる精神病、人格障害、"こころの病"(心因性疾患)のいずれとも違う、生まれつきの素質による独自の精神生理学的特徴を指します。 自閉症との類似は有名ですが、アスペルガー障害では「対人相互性の問題」があまり目立たず、誤診による混乱が多いのが現状です。 今では医療・教育・心理関係者に加え、福祉、就労、司法の領域でも、その知識は不可欠です。 【特集】アスペルガー障害 ・特集にあたって 十一元三 第1部 アスペルガー障害 Q&A集 Q1.アスペルガー障害とはどのような障害でしょうか? また,アスペルガー障害(症候群)という名前はどのようにしてつけられたのですか? Q2.アスペルガー障害が広く知られるようになったのはいつごろですか? Q3.アスペルガー障害と高機能自閉症とは同じですか? Q4.「発達障害」とアスペルガー障害の関係をわかりやすく教えてください。 Q5.注意欠陥/多動性障害(AD/HD)も最近話題になっていますが,アスペルガー障害とAD/HDとの間に何か関連はあるのでしょうか? Q6.アスペルガー障害と診断される人はどのくらいいるのですか? Q7.アスペルガー障害をもつ子どもの具体的特徴を教えてください。成人になると変化するのでしょうか? Q8.医療・教育などの面での日本における支援体制は整っているのでしょうか? Q9.むずかしい問題が起きた時に精神科医に相談したほうがよいでしょうか? Q10.アスペルガー障害の原因はわかっているのでしょうか? Q11.アスペルガー障害は遺伝と関係があるのでしょうか? Q12.アスペルガー障害によって生じやすい日常生活上の困難を教えてください。 Q13.入院は役に立つのでしょうか? Q14.治療について教えてください。 どのような治療法があるのでしょうか? Q15.脳のはたらきにも個性や特徴はあるのでしょうか? Q16.アスペルガー障害と診断される基準はどのようなものですか? Q17.薬は役に立つのでしょうか? Q18.アスペルガー障害の子どもは学校では個別に教育を受ける方がよいのでしょうか? Q19.アスペルガー障害をもつとわかるのはどのくらいの年齢ですか? Q20.地域性との関連はあるのですか? Q21.アスペルガー障害の人に特徴的な思考パターンはあるのでしょうか? Q22.アスペルガー障害にも知覚過敏や運動の苦手さはあるのでしょうか? Q23.癇癪やパニックを起こすのはわがままが原因ですか? Q24.親が子どものアスペルガー障害に気づく方法はありますか? Q25.アスペルガー障害の幼児をもつ家族が心がけるべき点はなんですか? Q26.アスペルガー障害を持つ大人のほうが同じ障害の子どもをよく理解できるのでしょうか? Q27.何故うまくコミュニケーションがとれないのですか? Q28.コミュニケーションを改善するヒントを教えてください。 Q29.アスペルガー障害をもつ大人がうまく社会生活するにはどうすればよいでしょうか? Q30.アスペルガー障害の人にとってわかりやすい話し方はありますか? Q31.今の学校の校長先生はアスペルガー障害のことをよく知っていますか? Q32.親と子どもにどうやって障害のことを伝えたらよいのですか? Q33.人付き合いの苦手を克服するため多くの人と交わればよいのでしょうか? Q34.アスペルガー障害の子どもの場合,学校でどう保健室を利用したらよいのでしょうか? Q35.医療と教育的な対応を連携するシステムはあるのでしょうか? Q36.アスペルガー障害とIQの関係について教えてください。 Q37.社会的事件とアスペルガー障害の関連が話題となっていますが。 Q38.子どもの育て方(愛情不足や過保護など)と関係はあるのでしょうか? Q39.引きこもりや不登校との関係はあるのでしょうか? Q40.社会人としての生活にどのような支障が生じやすいですか? Q41.高度な技術や非常に高い能力をもっている人も多いと聞きました。多くの天才がアスペルガー障害だというのは本当ですか? Q42.アスペルガー障害の人には友達ができないのですか? Q43.コレクションが趣味の人はアスペルガー障害なのですか? Q44.家庭裁判所でアスペルガー障害の少年を担当した調査官が心がけるべき点を教えてください。 Q45.結婚しているアスペルガー障害の人が家庭生活で直面する問題を教えてください。 Q46.戦争ゲームなど刺激の強いものに熱中するのですが大丈夫でしょうか? Q47.受診先や紹介先はどのように選べばよいでしょうか? Q48.民間の支援・援助団体について教えてください。 Q49.相談する窓口にはどのようなところがありますか? Q50.「特別支援教育」について教えてください。 第2部 ・情動的な対人コミュニケーションの神経メカニズム 佐藤弥 ・アスペルガー障害への早期からの療育支援 中林睦美 ・注意欠陥/多動性障害とアスペルガー障害の鑑別 岡田俊 ・高機能自閉症・アスペルガー障害における虐待の問題 崎濱盛三 ・アスペルガー障害と特別支援教育:現状と課題 岡田眞子 ・アスペルガー障害と少年事件 熊上崇 ・アスペルガー障害と家庭事件 —ライフサイクルの各段階における広汎性発達障害を有する成人の危機と司法的介入— 梅下節瑠 ・アスペルガー障害と高次対人状況 十一元三 ・矯正教育におけるアスペルガー障害少年への取り組み 松井俊史 ほか ・エビデンスからみた非行のリスクファクターと複合的相互作用 —少年院との共同研究の成果から— 松浦直己 〈コラム〉少年事件の取材を通して見えてきたもの 草薙厚子 【その他】 連載 ・映画にみる精神療法 第5回 —認知療法的映画鑑賞術— 高橋徹 ・[認知療法NEWS 第37号] 井上和臣 NPO法人 日本トゥレット協会会報 第11号 [日本EMDR学会ニューズレター 第12号] | 2,200円 |
 三省堂書店オンデマンド 星和書店 逆説心理療法 三省堂書店 | 内容紹介 逆説心理療法 G.R.ウィークス、L.ラベイト 著 篠木満、内田江里 訳 心理療法の効果的な治療技法には必ずといっていいほど逆説構造が隠れている。 本書は、逆説療法を体系的にまとめあげたものである。 十分に理解でき、実践できる内容は他に類をみない。 ・エスプレッソ・ブック・マシーンによって製本された書籍です。 ・表紙はソフトカバーです。 ・装丁がオリジナル書籍とは異なりますのでご了承くださいませ。 | 4,180円 |
 三省堂書店オンデマンド 星和書店 精神科治療学 第27巻03号 三省堂書店 | ◆内容紹介 【特集】 精神科臨床における「頭部外傷後遺症」の評価とマネジメント抄録 ・特集にあたって 堀川直史 ・脳外傷による高次脳機能障害が関心を集めた経緯 大橋正洋 ・頭部外傷に対する今日の脳外科の考え方 原 睦也,戸根 修,富田博樹 ・頭部外傷後に生じる脳の病理学的変化 平川公義 ・重症頭部外傷後に生じる認知機能障害 橋本圭司 ・頭部外傷後に生じる精神症状と行動変化 上田敬太,村井俊哉 ・軽度外傷性脳損傷(MTBI)後の認知機能障害 先崎 章 ・軽症頭部外傷後に生じる精神と行動の障害 堀川直史 ・頭部外傷後のPTSD 西 大輔,臼杵理人,松岡 豊 ・頭部外傷の画像診断 鳴海 滋,井田正博 ・認知機能障害の検査方法 是木明宏,船山道隆,村松太郎 ・頭部外傷後遺症の薬物療法 橋本 衛,池田 学 ・認知リハビリテーションの実際 山里道彦 ・小児の頭部外傷と頭部外傷後遺症の特徴 栗原まな ・高齢者の頭部外傷と頭部外傷後遺症の特徴 屋田 修,木村孝興,萬代秀樹 ・スポーツによる頭部外傷と頭部外傷後遺症の特徴 谷 諭 ・精神障害者と頭部外傷 高瀬 真,荒井 稔 ・頭部外傷は長期的にみたときに認知症やその他の精神障害の危険因子といえるのか,またどの程度の危険因子なのか 牧 陽子,山口晴保 ・頭部外傷後遺症と裁判および損害賠償請求の関係 高野真人 研究報告 ・SSRIによる中枢刺激症状の発現—問診票を用いた前方視研究の予備的調査— 辻 敬一郎,松久保 章,田島 治 臨床経験 ・Mirtazapine投与後に悪夢が生じた1例 正山 勝,辻 富基美,鵜飼 聡,他 Letters to the editor ・レビー小体型認知症の精神症状への問いかけ —塚本壇,山本健治,畠山佳久ほか:「アンモニア臭」を呈したレビー小体型認知症の一例.精神科治療学,25 ; 1097—1103, 2010. に寄せて— 上田 諭 連載 〔自著海外誌論文の紹介〕 ・CogState統合失調症バッテリー日本語版の妥当性 吉田泰介,管 心,有馬邦正,他 〔知っておきたい症状用語〕 ・夢幻・錯乱状態 岡野禎治 | 3,168円 |
 三省堂書店オンデマンド 星和書店 精神科臨床サービス Vol.13 No.3 Jul.2013 三省堂書店 | ◆内容紹介 ページ数:136ページ 【特集】 恋愛・結婚・子育て ・特集にあたって 鶴見隆彦第1章 総論:精神障害をもつ人の「恋愛・結婚・子育て」を支援するということ・精神障碍者の恋愛・結婚・子育てをめぐる障壁 池淵恵美・身体障がい領域では「恋愛・結婚・子育て」をどう受け止め,どう支援しているか 玉垣 努・精神障害をもつ人の「恋愛・結婚・子育て」のこれまで・これから 向谷地生良,伊藤恵里子,高田大志,池松麻穂,向谷地悦子第2章「恋愛・性・結婚・出産・子育て」にまつわる課題と支援のノウハウ・精神科病棟における性と恋愛:セクシュアリティの回復をめぐって 前田正治,坂本明子・デイケアにおける恋愛と性,結婚,出産,子育てへの支援 肥田裕久・日中活動支援の場での「ビバ恋愛!」 吉田久美子・居住支援における恋愛・性について 那須由香,林田輝子,田尾有樹子・妊娠・出産と薬物療法 松島英介・医療における妊娠・出産の生活支援 西尾雅明・子育て支援と虐待予防 宮崎全代・親が精神障がいである子どもたちへの生育支援 土田幸子・精神障害を抱える親のいる家庭への支援:オーストラリアCOPMI(Children of Parents with a Mental Illness)の取り組み 澤田いずみ,大野真実,塚本美奈第3章 私たちの「恋愛・結婚・子育て」・障害があっても恋愛・結婚 門馬賢治・統合失調症のお母さんの平凡な幸せ 北村庄子・家族の立場 中井和代・2人の結婚で広がった家族 根本勝子,川村昭子・あれやこれやで,結婚できませんでした。 野村義子・統合失調症の母と暮らした子ども時代を振り返って:その葛藤と回復,支援への手掛かりについて 夏苅郁子第4章 事例から学ぶ「恋愛・結婚・子育て」支援・医師の立場からの「恋愛・結婚・子育て」支援 三輪健一・子育て中の障害者をチームで支えるということ 松本光代・生きる力へとつながる子育て支援:親役割をもつ20の事例が教えてくれたこと 榎原紀子,栄セツコ・精神科デイケアでの恋愛・結婚支援 藤枝由美子,石橋綾,清水希実子,江口聡,管心,古川俊一・精神科デイケアにおける支援:土壌づくりから個別ケアまで 山埼勢津子第5章 さまざまな取り組みから学ぶ・身体に障害のある人の恋愛・結婚・子育てと「支援」 田中恵美子・知的障がいを抱える方への「恋愛・結婚・子育て」の支援から 松村真美・発達障害を抱える方への「恋愛・結婚・子育て」支援から 加藤 潔・当事者活動による障害者の恋愛や性活動支援 熊篠慶彦 | 2,420円 |
 三省堂書店オンデマンド星和書店 精神科治療学 Vol.32 No.6 Jun.2017 三省堂書店 | ◆内容紹介 ページ数:138ページ 【特集】 周産期メンタルケア─多職種連携の作り方─ ・特集にあたって渡邉博幸・周産期メンタルケアの現状と展望岡野禎治・精神保健と母子保健の連携はなぜ困難なのか?─ 3 つの連携障壁とその解決─渡邉博幸,榎原雅代・周産期メンタルケア外来(精神科設置)菊地紗耶,小林奈津子,本多奈美 他・周産期メンタルヘルス外来の立ち上げ方安田貴昭,大賀公子,志賀浪貴文 他・総合病院での周産期メンタルヘルスケア連携─産科医の立場から西郡秀和・総合病院での周産期メンタルケア連携─精神科医の立場から─武藤仁志,竹内 崇・産科入院事例への多職種ケア清野仁美,湖海正尋,松永寿人・多職種協働における助産師の役割小澤千恵・精神疾患合併妊婦・授乳婦における薬物療法に対する薬剤師の取り組み川口寿子,南雲まい,影山名織 他・周産期メンタルヘルスにおけるリエゾン精神看護専門看護師の役割宮田 郁・マタニティーホスピタルでの精神科診療高橋由美子,横田英巳,松川幸英 他・産科医院における心理カウンセリング窪谷 潔,望月 愛,小路和子 他・地域の周産期メンタルヘルスケアのために精神科診療所では何ができるか?武田直己・単科精神科医療機関における「周産期メンタルヘルス専門外来」のリエゾン活動岡野禎治,岩佐貴史,森川将行・周産期メンタルケアにおける自助グループの役割と今後の課題─自助グループリーダーおよび心理職の立場から─宮崎弘美・妊娠期からの切れ目ない連携支援体制づくり立花良之,小泉典章・大阪府の妊産婦メンタルケア体制強化事業岡本陽子,和田聡子,光田信明・社会的ハイリスク妊娠に対する保健師の取り組み─妊娠・出産・育児の切れ目ない相談・支援のしくみ「名張版ネウボラ」より─上田紀子・児童虐待防止に向けた地方自治体と医療機関との円滑な連携促進の取り組み─千葉県および松戸市における児童福祉と医療の連携の実際─三平 元・嬰児殺・新生児殺事例から見た周産期メンタルヘルスの現状と課題田口寿子・特定妊婦に関する情報提供と法的諸問題石川博康・精神科医療者の周産期メンタルヘルスリテラシーの向上のために鈴木利人【研究報告】・抑うつ症状を伴う睡眠相後退症候群に対するaripiprazole の有効性の単群試験による検討大森佑貴,神林 崇,高木 学 他【臨床経験】・不整脈に対してカテーテル治療あるいはペースメーカー留置を行った老年期うつ病患者に修正型電気けいれん療法が奏効した2 症例近江 翼,金井講治,陸 馨仙 他 | 3,168円 |
 三省堂書店オンデマンド星和書店 こころのりんしょう a・la・carte 第28巻03号 三省堂書店 | ◆内容紹介 【特集】 精神鑑定と責任能力吉川和男 編集・特集にあたって吉川和男第1部 精神鑑定と責任能力 Q&A集Q1 精神鑑定とは,何を鑑定するのでしょうか? 鑑定とは,どういうことを意味しているのでしょうか?Q2 なぜ,どのような時に精神鑑定が必要になるのでしょうか?Q3 精神鑑定をしている精神科医はどのような方ですか?Q4 精神鑑定を行うための資格はあるのでしょうか? 精神鑑定を学ぶためには,どのような研修制度や学び方がありますか?Q5 精神鑑定は誰の依頼で行われるのですか? 誰が必要だと決めるのでしょうか?Q6 精神鑑定は,精神疾患が疑われる人に対して行われるものなのでしょうか? 健常者に対しても行われるのでしょうか?Q7 精神鑑定では,どのような検査が行われるのでしょうか? 心理テストなども使われるのでしょうか?Q8 精神鑑定にはいろいろな種類があるのでしょうか?Q9 精神鑑定に要する時間はどのくらいなのでしょうか?Q10 精神鑑定の報告書は,どのくらいの分量になるのでしょうか?Q11 精神鑑定は,精神科診断とは異なるのでしょうか?Q12 精神鑑定では,精神科診断をつけることが目的ですか? あるいは,責任能力の有無を判断することでしょうか?Q13 精神鑑定で精神障害のふりをしている人を見分けられますか?Q14 精神鑑定の途中で,心理検査などが必要になった場合は,心理士に依頼できるのでしょうか?Q15 精神鑑定中に精神障害に対する治療はしますか?Q16 精神鑑定書は,誰に見せてもいいものなのでしょうか?Q17 裁判官など司法関係者は,精神医学の知識をもっているのでしょうか?Q18 被疑者や被告人が精神鑑定を希望することはできますか?Q19 犯罪を犯した人の精神鑑定では,精神科診断をつけるのですか?Q20 事件後すぐにではなくかなり時間がたって精神鑑定を始める場合,当時の状況を正確に把握できるのでしょうか?Q21 心神喪失というのは,どのような精神科の症状なのでしょうか?Q22 統合失調症と診断された場合,責任能力なしとなるのでしょうか?Q23 精神鑑定医が心神喪失と判定した場合,それを認めるかどうかは裁判官に委ねられているのでしょうか?Q24 精神鑑定の結果を裁判官は必ず採用するのですか?Q25 他の国でも精神鑑定はやっているのですか?Q26 精神鑑定を受けずに罰せられる精神障害の方もいますか?Q27 心神喪失で痴漢行為や婦女暴行を行った場合の処遇はどうなるのでしょうか?Q28 精神鑑定を受けて無罪になった人はどうなりますか?Q29 精神鑑定を受けて有罪になった人はどうなりますか?Q30 犯罪を犯した精神疾患を持つ人に,精神科の治療は行われるのでしょうか? 治療を受けることはできるのでしょうか?Q31 有罪となった精神障害を持つ人の治療は,どのように行われるのでしょうか?Q32 刑務所で精神障害になった人は精神鑑定を受けることはできませんか?Q33 覚せい剤など麻薬摂取の場合,それ自体違法なのですが,犯罪が行われた場合,どうなるのでしょうか?Q34 暴力事件を起こすときの精神状況は,どのようなものでしょうか?Q35 暴力行為で検挙された精神疾患を持つ人は,治療を受けていなかったからでしょうか?Q36 どのような精神疾患の有無が問題になるのでしょうか?Q37 犯罪を犯した人が精神疾患を持つ場合,どのような精神疾患が考えられますか?Q38 アルコール依存症という診断がなされた場合,どのように判断されるのでしょうか?Q39 婦女暴行での受刑期間が終わって社会に出てきたとたんに犯罪を繰り返すのは,精神科の治療が行われなかったからなのでしょうか?Q40 精神鑑定はなぜ何度も行われるのですか? それぞれの結果が異なっていることもありますか? もし異なる結果がいくつかあるとすると,真実味がないように見えますが。Q41 結果が異なるということがないような客観的な鑑定方法はないのでしょうか? 例えば血液検査の結果のような。Q42 精神科の治療を受けているとき犯罪を犯した場合,責任は治療者にあるのでしょうか?Q43 精神障害であるからといって罰せられないのはおかしくないですか?Q44 精神鑑定の結果,鑑定を受けた人が死刑になることは医師のモラルに反しませんか?Q45 精神鑑定の結果,無罪や執行猶予,不起訴処分を受けた人は,重大な犯罪を行いながら,一切の罪も問われずに無条件に社会に釈放されてしまうのですか?Q46 精神鑑定は捜査の一環として中立な立場で行うべきではないですか?Q47 裁判員制度になって,一般の人が裁判員になる場合,これらの人に精神医学の知識を勉強してもらう必要があると思いますが,これは義務的に要求されるのでしょうか?Q48 裁判員裁判ではどのようなときに精神鑑定を行いますか?Q49 裁判員裁判ではどのような精神鑑定を行いますか?Q50 裁判員はどのようにして責任能力を判断すればよいですか?第2部・〈座談会〉新たな法制度における精神鑑定と責任能力のあり方吉川和男,中谷陽二,十一元三,福井裕輝・精神鑑定をめぐる諸問題吉川和男一・司法精神医学と患者の人権中田修・責任能力判定の歴史西山詮・人格障害犯罪者の刑事責任能力加藤久雄・責任能力について語る前に—精神鑑定と「藪の中」—中谷陽二・広汎性発達障害と精神鑑定十一元三・責任能力と自由意思安田拓人・情動犯罪の責任能力吉川真理・精神障害と触法行為大下顕・鑑定人と裁判官の責任能力判断の実態大澤達哉・脳と責任能力福井裕輝【連載】 ・アメリカ こころの臨床ツアー 第3回 丹野義彦・認知療法NEWS 第50号・NPO法人 日本トゥレット協会会報 第25号・バックナンバー案内 | 2,200円 |
 三省堂書店オンデマンド 星和書店 臨床精神薬理 第11巻08号 三省堂書店 | 【特集】 ドパミン再考 ドパミン神経伝達のtonic/phasic仮説に基づくaripiprazoleの薬理作用—Phasic component buster仮説を中心に 浜村貴史,児玉匡史,原田俊樹統合失調症再発予防効果におけるドパミンの役割 久住一郎,小山司 抗うつ効果におけるドパミンの役割 樋口久,山口登躁病におけるドーパミン仮説武田俊彦ドパミン関連遺伝子と抗精神病薬の薬物反応性との関連古郡規雄ドパミンアゴニストの副作用・随伴症状—最近の話題田中輝明,井上猛,小山司【シリーズ・他】 そこが知りたい薬物療法Q&A萩野谷真人,渡邊崇,大曽根彰,下田和孝薬の使い方Quetiapineを使いこなす第2回至適用量と等価換算稲垣中,稲田俊也【原著論文】 統合失調症患者における精神症状・病識・アドヒアランスの関連性について高木恵子,亀井浩行,西田幹夫,他慢性統合失調症患者に対する急速増量法を用いたquetiapineへのスイッチングの有用性諸治隆嗣,宇佐見和哉,大久保武人統合失調症急性期治療におけるolanzapine口腔内崩壊錠の可能性吉川憲人Olanzapineによる急性期治療後のoutcomeに関する検討—治療継続からみたolanzapineのtreatment effectiveness杉山克樹,中田信浩,松木武敏,他Perospironeの初発統合失調症に対する市販後調査—有効性と安全性の検討村崎光邦,小山司,伊豫雅臣,他長期入院精神障害者の退院促進要因の分析:Psychoms?を用いたバリアンス分析結果と薬剤との関係谷岡哲也,川村亜以,大坂京子,他【症例報告】 経口血糖降下薬二次無効となった統合失調症患者においてインシュリン導入から抗精神病薬の減量に結びついた1例松田公子,福尾ゆかり,福田一,他【紹介】 GAD研究会が提唱する本邦における『GAD治療手順』中込和幸,牛島定信,大坪天平,他【講演紹介】 抗精神病薬における薬物動態,薬力学の問題Siegfried Kasper(監訳/木下利彦)【座談会】 初発統合失調症の病態と治療およびquetiapineの位置づけRene Sylvain Kahn,齊藤卓弥,宮本聖也,堤祐一郎(司会)【対談】 服薬アドヒアランスによる統合失調症再発予防伊豫雅臣,渡邊衡一郎 | 3,190円 |
 三省堂書店オンデマンド星和書店 精神科治療学 第18巻増刊号 精神科救急ガイドライン 三省堂書店 | ◆内容紹介 精神科救急の現場は,迅速かつ的確な治療対応が求められるため,ガイドラインがもっとも要請される領域であると考えられる。 本増刊号の特色は、従来の成書がいきなり「状態像ごとの治療的対応」から記載が始まるものが多いことを踏まえ、救急において もっとも重要なものでありながら記載が少なかった「状態像の診分け」に1章を割き(第1章)、受診動機を出発点にどのような 鑑別診断が 行われていくかを、症例記載も入れて詳述する点にある。日本の精神科救急の第一線で活躍する執筆陣を揃え、 現時点における精神科救急のガイドラインとして最良・最高の内容を誇る。 第1章 状態像の診分け 1.訳のわからないことを言って、暴れている 八田耕太郎 2.騒いで、しゃべりまくっている 大塚公一郎 加藤敏 3.怒りっぽく、攻撃的である 兼本浩祐 吉田典代 新井啓之 4.居ても立ってもおられない 下村昇 市田勝 5.ぼおっとして、戸惑っている 細川清 小林建太郎 李陽明 6.動かず、何も言わない 日野原圭 加藤敏 7.「死ぬのではないか」と不安におののいている、息をハアハアしている 松丸憲太郎 上島国利 8.けいれんしている 兼本浩祐 大島智弘 深谷修平 9.記憶がない 兼本浩祐 三宅芳子 渡辺雅子 10.手首・前腕を切った 福島春子 中井祥博 岩尾俊一郎 山口直彦 11.大量の薬を飲んだ 神尾聡 12.(抗精神病薬を服用中の患者が)体が突っ張っている,眼が吊り上がっている 山口直彦 中元幸治 13.(向精神薬を服用中の患者が)グッタリとして、顔面蒼白であるが高熱を発している 西嶋康一 第2章.精神科救急に必要な検査と処置 1.検査 1)種類と手技 神尾聡 2)検査値の読み方 八田耕太郎 2.処置 1)鎮静法 八田耕太郎 2)身体拘束 神尾聡 3)電気けいれん療法(electroconvulsive therapy:ECT) 中村満 一瀬邦弘 島陽一 奥村正紀 関口佳穂子 道行隆 今村達弥 清水研 山田建志 竹林宏 益富一郎 清水恵子 第3章. 状態像ごとの治療的対応 1.緊張病性興奮 八田耕太郎 2.幻覚妄想状態 八田耕太郎 3.意識変容状態(せん妄や夢幻-錯乱状態) 八田耕太郎 4.躁状態 大塚公一郎 加藤敏 5.てんかん性不機嫌症 兼本浩祐 森真琴 大島智弘 6.不安焦躁状態 下村昇 市田勝 7.困惑状態,アメンチア,もうろう状態,発作性昏迷 ictal stupor(spike-wave stupor) 細川清 小林建太郎 李陽明 8.昏迷状態 日野原圭 加藤敏 9.パニック発作・過換気症候群 松丸憲太郎 上島国利 10.けいれんおよびけいれん発作重積状態 兼本浩祐 大島智弘 11.一過性全健忘 三宅芳子 兼本浩祐 12.全生活史健忘 兼本浩祐 多羅尾陽子 13.リストカット 福島春子 中井祥博 岩尾俊一郎 山口直彦 14.大量服薬 神尾聡 15.アカシジア 下村昇 市田勝 16.急性ジストニア,眼球上転発作 山口直彦 青木信生 17.悪性症候群 西嶋康一 第4章.精神科救急に必要な法的あるいは実務上の知識 1.受診希望あるいは相談の電話に対する対応 1)トリアージュ機能とカウンセリング機能 平田豊明 2)大量服薬の場合 上條吉人 2.精神科救急の実務に関わる法の運用 平田豊明 3.患者・家族に説明すべきこと—精神科救急とインフォームドコンセント— 白石弘巳 4.精神科救急と刑事司法の接点—その司法精神医学的課題と対策— 武井満 | 6,490円 |
 三省堂書店オンデマンド星和書店 精神科治療学23巻増刊号 三省堂書店 | ◆内容紹介 ページ数:397ページ 発達障害がますます注目されるなど、わが国における児童精神科領域のニーズは高まるばかりで、診断や治療の進歩を踏まえた新しいガイドラインが求められていることから、このたび児童・青年期の精神障害治療ガイドラインを刊行する 運びとなった。執筆陣は現在、児童精神科医療の第一線で活躍されている方々を揃えた。児童精神科のみならず、一般精神科や教育・福祉領域においても必ず役立つ一冊。編集:「精神科治療学」編集委員会 B5判 並製 400頁 通巻263号 | 6,490円 |
 三省堂書店オンデマンド星和書店 臨床精神薬理 第15巻09号 三省堂書店 | ◆内容紹介 ページ数:172ページ 【展望】・Lithium療法の歴史と現状渡邉 昌祐【特集】 Lithium再考:多様なムードスタビライザーの時代にlithiumを再考する・Lithiumの作用メカニズムはどこまで分かったのか?伊賀 淳一,大森 哲郎・神経心理学的側面からみたlithiumの効果長田 泉美,兼子 幸一・ムードスタビライザーとしてのlithiumの位置づけを巡る議論吉村 直記,大坪 天平・双極性障害に対するlithium療法の実際近藤 毅・Lithiumによるaugmentation療法を巡る問題菅原 裕子,坂元 薫,石郷岡 純・自殺防止とlithium寺尾 岳,石井 啓義・長期lithium療法の安全性——維持療法の際に注意すべきポイント鷲塚 伸介シリーズ・そこが知りたい 薬物療法Q&A井桁 裕文,常山 暢人,染矢 俊幸原著論文・Aripiprazoleの外来処方調査——5年転帰データからみる長期有用性の検討住吉 秋次・認知症へのmemantine実践的投与:鎮静効果による介護負担軽減と活動性低下などの副作用を減らす減量投与について山口 晴保,牧 陽子,山口 智晴 他・RLAIを投与した35症例の症状・薬剤量の変化の調査——外来群と入院およびグループホーム入居患者群の比較をまじえて立花憲一郎,鈴木 滋,大島 智弘 他・統合失調症薬物療法治療においてaripiprazoleの薬理特性を考慮した使用方法に関する検討下山 武・Ramelteon投与によるベンゾジアゼピン系・非ベンゾジアゼピン系睡眠薬離脱へのアプローチ小林 和人症例報告・Clozapineによって頻回の解離症状・自傷行為が消失した治療抵抗性統合失調症の1例宮澤 惇宏,榎原 雅代,金原 信久 他Letters to the editor・Activation syndromeについての誤解を招かないために石川 博康私が歩んだ向精神薬開発の道——秘話でつづる向精神薬開発の歴史・第14回 Triazolo benzodiazepine物語——その3 失われたbenzodiazepine系抗うつ薬の物語村崎 光邦座談会・統合失調症:新しい薬物治療の展望——グルタミン酸神経伝達を中心に樋口 輝彦,Joseph Coyle,西川 徹,久住 一郎・診断基準改訂の方向性(DSM-IVからDSM-5へ)とうつ病・不安障害治療の最適化塩入 俊樹,松永 寿人,鈴木雄太郎 | 3,190円 |
 三省堂書店オンデマンド 星和書店 臨床精神薬理11-5 三省堂書店 | ◆内容紹介 ページ数:228ページ 【特集】 Blonanserinへの期待 ・Blonanserin誕生の研究経緯と基礎薬理 久留宮聰,釆輝昭・わが国におけるblonanserinの臨床試験成績 石郷岡純・Blonanserinの急性期患者への可能性 堤 祐一郎・ドパミン−セロトニン拮抗薬—新規統合失調症治療薬blonanserinの受容体結合特性 村崎光邦,西川弘之,石橋正 座談会・新規抗精神病薬blonanserinへの期待 村崎光邦(司会),石郷岡純,久住一郎,渡邊衡一郎,宮本聖也,武田俊彦【新薬紹介】 ・Blonanserinの基礎と臨床 村崎 光邦【シリーズ・他】 ・第21回新規抗精神病薬の等価換算(その5):Blonanserin 稲垣中,稲田俊也・そこが知りたい薬物療法Q&A 杉本篤言、福井直樹、染矢俊幸・そこが知りたい薬物療法Q&A 渡邊崇、大曽根彰、下田和孝【原著論文】 ・日本人健康成人男子におけるblonanserinとerythromycinとの薬物相互作用の検討 松本和也、安本和善、中村洋、他・日本人健康成人男子におけるblonanserinとグレープフルーツジュースとの相互作用の検討 松本和也、安本和善、中村洋、他・統合失調症入院患者におけるメタボリックシンドローム有病率の検討 松田幸彦、梅原慈美、渡邊彩見、他・新規抗精神病薬quetiapineの薬理作用メカニズムについて —D2以外の受容体に対する作用を中心に 竹内崇、西川徹・Risperidone内用液1mg/mLの使用成績調査 —Risperidone内用液の安全性と服薬アドヒアランスの確保に向けて 伊豫雅臣、小川嘉正、橋元佐代子、他【総説】 ・てんかん患者のQOL研究ならびにQOLへのlamotrigineの影響 久保田英幹、八木和一【座談会】 ・ジェネリック医薬品を含めた薬剤選択とインフォームドコンセント 政田幹夫、岡村武彦、吉本哲也、西元善幸(司会)、松本暢代【講演紹介】 Aripiprazole発売1周年記念講演会・開会にあたって 鮫島健・開会にあたって 高橋清久 セッション1・統合失調症およびその治療に対する基礎的アプローチ AnissaAbi-Dargham(監訳/石郷岡純)・統合失調症治療にaripiprazoleを使用したスペインでの臨床経験 FernandoCanas(監訳/石郷岡純 セッション2:パネルディスカッション・Aripiprazoleをどう使いこなすか 上島国利、伊豫雅臣、大下隆司、他・閉会にあたって 山内俊雄・閉会にあたって 佐藤光源 | 3,190円 |
 三省堂書店オンデマンド 星和書店 精神科臨床サービス3-4 三省堂書店 | ◆内容紹介 ページ数:124ページ 【特集】これだけは知っておきたい— エンパワメント:当事者が力を発揮するのをどう援助するか(I) [第1部]総論・自己回復力を考える—精神医学史の視点から— 田辺英・当事者が力を発揮するのをどう援助するか—福祉の立場から— 田中英樹・身体障害者の「自立」に向けての支援—視点と方法— 小澤温[第2部]援助理念・自己決定をめぐって 門屋充郎・精神科領域でのインフォームド・コンセント—説明による同意をこえて— 中谷真樹・アドヴォカシー 池原毅和・どう創る、わがまちのノーマライゼーション 藤井克徳・エンパワメント 稲沢公一・患者会などのセルフヘルプグループで蓄えられてきた援助の原理 —ヘルパーセラピーの原理とプロシューマーへの変換を中心にして— 岩田泰夫・自立生活運動—精神障害分野との共通点— 圓山里子[第3部]援助技術・当事者の力をひきだす治療・援助関係 村上雅昭 稲井友理子 高橋佳代 ほか・統合失調症の薬物療法 内田裕之・自己対処技法の獲得を援助する方法—認知行動療法に基づくSST— 前田ケイ・当事者への心理教育 内野俊郎 前田正治・ストレングス視点に基づく生活支援 三品桂子・ピアカウンセリング 寺谷隆子・サポートグループ 蔭山正子<連載>・精神医学・医療の今昔(第4回:精神医学・医療の革命) 山下格 | 2,200円 |